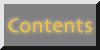
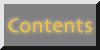 |
第1節 第1期(明治32年〜明治40年)
京都大学附属図書館は,閲覧の開始された明治32年(1899)12月11日を創立の日としている。しかし実際の図書事務はこれより先,明治30年(1897)京都帝国大学が創設されるとともに,理工科大学教室の一部に仮図書室を設けて,購入図書および文部省,東京帝国大学,第三高等学校,帝国図書館等から移管された図書の整理をはじめた。
本館の創設された明治32年という年は,わが国における近代図書館発達史の上で忘れることのできない年である。すなわち本館創立日の約1カ月前の11月11日,わが国最初の「図書館令」が,勅令第429号をもって公布された。「図書館令」の附則第8条に「諸学校通則第三条中及小学校令中書籍館及図書館ニ関スル規定ハ之ヲ廃止ス」とあるように,それまでは明治19年の「諸学校通則」,明治23年の「小学校令」の一部をもって,図書館の設置運営に関する方策が指示されていたにすぎない。それがいま,学校から分離して,独立の規程をもって統轄されることになったのは,従来学校教育の補助機関的に見られていた図書館が,はじめて独立の社会教育機関として確立されたことを意味すると言えよう。図書館令公布後,全国の図書館数は飛躍的に増大し,明治32年全国国公私立図書館数は43館であったのが,34年には50館,37年100館,41年200館,そして明治45年には541館と増加していったのである。京都大学附属図書館は,日本における近代図書館発展の跳躍台となった図書館令公布の年に産声をあげたのである。 明治30年6月18日勅令第209号によって京都帝国大学が創設されるとともに,同日勅令第208号によって,それまで東京にのみあった帝国大学が東京帝国大学と改称された。それと同時に同じく勅令をもって両帝国大学の官制が定められ,帝国大学附属図書館および図書館長の名称が官制にはじめて明記された。今日全国立大学に附属する図書館の名称である「附属図書館」および「図書館長」という名称は,本学創立の日をもって始まったのである。
それ以前,すなわち東京帝国大学が帝国大学令による唯一の帝国大学であった時代の帝国大学官制(明治26年)には,医科大学附属病院および理科大学附属東京天文台はすでに見えているが,附属図書館および図書館長という名称はない。「東京帝国大学五十年史」によれば,明治10年以前には,法理文3学部には書籍縦覧室あるいは図書室と称する設備があっただけであるが,明治14年,はじめて東京大学図書館規則が制定されたという。ついで明治19年3月,東京大学が帝国大学と改められるとともに,東京大学図書館も帝国大学図書館と改称され,新たに帝国大学図書館規則が制定された。しかし,この規則にも図書館長という名称は全く見えず,貴重図書・参考図書等の借受に関しては,「総長ノ特許」を得ることになっている。官制上図書館長を置くことはまだ認められていなかったが,館務の統轄上,明治14年東京大学図書館規則が制定された後,法理文3学部と医学部と各別に,図書課取締または図書課監督が置かれ,教授または助教授の中より総長が任命した。その後図書館管理が置かれ,以前と同様に,教授または助教授をもってこれにあてていた。つまり本学創立の日まで,東京大学にも正式の官制上で認められた附属図書館や図書館長はなく,図書館に関することは,ただ学内的にのみ規制されているにすぎなかった。したがって官制上正式に認められた附属図書館は,本館と東京大学附属図書館をもって嚆矢とするわけである。
本館はこのような歴史的意味をになって創設されたのであるが,本館創立の明治32年には,東京大学はすでに和洋あわせて266,200冊の蔵書を誇っていた。もともと京都大学の開設は,わが国に大学がただ一つである限り,たがいに競学の風を欠き,清新なる学術の発達は期しがたいという,当時の一般的世論にもよるものであったから,本学の東京大学に対する独特の使命というものは,本学創設当時のひとびとには強く意識されていた。したがって教育・研究にとって欠くべからざる図書館の充実は,もっとも緊急を要する事柄でなければならなかった。
初代総長木下広次は,とくに図書館について深い関心を払い,関西唯一の大学創立のため,広く図書の寄贈を有識者に懇請するとともに,自らもその蔵書を本学に寄贈した。木下総長は明治19年3月より22年10月まで,(東京)帝国大学教授として初代の図書館管理を兼ね,親しく図書館行政の衝に当り,図書館を理解すること甚だ深かったことは,本館にとってまことに幸いであった。
木下総長は本学の創設から10日を経た明治30年6月28日付で,本学総長に任ぜられたが,当時の木下総長の図書館に対する考え方の一端について,大阪毎日新聞(明治30年8月29日付)は次のように報じている。
 |
|
初代総長木下博士肖像
浅井忠画(本館所蔵) |
京都帝国大学附属図書館の設立 ―木下総長の談片―
図書館は勿論設定するの方針を採り既に其設計にかかり居れり。而して設立の暁には勿論公開に為すの見込にて,即ち学生の研究上に要する書籍の外は勿論,誰人にても閲覧するの便利を与えんこと蓋し困難の事に非ずと思えり。元来図書館は人民の必要に迫られて設立するものに非ずして,之を設立して置きて何時にても其用に充てん覚悟なかるべからざるものなり。欧洲にては図書館の完不完をもって,各地方の程度如何を測度するの観あり。而して我国の如き東京に唯一あるのみ。故に一事を調査せんとすれば,遠方の者と雖ども東京に出でざるべからず。不便も亦甚しと云ふべし。故に京都に之を開設して我国西部の必要に応ずべし。殊に山城・大和は昔時より歴史の中心となり居れば,其旧記のみにても蓋し非常に大部なるべく,又京都地方は宗教の中心として,此等の学科を研究するものに不便なからしむべし云々。
また明治34年4月,関西文庫協会より発行された同会の機関誌「東壁」創刊号は,「図書蒐集の必要を論ず」と題する木下総長の演説筆記を掲げているが,その中で総長は,まず最初に「抑図書館の事は書籍の蒐集其分類及び配置等普通の学識を要するのみでなく一種の専門的事業であって決して素人の云為する事ではありませぬ」と,図書館の業務が専門的業務であることをはっきりと認め,ついで「私は図書館が社会上に於ける位置は極めて重要な位置であって国家の文明を進むる上に於て欠くべからざる機関であるといふことを確く信ずるのであります」と,述べている。ところが当時の実情は「東京市に至っては此の社会教育の重要機関に向って何等の意念なきかの様に思はれ我帝国の首府としては遺憾なことであります」という状態であった。かえって維新前には,大藩と言われる城下には必ず藩校があり,必要な図書を収集して城下の子弟を教育していた。「然るに王政維新は旧来の事物を一掃したるの結果各地の図書館は一二を除くの外挙て跡形なく散逸せしめました此維新は古書旧籍の運命上実に急劇残忍の革命でありました」。こうして維新後貴重な図書が無残にも散逸していったのであるが,「其当時の帝国議会は滅法無闇に図書館の費目を削減しつつありました」。そこで京都帝国大学の図書館では「経費の許す限りに於て出来る丈図書の購買に従事したいと思ひます。又図書購買の外に古文書謄写の一事は最も本館に須要の事業と考えます」。「若し一朝社寺に火災でもありましたならば実に千歳の遺憾である故に大学の事業として是非とも全国の古文書少くとも京都近傍の古文書を複写しやうと思ひます此の如くにして始めて帝国大学の図書館が社会に尽す一方面の仕事は満足したものと思ひます」と,結んでいる。
このような総長の指導理念のもとに,本館は創設の努力を続けたのであるが,そのためには創設の任に堪えうる人材が必要であった。
明治30年12月,京都大学は,当時東京帝国大学大学院学生であった島文次郎に,図書館に関する研究を嘱託し,32年2月には,本館創立事務を嘱託した。さらに同年11月6日付で,島文次郎は法科大学助教授に任ぜられるとともに,附属図書館長に補せられた。
本学の創立とともに,東京帝国大学も官制が改正され,附属図書館に館長を置くことになり,明治30年6月28日付で,それまでの図書館管理であった和田万吉助教授が館長に任命された。官制によれば,館長は「教授助教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス」となっていたのであるが,東西の両帝国大学の図書館長は,このように助教授をもって出発したのである。
本館は館長の任命とともに,また一方帝国図書館よりは笹岡民次郎,その他新進の図書館員を迎え,かくて人的機構においても,逐次その陣容を整備するに至ったので,32年12月11日いよいよ閲覧室を開室することになった。開館当初の本館人員は,館長1,書記2,雇員2,閲覧掛見習2,小使2,臨時雇2の計11名であり,その機構は次の通りであった。
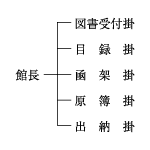
図書館運営のためには,運営のための一定の凖拠がなければならない。本学創立後直ちに,本学へ図書・標本等の寄贈を広く仰ぐため,「図書標本等寄贈手続」を定めるとともに,翌31年3月16日には,本学舎監石川一を図書館事務取調委員に任命し,図書館規則制定の凖備に着手した。同年4月5日には,石川一は早くも京都帝国大学図書館規則および同規則執行手続案を木下総長宛報告している。
同年7月には,煉瓦造2階建延70坪の書庫(第1書庫)が,図書館の最初の建物としてまず完成した。しかし閲覧室,事務室はまだ完成していなかったので,閲覧のための規則は必要ではなかったが,図書の一応の整理がつくとともに,図書貸出の必要は起ってきたのであろう。同年12月2日には,とりあえず「京都帝国大学図書借受仮規則」が制定された。まだ正式に附属図書館は創設されていなかったので,最初の仮規則はこのような名称で呼ばれたのである。
| 第1条 本学教授,助教授,講師及助手等ニシテ参考用トシテ本学備付ノ図書ヲ借受セントスルモノハ左ノ冊数ニ限リ之ヲ貸付ス | |||
| 教授助教授講師 | 20冊以内 | ||
| 助手 | 10冊以内 | ||
| 以上ニ属セサルモノ | 5冊以内 | ||
| 但公用ノ為メ借受スル図書ニハ冊数ヲ制限セス | |||
| 第2条 借受ノ冊数ハ洋装ノモノニ就テ之ヲ定メ和漢装ノモノハ1幅又ハ1帙ヲ以テ1冊トシ装釘セサル遂次刊行ノ書ニシテ数号ヲ以テ完冊ヲナスモノハ其一完冊ヲナスマテノ若干号ヲ合セテ1冊ト見做ス | |||
| 但逐次刊行書ハ装釘ノ上ニアラサレハ貸付セス | |||
| 第3条 前条ノ図書ハ借受者其保存ニ任シ図書掛ノ臨時点検ヲ通知スルトキハ必ス通知ノ翌日中ニ図書室ヘ現物ヲ差出スヘシ | |||
| 第4条 図書ヲ借受セントスルモノハ自ラ図書室ニ至リ図書借用紙ニ書名番号姓名月日ヲ詳記シ捺印ノ上之ヲ差出スヘシ | |||
| 但貴重図書ハ一切之ヲ貸付セス委託図書ハ借受ノ都度総長ノ許可ヲ経ヘシ | |||
| 第5条 借受シタル図書ハ他ニ転貸スルヲ許サス | |||
| 第6条 借受シタル図書ハ常式点検ノタメ毎年7月1日ヨリ10日迄ニ返納スルモノトス | |||
| 第7条 教授,助教授及講師ハ仮書庫内ニ入リ図書ヲ検索スルコトヲ得 | |||
| 第8条 学生ノ教科書及参考書ヲ自弁スルコト能ハサルモノハ受持教員ノ保認証ヲ出セルモノニ限リ貸付スルコトアルヘシ | |||
| 第9条 借受シタル図書ヲ毀損汚染又ハ紛失シタルモノハ同一ノ書ヲ以テ償ハシム但時宜ニヨリ代金ヲ以テ償ハシムルコトアルヘシ | |||
| 第10条 職員ノ退職シ或ハ転任シタルモノ及学生ノ退学シタルモノハ其借受セル図書ヲ直ニ返納スヘシ,尤モ卒業シタル学生ハ卒業証書ヲ受クル前ニ必ス返納スヘシ | |||
| 第11条 此規則ヲ犯シタルモノハ其情況ノ軽重ニ由リ1週日以上1ケ年以内図書ノ借受ヲ許ササルコトアルヘシ | |||
| 第12条 図書ノ返納ヲ怠リ督促ヲ受クルモ尚ホ返納セサルトキハ相当ノ処分ヲナスヘシ | |||
32年7月には,閲覧室,事務室も竣工し,蒸気暖房工事や,その他の設備も整ったので,理工科大学内の仮図書室より移転した。こうしていよいよ開館もせまり,11月6日付で館長の任命もみたので,ここではじめて「京都帝国大学附属図書館規則」および「京都帝国大学附属図書館規則執行手続」が制定された。
 |
|
創設当時の閲覧室玄関
|
 |
|
東側からみた閲覧室
|
| 京都帝国大学附属図書館規則 | ||
| 第1条 京都帝国大学附属図書館ハ京都帝国大学ノ図書ヲ貯蔵スル所トス | ||
| 第2条 本館ニ於テ貯蔵保管スル図書ヲ左ノ2種トス | ||
| 第1 貴重図書 | ||
| 第2 通常図書 | ||
| 第3条 本館吏員ノ外図書ノ出納ヲ為スコトヲ許サス | ||
| 第4条 公用トシテ本館ノ図書ヲ借受クヘキ者ハ本部ニ於テハ書記官,各分科大学ニ於テハ大学長若クハ学科主任ノ教授,医科大学附属病院ニ於テハ医院長トシ其借受冊数ヲ制限セス | ||
| 参考用トシテ本館ノ図書ヲ借受クヘキ者ハ職員及総長ヨリ図書借受ノ特許ヲ得タル者トシ其借受冊数及日数制限ハ総長之ヲ規定ス | ||
| 第5条 職員学生生徒及総長ヨリ図書閲覧ノ特許ヲ得タル者ハ本館閲覧室ニ入リテ図書ヲ閲覧スルコトヲ得 | ||
| 第6条 貴重図書,辞書及諸学科ニ通スル参考書ハ一切之ヲ貸付スルコトヲ得ス,貴重図書ノ閲覧ハ其都度総長ノ特許ヲ得タル後之ヲ許可ス | ||
| 第7条 学生ノ教科書若クハ参考書ハ学科主任教授ノ申出ニ依リ当該分科大学長ノ保認証ヲ得タル者ニ限リ之ヲ貸付スルコトアルヘシ | ||
| 第8条 左ニ掲クル者ハ図書借受及閲覧ノタメ本館書庫内ニ入リテ図書ノ検索ヲ為スコトヲ得 | ||
| 1. 教授,助教授,講師 | ||
| 2. 書記官,舎官 | ||
| 3. 大学院学生 | ||
| 4. 当該分科大学長ノ保認証ヲ有スル学生 | ||
| 5. 総長ヨリ特別閲覧票ヲ交付セラレタル者 | ||
| 第9条 前条ニ掲ケサル職員ニシテ書庫内ニ入リテ図書ノ検索ヲ為スコトヲ要スルトキハ其都度総長ノ許可ヲ経ヘシ | ||
| 第10条 貸付シタル図書ハ臨時返納セシメテ之ヲ点検スルコトアルヘシ但公用借受ノ図書ニ限リ本館吏員出張ノ上点検スルコトアルヘシ | ||
| 第11条 冬夏季休業中図書ヲ借受セントスルトキハ総長ノ許可ヲ得ヘシ但学生ハ学科主任教授ノ申出ニ依リ当該分科大学長ヨリ得タル保認証ヲ添ヘテ総長ノ許可ヲ経タル後ニ非サレハ之ヲ貸付セス | ||
| 第12条 貸付シタル図書ハ借受者保存ノ責ニ任シ紛失汚損等ノ行為アリタルトキハ之ヲ弁償セシムルコトアルヘク且貸付閲覧ヲ停止スル等相当ノ処分ヲ為スコトアルヘシ | ||
| 第13条 左ニ掲クル事項ニ関シテハ其都度総長ノ許可ヲ経ヘキモノトス | ||
| 1. 諸官庁又ハ公共団体ニ対シテ図書ヲ貸付スル事 | ||
| 2. 諸官庁ノ吏員又ハ公共団体ノ代表者ニ対シ公用上図書ノ検索若クハ閲覧ヲ許可スル事 | ||
| 第14条 凡ソ職員学生生徒若クハ公衆ノ閲覧ニ供スルノ目的ヲ以テ図書ヲ委託セント欲スル者アルトキハ本部之ヲ受ケ該図書ハ本館貯蔵ノ図書ト同一ノ取扱ヲ為スヘシ | ||
| 第15条 本則ニ依リ総長ノ許可ヲ請フヘキモノハ第9条ニ規定スルモノハ除クノ外凡テ館長ヲ経由スルモノトス | ||
| 第16条 本規則ノ執行ニ関スル手続ハ総長之ヲ定ム | ||
| 京都帝国大学附属図書館規則執行手続 | |||||
| 第1 図書貸付 | |||||
| 第1条 図書ヲ借受セントスル者ハ自ラ図書館ニ至リ其借受ノ種類ニ従ヒ定式ノ証書用紙ニ書名冊数番号姓名年月日等ヲ詳記シ捺印シテ之ヲ差出スヘシ | |||||
| 第2条 借受シタル図書ハ他ニ転貸スルコトヲ許サス但公用ニテ借受シタル図書ハ総長ノ許可ヲ経タル取扱規定ニ依リ教室内ニ限リ貸付スルコトヲ得 | |||||
| 第3条 公用ニ非サレハ一部ノ外同一ノ図書ヲ借受スルコトヲ許サス | |||||
| 第4条 職員及図書借受ノ特許ヲ得タル者ニシテ冬夏季休業中参考用図書ヲ借受セントスルトキハ書名,冊数ヲ詳記シタル伺書ヲ館長ヲ経テ総長ニ差出シ其許可ヲ経タル後第1条ノ手続ヲ為スヘシ | |||||
| 第5条 学生ニシテ教科書ヲ借受セントスルトキハ学科主任教授ノ申出ニ依リ当該分科大学長ヨリ得タル保認証ヲ添ヘ館長ヲ経テ総長ニ差出シ其許可ヲ得タル後第1条ノ手続ヲ為スヘシ | |||||
| 但聴講生ニ本条ヲ適用スル場合ニハ学生ニ貸付ノ後余裕アルモノニ限ル | |||||
| 第6条 学生ニシテ冬夏季休業中教科書ヲ借受セントスルトキハ書名冊数ヲ詳記シタル願書ニ学科主任教授ノ申出ニ依リ当該分科大学長ヨリ得タル保認証ヲ添ヘ館長ヲ経テ総長ニ差出シ其許可ヲ得タル後第1条ノ手続ヲ為スヘシ | |||||
| 第7条 職員退職若クハ転任シタルトキ及学生退学シタルトキハ其借受セル図書ヲ直ニ返納スヘシ学生卒業シタルトキハ卒業証書ヲ受クル前其借受セル一切ノ図書ヲ返納スヘシ | |||||
| 第2 図書貸付期限 | |||||
| 第8条 凡ソ借受シタル図書ハ其閲覧ヲ了シタルトキハ直ニ之ヲ返納スヘシ | |||||
| 但1月21日以後ニ借受シタル分ハ同年7月10日迄ニ9月11日以後ノ分ハ同年12月24日迄ニ必ス返納スヘシ | |||||
| 第9条 冬夏季休業中借受シタル図書ハ其休業ノ末日迄ニ必ス返納スヘシ | |||||
| 第3 借受冊数 | |||||
| 第10条 参考用トシテ借受スルコトヲ得ヘキ冊数ハ左ノ如シ | |||||
| 教授,助教授,講師 | 各30冊以内 | ||||
| 書記官,舎監 | 各20冊以内 | ||||
| 助手 | 各10冊以内 | ||||
| 以上ニ属セサル職員 | 各5冊以内 | ||||
| 借受ノ冊数ハ洋装ノモノニ就キテ之ヲ定メ和漢装ノモノハ3冊ヲ以テ洋装1冊ニ宛テ其他ノモノハ1個ヲ以テ1冊ト認ム又装釘セサル逐次刊行ノ書ニシテ数号ヲ以テ完冊ヲ為スモノハ其一完冊ヲ了ル迄ノ若干号ヲ合セテ1冊ト見做ス | |||||
| 但逐次刊行書ハ公用ヲ除クノ外装釘ノ都合ニ依リ臨時貸付セサルコトアルヘシ | |||||
| 第4 図書閲覧 | |||||
| 第11条 図書ヲ閲覧セントスル者ハ閲覧票若クハ閲覧許可証ヲ掛員ニ渡シ定式ノ証書用紙ヲ受取リ書名,冊数,番号,姓名,年月日等ヲ詳記シテ之ヲ差出スヘシ | |||||
| 但閲覧冊数ハ一時ニ7部15冊ヲ過クルヲ得ス | |||||
| 貴重図書ヲ閲覧セントセル者ノ中職員及特別閲覧票ヲ有スル者ハ書名冊数及閲覧ヲ要スル事由ヲ詳記シタル願書ヲ総長ニ差出シ学生ハ願書ニ学科主任教授ノ理由書ヲ添ヘ当該分科大学長ヲ経テ総長ニ差出シ共ニ其許可ヲ経タル上前項ノ手続ヲ為スヘシ | |||||
| 第12条 図書ハ必ス閲覧室内ニ於テ閲覧スヘシ貴重図書ハ必ス閲覧室内ノ特ニ定メタル別席ニ於テ閲覧スヘシ | |||||
| 但閲覧室内ニ於テハ一切音読談話喫煙ヲ為スヘカラス | |||||
| 第13条 閲覧票ハ左式ノ如ク定メ館長之ヲ交付ス | |||||
| 但職員学生以外ニシテ臨時図書ノ閲覧ヲ出願シ其都度総長ノ許可ヲ経ヘキ者ニハ総長ヨリ閲覧許可証ヲ交付ス | |||||
| 第14条 特別閲覧票ハ左式ノ如ク定メ総長之ヲ交付ス | |||||
| 但本学分科大学卒業者ニ交付スヘキ閲覧票ハ前条ノ式ニ依ル | |||||
| 第15条 閲覧票ヲ遺失シタルモノハ保証人連署ノ上直ニ其旨ヲ届出ヘシ | |||||
| 第5 閲覧時間 | |||||
| 第16条 閲覧室ハ休日ヲ除クノ外左ノ時間之ヲ開ク | |||||
| 自9月1日 至10月31日 午前8時ヨリ午後9時迄 | |||||
| 自11月1日 至4月30日 午前8時ヨリ午後9時迄 | |||||
| 自5月1日 至7月10日 午前7時ヨリ午後9時迄 | |||||
| 但日曜日及大祭祝日ハ午後6時ヨリ同9時迄 | |||||
| 第17条 休業中閲覧室ハ日曜日及大祭祝日ヲ除クノ外左ノ時間之ヲ開ク | |||||
| 自12月25日 至同月28日,自1月4日 至同月20日 午前8時ヨリ午後9時迄 | |||||
| 自7月11日 至同月30日,自8月22日 至9月10日 午前7時ヨリ正午12時迄 | |||||
| 第6 図書検索 | |||||
| 第18条 書庫内ニ入リテ図書ヲ検索セントスル者ハ特別閲覧票若クハ検索許可ノ捺印アル閲覧票若クハ検索許可証ヲ掛員ニ渡シ在庫証ヲ受取リタル後書庫ニ入リ検索シ得タル上ハ直ニ庫外ニ出テ第1条ノ手続ヲ経テ閲覧スヘシ | |||||
| 但庫外ニ出タルトキハ直ニ在庫証ヲ掛員ニ返付スヘシ | |||||
| 第19条 書庫内ニ入リ図書ヲ検索スルノ際図書ノ位置ヲ錯乱セサルハ勿論出納者ノ障 礙ヲナササル様厚ク注意スヘシ | |||||
| 第20条 学生ニシテ図書検索ノ許可ヲ得ンカ為メ当該分科大学長ノ保認証ヲ要スルトキハ学科主任教授ノ証明書ヲ添ヘタル願書ヲ其分科大学長ニ差出スヘシ | |||||
| 第21条 6人以上同時ニ書庫内ニ入リテ図書ノ検索ヲ為スコトヲ得ス | |||||
| 第22条 貴重図書ヲ検索セントスルトキハ更ニ其旨ヲ掛員ニ申出テ立会ノ上検索ヲ為スヘシ | |||||
| 但貴重図書ハ該図書ノ閲覧ヲ許可セラレタル者ノ外検索ヲ為スコトヲ得ス | |||||
| 第23条 検索ノ許可ハ図書館規則第8条ニ掲クル者ノ外ハ閲覧票ノ表面ニ検索許可ノ印ヲ捺シテ之ヲ証ス | |||||
| 但其都度総長ノ許可ヲ経ヘキ者ニハ総長ヨリ検索許可証ヲ交付ス其式左ノ如シ | |||||
| 第7 図書点検 | |||||
| 第24条 点検ノ為メ図書ヲ返納セシムルトキハ3日以前ニ其旨ヲ通知スヘク又,吏員出張ノ上点検スルトキハ前日ニ其旨ヲ通知スヘシ | |||||
| 第8 制裁 | |||||
| 第25条 公用ノ為メ借受シタル図書ヲ毀損汚染若クハ紛失シタルトキハ其旨ヲ詳記シ タル書面ヲ借受者ヨリ館長ヲ経テ総長ニ差出スヘシ | |||||
| 第26条 参考用閲覧用又ハ教科書トシテ借受シタル図書ヲ紛失シタルトキハ同一ノ図書ヲ以テ償ハシム | |||||
| 但時宜ニ依リ代価ヲ以テ償ハシムルコトアルヘシ | |||||
| 第27条 参考用閲覧用又ハ教科書トシテ借受シタル図書ヲ毀損或ハ汚染シタルトキハ其損害ノ多寡ニ従ヒ同一ノ図書ヲ以テ之ヲ償ハシメ或ハ之ヲ修繕セシム | |||||
| 但時宜ニ依リ代金ヲ以テ償ハシムルコトアルヘシ | |||||
| 第28条 図書館規則及同規則執行手続ニ違背シタル者アルトキハ其軽重ニ従ヒ一定ノ期限内若クハ無期限ニ図書ノ貸付及閲覧ヲ停止シ其旨ヲ閲覧室内ニ掲示スルモノトス | |||||
| 第29条 図書ヲ弁償セシメ若クハ貸付ヲ停止スヘキ者アリト認ムルトキハ館長意見ヲ具シテ総長ニ禀申スヘシ | |||||
| 第9 寄贈図書 | |||||
| 第30条 凡ソ教員若クハ学生ノ閲覧ニ供スルノ目的ヲ以テ図書又ハ購入費ヲ寄贈セント欲スル者ハ其目録員数又ハ金員等ヲ詳記シテ照会スヘシ本館ハ其需ニ応スルコトアルヘシ | |||||
| (閲覧票,特別閲覧票,図書検索許可証の様式は省略した) | |||||
本館は国立大学のうち,東京帝国大学附属図書館につぐ2番目の附属図書館として出発したが,新興の意気は,開館後間もない明治33年(1900)1月5日に,早くも関西文庫協会の設立を発起し,日本における近代図書館運動の先駆の一つとなったのである。翌34年4月には,わが国最初の図書館関係の専門雑誌である「東壁」を発行するに至った。
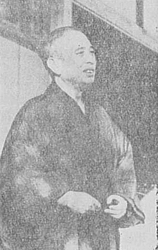 |
|
初代館長島文次郎
|
 |
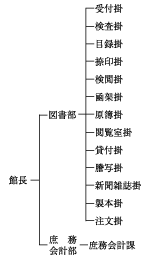 |
|
明治33年頃の本館職員
|
明治35年(1902)11月,法科大学に分館を設置し,分館主任ならびに法科大学図書購入主任を任命。翌36年には目録掛を専門化するため,和漢書・洋書別に職務を分担した。また検閲掛・注文掛を廃止した。
36年7月には京都帝国大学附属図書館規則の最初の改正が行われた。同年3月,京都帝国大学福岡医科大学が福岡に設立されたが,本館規則第1条によれば,福岡医科大学の図書も,本館に保管することになるわけであるが,それでは実際の取扱上非常に不便であるため,第1条に「福岡医科大学及同附属医院所属ノ図書ハ別ニ定ムル規程ニ依ル」と但書が追加された。
閲覧室の暖房設備は開館時すでに完成していたが,点燈の設備はなく,したがって規則の上では,夜9時まで開館となっていたが,実際上は夜間開館は不可能であった。それでこの欠を補うため,祝祭日・日曜日も開館していたが,36年6月待望の電燈設備が完成し,6月24日より点燈を始めた。
37年(1904)7月,閲覧室の一隅に法科大学の参考図書を排列して閲覧者の便を図り,また同年9月より書庫検索を許可することになった。こうして設備の拡充とともに,本館規則がいよいよ全面的に実施されるようになるにつれて,これまでの経験からして,執行手続の改正を必要とするようになり,同年10月11日付で,はじめてのかなり大巾な改正が行われ,これまでの30条が33条となった。この改正により,たとえば借受期限を短縮するとか,頻繁に利用される図書の貸付は臨時に拒否することがあること,また月に1度閉館日を設け,館内の大掃除や図書の点検を行ったり,あるいは館員会議を催すことなどがきめられた。
この年日露戦争が勃発したが,戦争の余波も大学には波及せず,この年閲覧人員は開館以来はじめて,年間総計1万人を越え,閲覧冊数も4万冊を越えるに至った。こうして本館の活動もいよいよ本格的になっていった。
一方本学全体としても,明治39年(1906)文科大学が開設され,本学当初の計画であった理工科大学(30年9月創設),法科大学(32年9月),医科大学(32年9月),文科大学の4大学がここに全部予定通り開設され,京都帝国大学の構成が完了した。
明治40年(1907)4月に,本学は早くも創立10周年を迎えることになり,10周年祝賀講演会が閲覧室で開催された。一方図書館も,業務の拡充とともに,当初の事務室では狭隘となっていたが,この年5月事務室の増築も完成し,ここに本館の歴史の第一期である拡充期を終え,いよいよ本格的な充実時代に入るのである。