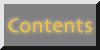
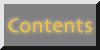 |
��1�́@���v
��2�߁@��2���i����41�N�`���a10�N�j
�@����41�N�i1908�j�͖{�ق̗��j�ɂƂ��āC�傫�ȈӖ������N�ł���B���̑�1�͊����̉����ɂ��C�{�ق��i��������юi�����u�����悤�ɂȂ������ƁC��2���u�����}���ُ��c��K���v�����肳�ꂽ���Ƃł���B
�@���̔N6��2���C���߂������Ė{�w��������������C�i��������юi�����V�݂��ꂽ�B���߂̊W�͂��̒ʂ�ł���B
| �@ | ��1���@���s�鍑��w�j�E�����u�N�@���m�@�V | |
| �@ | �@ | ���@ �� |
| �@ | �@ | ���L�� |
| �@ | �@ | ������ |
| �@ | �@ | �w���� |
| �@ | �@ | �i���� |
| �@ | �@ | ���@ �L |
| �@ | �@ | �i�@ �� |
| �@ | ��4�� | |
| �@ | �@ | �i��3���j�i�����n��C1�l�t�C�g�X�@�㊯�m�������P�����}���كj���P���}���L�^�y�{���j�փX�������j�]���X |
| �@ | ��5�� | |
| �@ | �@ | �i��3���j�i���n��C5�l���C�g�X�@�㊯�m�������P�����}���كj���P���}���L�^�m�����y�{���j�փX�������j�]���X |
�@�����Ă킪���̑�w�}���ق́C�͂��߂Đ}���ًƖ��̂��߂̐��I�E��������Ƃ��ł����̂ł���B
�@���������̔N12��1���t�B����19���������āC���s�鍑��w�����}���ُ��c��ݒu���ꂽ�B�i�����E�i���̐E�����V�݂���C���܂܂������}���ى^
�c�̐R�c�@�ւƂ��ď��c��ݒu����C��w�}���قƂ��Ẳ^�c�@�\�͂����Ɋ��������B���c��͐}���ق̂��ƂɊւ��āC�����̎��m�ɉ�����ƂƂ��ɁC�}���ْ�����я��c��ψ��̒�c���鎖����R�c����B���c��͈ψ����ƈψ�����Ȃ�C�ψ����͈ψ��̌ݑI�ɂ���đI�o�����B�ψ��͊e���ȑ�w���ƁC�e���ȑ�w�̋���1������\������Ă����B�����Đ�㏤�c��K���̉��������܂ŁC�}���ْ�����юi�����͈ψ��ɗ��C���c��ψ��̎��^�ɓ����C���̂��鎞�͒�c����Ƃ�������ł������B���c��J�ݓ����̋K���͎��̒ʂ�ł���B
| ���s�鍑��w�����}���ُ��c��K�� | ||
| �@ | ��1���@���s�鍑��w�j�}���ُ��c��݃N | |
| �@ | �@ | ���c��n�e���ȑ�w���y�e���ȑ�w�����e1�����ȃe�g�D�X |
| �@ | ��2���@�����j�V�e�ψ��^���҃n���Y�e���ȑ�w�����m�ݑI�j���������V�����X | |
| �@ | �@ | �ψ����n�ψ��j���e�V���ݑI�X |
| �@ | �@ | �ψ����n���c����W�V���c���g�׃� |
| �@ | �@ | �ψ������̃A�����n�N���ҔV���㗝�X |
| �@ | ��3���@���c��j���L1�l���u�N�@�ψ����m�w������P�����j�]���X | |
| �@ | �@ | ���L�n�{�w�i�����ȃe�V�j�[�c |
| �@ | ��4���@�ψ��m�C���n3�P�N�g�X�@�A�V�����L�đI�Z�������������X | |
| �@ | �@ | �ψ����y�ψ��⌇�m�ꍇ�j���P���C���n�O�C�҃m�C���j�˃� |
| �@ | ��5���@���c��n���m�������R�c�X | |
| �@ | �@ | 1�@�}���كj�փV�����������m�m�� |
| �@ | �@ | 1�@�}���ْ�������c�m�� |
| �@ | �@ | 1�@�}���كj�փV�ψ�������c�m�� |
| �@ | ��6���@�}���ْ��n���c��j��ȃX�@���ψ����n�K�v�A���g�F�����ꍇ�j���e�����m�{�w�E���j��ȃ��v���X���R�g���� | |
| �@ | �@ | �A�V�����m��Ȏ҃n�c���m���j���n���������X |
| �@ | ��7���@�{�K���n����41�N12��1�������V���{�s�X | |
| �@ | �ψ��� | �v���@�Z���@ | ���H�ȑ�w�� |
| �@ | �ρ@ �� | �c�Ӂ@��Y | ���H�ȑ�w���� |
| �@ |
�V
|
���@�� | �@�ȑ�w�� |
| �@ |
�V
|
�ьˁ@���� | �@�ȑ�w���� |
| �@ |
�V
|
�r�ؓЎO�Y | ��ȑ�w�� |
| �@ |
�V
|
�ɓ��@���O | ��ȑ�w���� |
| �@ |
�V
|
���{���O�Y | ���ȑ�w�� |
| �@ |
�V
|
���c�@�① | ���ȑ�w���� |
�@����42�N�i1909�j2��17����1��̏��c��J�Â��ꂽ�B���̍ŏ��̏��c��ŐR�c���ꂽ�d�v�Ȗ��́C�}���ْ�����c���ꂽ�u�{�w�}���i�e���ȃ��ʃV�j����ژ^�iAuthor�@Catalogue�j������]�m���v�ł������B���̖��͏n�l��v����䂦�C����ۗ�����Ƃ̈ӌ������ŁC������݂Ȃ��������C�S�w�ɋ��ʂ��Ďg�p�ł������ژ^���쐻���悤�Ƃ������ł����������ɁC���ڂ���Ă����B
�@��2�c��͂Ђ��Â����N6��17���ɊJ�Â���C����43�N�x�}���ٗ\�Z�v���T�Z���Ăɂ��āC�e��ڂ��ڍׂɐR�c�����B���̉�c�ɂ����āC���ْ��̈Ăł����������}���̌����������������z����o���ꂽ���C�u�}���كj�n�{�w�S�̃m�}���ژ^�m����T���^�����m�i�V�V�j�旧�e�����}���m�~�m������V�e�z�t�X�������{�I�m�ژ^�i�L���ȃe�i�ʃm���v�i�V�v�Ƃ��Ĕی����ꂽ�B
�@����43�N�i1910�j7��25���C�������Y�͑�O�����w�Z�����ɓ]���Ċْ���Ƃ����C�ΐ�����������i�����ɔC������Ƌ��Ɋْ��ɕ₹��ꂽ�B�{�قɂ����āC�����n�ȊO���}���ْ��ɕ₹��ꂽ�̂́C���̐ΐ��ْ��݂̂ł���B����41�N�̊��������ɂ��C�ْ��́u�������������n�i��������������b�V����X�v�ƂȂ��Ă����̂ŁC�ΐ��͎i�����ɔC�����邱�Ƃɂ���āC�ْ��ɕ₹��ꂽ�̂ł���B
�@���ْ��͏���ْ��Ƃ��āC�{�ق̑n�݈ȗ����̔��W�̂��߂ɐs�͂������C������ȑ�w�̊J�݂ɔ����C���Ȍn�}���̎��W�ɂ��Ƃ߁C���X�Ƃ��̐��ʂ������C�܂������ɋ�����n�݂��铙�C�يE��ʂɂ����C���̌��т����ɑ�ł������B����œ��ْ��̎��C�ɍۂ��C���{�}���ً������s���u�}���َG���v��10���́C�����s�鍑��w�����}���ْ��̓]�E�Ƃ��āC���̒ʂ�Ă���B
�@���s�鍑��w�����}���ّn���̍ۂ��ْ��̐E�������ĔM�S���ق̌o�c�ɔC����ɑ����ǔ��W���v��Đ��ɍ����̐����v���ꂵ���w�m�������Y�N�͋���8�����w�i������蕶�ȑ�w�������ɓ]�C�C�����ɐ}���ْ��̐E������ꂽ��B��P�͓��N�]�E�̎��R�̔@���Ȃ���̂��邩��m�炸��嫂��C������P���Ƃ̗�����ςČN�̔@���L�͑��J�̎m�̉䂪�}���يE������ꂽ���ɂ܂���\�͂��B�N���]��[��]�w�B�x�֔V�ɉ��ӂ�Ɏz�Ə\���O�N�̌o�����ȂĂ��B�䂪�E���l�ɖR������i�ӂ�ɓ���Ē[�����N�̑ވ�������B�^�Ɉ⊶���薳���ƈ��ӂׂ��B�N���V�ɓ���ꂽ��p���w�E�͌N�����}���邱�Ɩܘ_�Ȃ��嫂��C��P�̎��]�͍��ɂ��ĈԂނׂ������炸�B�����ꎖ�̂��邠��C�H���N���E��]�����嫂��C��͂��͉䂪�}���قɒ����Ȃ邱�Ɛ̓��̔@���Ȃ�ƁB
�@�ΐ�ْ��͏A�C��Ԃ��Ȃ��C43�N10��20����5�c����J�Â����B���̉�c�ɂ����ẮC�i1�j�}���ًK�������̌��C�i2�j�}�����ސ���̌��Ƃ���2�̈Č���R�c�����B�K�������́C�����̉����ɂ��C�u�������v�u��ǒ��v�u�w���āv�u�Z�t�v���̕������V���ɂ����������ƂƁC�u�M�d�}���n���w�ȃj�փX�������m�O�����m���������^�����m�j�����V���{���X���R�g�����v�Ƃ������̂��C�u�ْ��m���F���o�e�v�Ɖ������ꂽ���Ƃł���B
�@���̏��c��̌��ʁC11��14���t�Ő����ɖ{�ًK���Ȃ�тɓ����s�葱����������C�����11��15�������u���s�鍑��w�����}������v�����s����͂��߂��B
�@����J���t�I���j�A��w�Ƃ��}���������͂��߂��C�܂��{�����̈ꕔ�����R�ډː��ɂ��}���̓W����s���ȂǁC���O�ɂ킽��}���ي����͏[������Ă������B
�@����44�N�i1911�j6��7���C��6�c����J�ÁB������O��Ɠ��l�C�K�������Ɋւ��R�c���s�����B����ǂ̉����͑����L�͈͂ɂ킽��C�����͐}���ًK���ɂ���10�J���C���s�葱�ɂ���5�J���ł������B�����̉����͊����̉������̌��ʂɂ����̂ŁC����43�N12��22����B�鍑��w�̐ݒu�����肳�ꂽ�̂ɂƂ��Ȃ��C�����ɖ{�ًK����1���ɁC������ȑ�w�ɏ�������}���ɂ��Ēlj����ꂽ�����C���炽�߂č폜���ꂽ�B
�@���̉�c�ɂ��e�r�������ՐȂ������C���������c��ɎQ�������̂́C���ꂪ�ŏ��ł���B�����������[���̂́C�����̔����ɂ���āC�����Ă��C���Ƃ̏����ɍ폜���ꂽ������邱�Ƃł��낤�B�����̋L�^���݂�ƁC���s�葱�̑�32���́C�������Ắu�}�\�{�w�j�}�����n�}���w����Z���g�~�X���҃A���g�L�n�{�w�n�����j���X���R�g�A���w�V�v�Ƃ������̂��C���̂悤�ȋK���͑�w�S�̂̋K���̒��ɓ����ׂ����̂ł���Ƃ������ƂŁC�폜���ꂽ�B���c��ł̂��̐R�c�̌��ʂɂ��ƂÂ��C9��8�������ɋK������ю��s�葱���������ꂽ�B
�@���̔N7���ȍ~�C�č��c�@�}�����J�[�h�^����ژ^�̊����̕��ƍ��㊧�s�̕����C���킹��������邱�ƂɂȂ����B����́C����42�N12���C���̑����e�r��[�����Č��������Ƃ��ăA�����J�؍ݒ��C�u���̗]�ɂɋc�@�}���فiLibrary�@of�@Congress�j�����@�����Ƃ��C���قŔ��s���Ă����J�[�h�^����ژ^���w�p������C�܂��}���ٌo�c����v����Ƃ��둽�����Ƃ�m��C���������̊��s��10�N�߂��o�߂��Ă���̂ɂ�������炸�C�킪���ɂ�1�J��������������ق̂Ȃ��̂��⊶�Ƃ��C���ْ��p�g�i���iPutnam�j���Ƒ��k���C���J�[�h����{�ɂ��z�z����悤�蔤���߂ċA�������B�����������鍑��w���鍑�}�����Ƃ́C���J�[�h�̔z�z���C�s���ɂ��Ƃ��Ɏ��ނ����̂ŁC�܂��{�w�̂ݔz�z���邱�ƂɂȂ�C�����Ȃ��h�����ĊO���Ȃ�ʂ��C�c�@�}���ق�����X�~�\�j�A���E�C���X�`�`���[�V�������ې}���������ƌ��̌��ʁC����Ƒ��t����邱�ƂɂȂ������̂ł���B
�@���N10��1���ΐ���ْ͊���Ƃ����C�V���o����3��ْ��ɔC�����ꂽ�B�ΐ�ْ��͍ݐE1�N2�J���]�ŁC���ْ��̂����ݐE���Ԃ͂����Ƃ��Z�����������C�悭����ْ��n�Ƃ̂��Ƃ��C�琬�̔C��S�������B
�@�V���ْ��͏��a11�N��N�ފ�����܂ŁC�����E�吳�E���a��3��ɂ킽��C�ݐE���邱�Ǝ���26�N�̋v�����ɂ킽��C�{�ق̏[��������肠�����B
 |
|
��3��ْ��@�V���o
|
| �@ | 1�@���������n�����c�̃j�V�e�}�����ݕt�X���� |
| �@ | 1�@�������m�������n�����c�̃m��\�҃j�V���p�}���̌�����N�n�{�������X���� |
| �@ | 1�@�}���ى{�����،�t�m�� |
| �@ | 1�@�}�����ʉ{���[��t�m���i�A�V1�P�N�ȓ��L���m���m�j�����j |
| �@ | 1�@�}���������،�t�m�� |
| �@ | 1�@�Ċ��x�ƒ��}���ݕt���m�� |
| �@ | 1�@2���ȏ�M�d�}���ݕt���m�� |
| �@ | 1�@�M�d�}���{�����m�� |
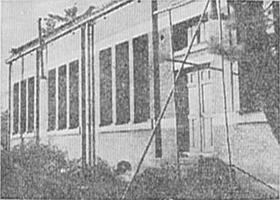 |
|
���}���َ������i���݂͕ی��f�Ï��j
|
| ���@�@�@�@�� | �\�@�@�@�@�� | �L�@�@�@�@�� |
| �{�@�@���@�@�� | �ؑ����ƌ� | 159.6�@�i527.6�u�j |
| �w���{���� | 115.3�V�@�i381.2�u�j | |
| �����{���� | 12.8�V�@�i 42.3�u�j | |
| �V���{���� | 6.5�V�@�i 21.5�u�j | |
| �o�@�[�@�� | 16.0�V�@�i 52.9�u�j | |
| ���@�@�@�� | 6.0�V�@�i 19.8�u�j | |
| �ԁ@�@�@�� | 3.0�V�@�i�@9.9�u) | |
| ��@1�@���@�� | ������2�K�� | 34.7�V�@�i114.7�u�j |
| �� 69.4�V�@�i229.4�u�j | ||
| ��@2�@���@�� | ������3�K�� | 96.1�V�@�i317.7�u�j |
| ��288.3�V�@�i953.1�u�j | ||
| ��@3�@���@�� | �S�R���N���[�g��4�K�� | 35.7�V�@�i118.0�u�j |
| ��142.8�V�@�i472.0�u�j | ||
| ���@�@���@�@�� | ���������ƌ� | 67.5�V�@�i223.1�u�j |
| �}�@���@�� (1) | �ؑ����ƌ� | 90.0�V�@�i297.5�u�j |
| �}�@���@�� (2) | �ؑ����ƌ� | 18.0�V�@�i 59.7�u�j |
| ���@�@�~�@�@�� | �ؑ����ƌ� | 7.8�V�@�i 25.8�u�j |
| �� �� �n �L �� | �ؑ����ƌ� | 4.3�V�@�i 14.2�u�j |
| �}�����n�L�� | �ؑ����ƌ� | 4.5�V�@�i 14.9�u) |
| �� �� �n �L �� | �ؑ����ƌ� | 2.0�V�@�i�@6.5�u�j |
| ���@�@�g�@�@�� | �ؑ����ƌ� | 6.0�V�@�i 19.8�u�j |
| �w�@���@�ց@�� | �ؑ����ƌ� | 2.5�V�@�i�@8.3�u�j |
| �E�@���@�ց@�� | �ؑ����ƌ� | 2.0�V�@�i�@6.6�u�j |
| �v | 530.7�V�i1,754.4�u�j | |
| ��864.7�V�i2,858.5�u�j |
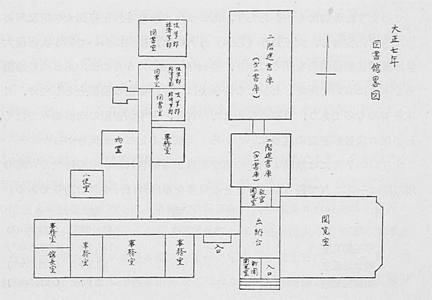 |
�@�P�j�����鍑��w�����}�����m�V�j�G�s�Y��j���z�Z�����^���j��n���g�X���j�A���U�����C�ŋ����m�����C�V�����}�����C�����s�[���}�������m�V�z�j�����C���j�O�E�����~�T�����E���E���~�m�\�Z���ȃe�C�V�����V����Z���j�Ńe���C�{�w�m�����}�����g�V�e�m�g���@�\���[���j�ʃT���g�X���j�n�C���N�g�������x�m�ݔ����K�v�g�F���^���j�����B����\�N��V�N�n�S�N��m�R�g���l�t���j���e�C���j���R�������Y�B�]�n�}���كm���g���j�Ӄ~�C�w���j����Q�l�p�}�����{���Z�V�����j�c�L�e�n�C�����m���ڎw���j�˃��Y�C���R�j�ƏC�X�������V���C���l�e�v�z�P���j�����Z�V�����g�X���j���e�C��{�����m�K�v���Ɋ��X���j�����^�����m�i���B ������1�{�������݃P�ܕS�������e�Z�V�����g�X���n�C���`�V�j��c�N���m�j�V�e�C���ܕS���m�Z�o�n�S�w�������ܐ疼�g����V�C��1�����F���^�����m�i���B���O�j��S�������e�X�x�L��2�{�������݃P���g�X���n�C�e�����m�Q�l�}�����ǃ}�V�����K�׃��j�V�e�C�^�j�������i�T���g�X�����m�g�ۃ��U�����m�g�����^���g�X���K�C���{�m���q�i���B�V���{�����C�G���{���������`�^��������|�j�O�i���Y�B�i�����j�@�{�E�m��]�X�����n�C�����}���كn���w���m���L���i���g�]�t�ϔO���ȃe�C�e�w�����������㉇�C���̓���P�^�L�R�g�i���B���ۋ����m�O����|�V�e�C�V�j���������j�����C�{���m��j�����p���������������R�g�����]�~�}�U�����m�i���B���V�V�L�l���ȃe�{�ă����Ē�o�V�^�����m�i���o�C��N�n�e�ʃj���e�����Ӗ��j���e�R�c�Z�������R�g���B�����j�{�E�m���ăg�X���}���َ����n�������T��
���ʃj�e�w���j�i��1�l���z�u�X���R�g�C�����e�w���j��C���L1�������z�u�X���@�N�i���V�����g�X�B�z�N�V�e���O�����W�e���j�����o�C��w�v���q���j�}�������m�����ʃX�����x�V�B�v�X���j�e�w���݃j�����P�C������w�}�����g�V�e�m�@�\���[���j�����Z�V���������R�g�����X�����m�j�V�e�C�}���ُ��c��K���ԃj�݃��e���N�֗^�w���V�C���ړI�������Z�V���������R�g���]���B�V�v�j�l�\�m��c�����݃P�^���n���Ӄj�˃��B
�Əq�ׂ��B
�@���̏��c��ɂ��V�鑍�����o�Ȃ����B�����đ吳�̎n�߂̏��c��ŁC�o�Ȃ�������������}�������v����Ă��C���ȑ�w���Ƃɕ��u����Ă���}����{�قɏW�������邱�ƁC���ȑ�w���Ƃɒ�߂Ă����}���戵�K���ꂷ�邱�ƁC����ɖژ^�쐻��̓���ƁC�S�w�}���̐����E�^�p��̓��ꉻ����}�������������Ȃ������B������܂����a�̎n�߂̏��c��ŁC���l�ɑ����o�Ȃ̂��ƂɁC�S�w�}���s���̓��������ēx��Ă��ꂽ�̂ł������B����������͑O���������ɓO��I�ɁC����ɐ����E�^�p�ʂ̓��ꂾ���łȂ��C�S�w�̐}���n�E���̓������Ӑ}������̂ł������B�����Ă��̂悤�ȗ��O�̎����̂��߂��u�}���ِV�c�āv����o���ꂽ�̂ł���B
�@���̓��̉�c�͏o�Ȏ҂̔�������������߁C�c���͓�s���C���Ǒ吨�͌��c������ɉ������邱�Ƃƌ������B
�@���̉�c�̌�C�V���ْ��͑����ƂƂ��ɁC�����V�z���������}�������w�̂��ߓ��サ�C�{�ِV�c�Ă̂��߂̍\�z������ɗ������̂ł���B
�@�����đO�c����17����������6��27���C��14�c��J�Â��ꂽ�B���̐ȏ�C�ْ��͓���̖͗l���ڂ������������B�ْ��͂����ŁC�}������ʌo���Ɋւ��āC����̐����������Ė{�w�̂���ƑΔ䂵�C�{�w�̌o��̋͏��ł��邱�Ƃ��q�ׁC�܂��C�{�����̍\���Ɨl���i�w��{�����C��ʑ�{�����C�I�[�v���X�^�b�N���̐��x�j�ɂ��Ă��C�{�w�̐ݔ��������ɕn��ł��邩��������B�܂��C���ɓ�������@�������������̂悤�ɕ����B
�@���p�}���g��ʗp�}���g���ʃ`�l�t���j�C���p�m���m�n���݃m���m���X�j�ژ^�j�e����V�C�݃j�Z�ʘA���V�e�s�N�l�j�Z�o�i�����g�v�n���B��w�o��w�m�_�W�m�@�L���m�n�C���w���j�e�w���V�e�V�������}�����j�ϑ��V�u�J�o���X������i�����B����j�e�n�呠�o���e���ʃj�e7���w���Z���@�L��A���B�V���n���Ǒ��݃j�A�������N�������Y�����m��i�����m�i�����B���M�j��ʗp�m���m�n�w�����V�e�L�N�������烒��P�V�����׃��j�C�w��{�������݃P�e�V���[�����p�Z�V�����g�~�X�����m�i���B�����n�e�w���m�l������j�e�C�����j�e�����{�X���������J�g�v�n���B�e�w���m�}�����E�]���~�m���C�������n���������J�o�C���`�j���s�V�������x�N�C�ꏊ�������J�m�����[���Z�o�����R�g�g�v�n���B���ۊe���m���̓��ؖ]�X�B�{���j���e���[�����s�Z���R�g�����X
�@��������������C�}�������̑g�D����R�c���C�e�w���̐}���戵�̌�����C�e�w���ψ����������āC����̏��c��ŕ��C���̌�ɂ����āC�e�w�����ꖼ���̈ψ���I�o���āC���̖�����Ɉ������ψ������邱�ƂƂȂ����B
�@4�J����̓��N10��24����15�c��J�Â��ꂽ�B�O�肳�ꂽ�e�w���ɂ�����}���戵�̌���ɂ��Ă̕��Ȃ���C�I���ď��ψ��𐄋����錏�Ɉڂ�C�e�w���ψ������ꖼ����I�o���ď��ψ�����������B�ψ����͏��c��ψ��������˂邱�Ƃ����߂��B
�@���̐}���戵���@�̉��P��ړI�Ƃ������ψ���̑�1���́C���N11��21���J���ꂽ�B���̉�ł́C�}���ّ��Ƃ��ẮC���m�Ȗژ^����邽�߂ɁC�e�w�����}���𑗕t����邱�Ƃ�]�݁C����ɗv����������ł��邾���Z�k���邽�߂ɁC���������^���������w���������B�܂��ْ����`�[�ɓ�����i�����ɗa����悤�ɂ������Ɗ�]�����̂ɑ��C�@�o�������w������́C���̎i�����e�w���ɏo���h�������āC�}�����e���ɒu�����܂܁C�ژ^�����𐋍s�ł���悤�ɂ��ꂽ���Ɗ�]�����B�܂��u�w���j���e�n�}���كn�}�����a�Z�V�����@�փi���g�X���O�j�����݃��F���U���V�ʃi���c�c�c����n�����㐥�������}�����j�˃��U���x�J���U���l�C�[���ݔ������w�������R�g���]���v�Ƃ�����������C�u�O���j�e�n�I�v�m�@�L���m�n�C�V�������}���كj���e�����X������g�i���������K�C�{�w�j���e���V�������}���ك������t�X���R�g�g�V�e�n�@���v�Ƃ̈ӌ����o���ꂽ�B
�@�������Č��ǐV���ْ��́C�S�w�}���s���̓��ꉻ�ƁC���̗��O�̏�ɗ����č\�z���ꂽ�}���ِV�c���͎������݂��ɏI�����B��������w�}���ق̗��O���߂����Ă̓��c�̒�����C�w��}�����x����āE������C���̔N������{����邱�ƂɂȂ����B
�@����ɏ��a8�N�i1933�j��9������́C�@�o��4������2�K����2�{�������J������C�u�����m���ڎw���j�˃��Y�C���R�j�ƏC�X�������v���{�����Ƃ����V���ْ��̍\�z�̈�[�������Ɏ������ꂽ�B
�@���a9�N�i1934�j�ɂ́C�{�w�̑�����100�����ɒB�����B���N4��21���t�����s�鍑��w�V���͂�������̂悤�ɕĂ���B
�@�@�킪�}���ق�
�@�@�@�@�����S����˔j��
�@�@�@�@�@�@��\�]�N�ԂɎ��\���̑���
�@�@�@�@�@�@�@�@���m��̑啶��
�@�ŋ߂̒����ɂ��ƁC�{�w�}���ق̑����͂���1�C022�C632���i�a����457�C438���C�m��565�C194���j�ɒB���C�{�N2����100���Ƃ����������C����˔j�����킯���B�������̊O����{�Ƃ����߉q���݉����߉q����10�������C�v���[�V�������v������������������C���������n�ゾ���C���̓��e�ɉ����Ă͂܂��ɓ��m����ւ蓾�ׂ��C���ꂪ���S�Ȃ�ۑ��Ɨ��p�̂��߂ɂ��C���̐V�z���w�̓��O����Җ]����Ă���B�Ȃ��ْ��V�������̘b�ɂ��C������20�]�N�O�����m�ْ��A�C�̓����́C30�����炢�̑�������������������C20�]�N�Ԃ�70�������������ƂɂȂ�B���قł͂�����L�O���邽�߁C���炩�L�Ӌ`�ȍÂ�������炵���B
�@�������Ė{�ق͏��a�̑O���C��w�}���ق̗��O�����̂��߁C���낢��Ɠw�͂��d�˂��ɂ�������炸�C����͎������Ȃ��������C�����͏����ȑ����������Ă������B����������͂܂��܂��Â��C���a8�N�i1933�j�ɂ͖{�w����쎖�����N���Đ��Ԃ��Փ��C���a10�N�ɂ͋��w���V�̗�������E�ɐ����r��C��w�̓���ɂ����悢��É_�����������Ԃ����Ă����B���a11�N�i1936�j1���C���ꂩ���̈Í��j��\�����邩�̂悤�ɁC�{�ى{�����͕s���̍Љɕ�܂ꂽ�̂ł���B