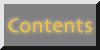
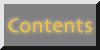 |
�@�s��ɂ���Đ펞����̐��͑S�ʓI�ɏI�~����������C�������̌R�ɂ���ĊǗ�����邱�ƂɂȂ����B����ƂƂ��ɖ����`�Љ�����݂��邽�߂̐V�����V����v���i�߂�ꂽ�B
�@���a21�N�i1946�j4��1���u�鍑��w�����v�����ߑ�205���������Č��z����C�������u���s�鍑��w�����v���p�~���ꂽ�B����܂Œ鍑��w�͂��ꂼ��ʌ̊����������Ă����̂ł��邪�C���ꂪ���ʂ̊����̉��ɂ����߂��邱�ƂɂȂ����킯�ł���B
�@���̐V�����̌��z�ɂ��C����܂ő����ȉ������E�������E���L���E�������E�i�����E���L�E�i�����Ƒ����킩��Ă����E����C���������E�����������E�����Z����3�ɓ��ꂵ���B���̌��ʖ���41�N�ȗ��C�}���ق̐��E���Ƃ��Ċ�����F�߂��Ă����i�����E�i���̐E��͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł���B�܂������̐g�����e�C���E���C���E�t�C�����̍��������ƁC���C���̕��ʕ����Ƃ̍��ʂ���߁C1�����i���C���j�E2�����i�t�C���j�E3�����i���C���j�̖��ɂ��炽�߂��B����Œ鍑��w������16���ɂ́C�u�鍑��w�j�����}���ك��u�N�@�}���كj�}���ْ����u�L������N�n�������^�������������n2���m�������������ȃe�V�j�[�c�v�ƋK�����ꂽ�̂ł���B
�@���̔N3���ɂ��A�����J����g�ߒc�����������B�g�ߒc��1�J���̌���{�̋��琧�x�Č��̂��߁C�������̐ϋɓI��Ă�A�����ō��i�ߊ����Ăɒ�o�������C���̂Ȃ������l�����Ɋւ��ẮC�u��̏d�v�Ȑ��l����@�ւ͌����}���قł���v���Ƃ��w�E���C�܂���������Ɋւ��Ắu�}���ٌ����{�݂���ь������̊g�[�v�������̈�ɋ����Ă���B���̂��Ƃ͔s���̔p�Ђ̒�����C����I�Љ�����݂��悤�Ɨ��������������{�̐}���يE�ɂƂ��Ă͑傫�Ȏx���ƂȂ����B
�@���������a11�N�{�����Ď����C���g�s���I��Ԃ𑱂��Ă����{�قɂƂ��ẮC���̍Č��͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ������B�{����z�[���ɐ݂����Ă������{�����͐���2�{�����ɍ�������Ă������C��2�{�������@�o���w���̎���ɂ��ԋp�����߂�ꂽ�̂ŁC�ӂ����і{���̋����H�����ꎞ�I�ɉ{�����ɂ��Ă�Ƃ�����Ԃł������B���a15�N�ɋN�H�����V�ق��푈�̂��߁C�O�s�H�����ꉞ���������܂܂ŕ��u����Ă����̂ŁC1��������������������邱�Ƃ��Ŕ��̋}�ł������B���������s��w�͔��ЍZ�łȂ��������߁C�H���C�V�c�̗\�Z���Ȃ��Ȃ��l���ł����C���a22�N�x�\�Z�ł͂��߂�163���~�̖{�ٍH����̔z�����邱�Ƃ��ł����B�\�Z�͂ǂ����l�����Ă��C���̂����鎑�ނ̌��R���Ă�������ł��������߁C�H�����v���悤�ɐi�s�����C���Ɛ���W�҂̋��͂łƂ肠�����{��������ю������ȂNjً}��v������̂��璅�肵�C���a23�N�i1948�N�j2���ꉞ�v�H���������邱�Ƃ��ł����B���N3���{��������ю����������̐V�قɈڂ����B
�@���̎��̏̈�[�������{���O�Y�����́C���a35�N�i1960�N�j6��19���t���s�V�����z���ɁC�u���E���v�Ƒ肵�Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�i�O���j���̐̒i�X�i�}���ٌ��֑O�̐Βi�j�ɂ��Ă͈�ʂ�̕��ꂪ����̂ł���B�K���X�C�Z�����g�C�؍ނȂǂ͎�ɓ���ɂ��������Ƃ͂����Ă��C���Ɛ��ɋ������Ή��Ƃ��Ȃ����̂ł��邪�C�K�i�Ɏg�����ꂾ���̐��C���ꂾ���������낦�邱�Ƃ́C�����Ƃ��Ă͂ƂĂ����X�Əo���邱�Ƃł͂Ȃ������B����ƂāC�R���N���[�g�ł�����̂ł͈����ۂ��āC��}���ق̌��ւɂ͂���Ȃ��B�����Đ����\���փK�X���������Ƃ��āC�K�X�ǂ������č��������C��w�\����{�������Ƃ���C���������ɓS�ǂ����낪���Ă����̂ŁC������E���W�߂čH�����ς܂������Ƃ�����B���̌̒m�ɂȂ���āC�����\���̑�{�����s�Ȃ����Ƃ���C����킠���B�����炱����ɓK���Ȑ����낪���Ă���B������E���W�߂Č�����C����Ȃɗ��h�ȉԛ���̊K�i���o���オ�����̂ł���B�@�i�����j
�@�������Đ}���ق��o����������C�������Ő��ʂɂ͂ߍ��܂�Ă����u���s��w�����}���فv�Ƃ����������̊z�����ɏ����Ƃ������ƂɂȂ����B�������ō����p�����炵�����Ă��鎟��ł���B���̎��̂͂����_�C�ق��̋ɂ݂ł��邪�C�������̐S�\�������͒��X�T�d�Ȃ��̂ł������̂ł���B����Ƃ����̂����̖{�c�����ǒ������̕��ʂł̒��X�̕��剮�ŁC���ꂱ��ƒ��ӂ��Ă��ꂽ��Ɂu���₵�������ȗ��◪���͂����܂���B�������������ŏ����Ȃ���v�Ƃ������̂�����C�g��K���Y�����ɂ������������肵�āC����������������ł���B���E���W�߂����Ƃ͍��ł����Ԃł͂悭�b�̎�ɂȂ�B�i�㗪�j
| �����}���ْ����F�t���K | ||
| �@ | 1�D�����}���ْ����F�t�̕K�v�����ꍇ�����͐}���ُ��c��Ɏ��m���� | |
| �@ | 2�D�}���ُ��c��O���̎��m�����Ƃ��͏��c��őF�t���s������1�����ɐ��E���� | |
| �@ | 3�D�����}���ْ��̔C����4�N�Ƃ���@�A���C�������̂Ƃ��͓��l�̎葱���o�čĔC�����邱�Ƃ͍��x�Ȃ� | |
| �@ | 4�D�����}���ْ��~�ނȂ����ׂ̂̈ߔC���̒��r�ōX�R����ꍇ��C�҂̔C���͑�3���ɂ�� | |
| ���@�@�� | ||
| �@ | ���̎葱�͏��a22�N5��1������{�s���� | |
| �����}���ْ��F�t�葱���K | ||
| �@ | ��1���@�����}���ْ����҂͐}���ُ��c��ňψ��̓��[�ɂ���Č��肷�� | |
| �@ | ��2���@�}���ْ����҂ƂȂ邱�Ƃ��ł���҂͒鍑��w������16���2���̎����Ƃ���ɂ�� | |
| �@ | ��3���@�����}���ْ����҂̑I���͈ψ���4����3�ȏ�o�Ȃ��邱�Ƃ�v���� | |
| �@ | ��4���@�����}���ْ����҂�1���Ƃ����̑I���͒P�L���L�����[��p���ߔ����̓��[�҂��Ȃē��I�҂Ƃ���@�A���ψ����͓��[�ɉ������̂Ƃ� | |
| �@ | ��5���@���[�̌��ʂ��Â���ߔ����ɒB���Ȃ��Ƃ��͍ő����̓��[��2���ɂ��Č��I���[���s�����̑���������̂I�҂Ƃ��� | |
| �@ | ��6���@�����̓��[�҂�2���ȏ゠��Ƃ��͍X�ɂ��̓����҂ɂ��ē��[���s�����̏������߂� | |
| �@ | ��7���@��4���̌��I���[�y�ё�5���̓��[�̌��ʂ��̓��[�������̂Ƃ��͔N���҂��Ȃē��I�҂Ƃ��� | |
| �@ | ��8���@���I���[�̏ꍇ���҂͔V��ɉ����Ȃ����̂Ƃ��� | |
| �@ | ��9���@���҂͎~�ނȂ��ꍇ�������O�͐��E�������邱�Ƃ��o���Ȃ� | |
| ���@�@�� | ||
| �@ | ���̓��K�͏��a22�N5��1�����炱����{�s���� | |
�@���̓��K�ɂ��5��14����21�c����J���C���������w�������������ْ��ɐ��E����邱�ƂɂȂ�C5��31���t���ْ��͎��C�C����������7��ْ��Ƃ��ďA�C�����B
�@���ْ��͕��w���j�w�ȋ����Ƃ��Đ��m�j��S���������C�ْ��A�C�O�{�ُ��c���Ƃ��āC�}���قɂ��Ă��[��������L���Ă����B�s���ɂ�����{�ٍČ��̑����͑O�ْ��ɂ��i�߂�ꂽ���C���̂��Ƃ������C���ɂ������w�̗��O�̍������ɁC�{�ق̍Č����ʂ��˂Ȃ�ʌ��ْ��̋�J�͑傫�������B
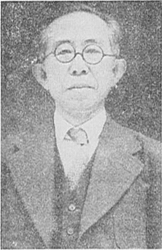 |
|
��7��ْ��@���@笉~
|
| �}�����Ǐ��w���ψ���K�� | ||
| �@ | ��1���@�w���y�юs���̓Ǐ��w���Ɋւ���}���ق̎��ƂɐϋɓI�������Ȃ��ړI�Ő}���ٓǏ��w���ψ����݂��� | |
| �@ | ��2���@�ψ���͐}���ْ��y�ъe�w�������e1���őg�D���� | |
| �@ | ��3���@�}���ْ��ȊO�̈ψ��͊w����������E���đ������Ϗ����� | |
| �@ | ��4���@�ψ����ɂ͐}���ْ����Ȃ� | |
| �@ | ��5���@�}���ْ��ȊO�̈ψ��̔C����1�N�Ƃ���B�A���d�C��W���Ȃ� | |
| �@ | ��6���@�ψ����̎�����㍲����ׂɊ���1����u���C�}���ِE������ψ������w������B | |
| �@ | ��7���@�ψ���͍��̎������戵�� | |
| �@ | 1�@�Ǐ����E | |
| �@ | �@ | 2�@�Ǐ��Ɋւ����C���Ɠ��̎w���I���� |
| �@ | 3�@�Ǐ��X���Ɋւ��钲���y�ё� | |
| �@ | ��8���@�{�K���̕ύX�͐}���ُ��c��Ō��߂� | |
�@���̈ψ���K���́C��w�}���قƎs���Ƃ̒����Ƃ����C�؉����㑍���̍\�z�̋���ł���C��w�}���ق̊����Ƃ��Ă͂܂��ɉ���I�Ȃ�����݂ł��������C�Ȃɂ����܂��H���Ƃ������Ƃɒǂ��Ă��������ł͋@���n���Ȃ������̂��C���ۂɂ͈ψ����12���ɂ����NJJ���ꂽ�����ŁC���a30�N4��15���K�����p�~�����܂ŁC�Ȃ��̊������s���Ȃ������B
�@���N12��4���J�Â��ꂽ��23�c��ł́u���������|�V���̌��v���̑����R�c���ꂽ�B���������|�̐V�݂ɂ������ْ��͂��̂悤�ɐ��������B
�@�}���ق͏��ɂƂ��Ă̏��ɓI�ȗ��ꂩ��ϋɓI�ɓǏ��w���̕����ɔ��W���Ă���̂ŁC���������Ƃ��̂��߂̖ژ^�����͌���̐}���ً@�\�㌇�����Ƃ̂ł��Ȃ��펯�ł��邪�C���̎��v���݂������˂�{�ق̌���ɂ����ẮC�ʎ��Ă̂悤�ȕ��������|��V�݂��āC�{�w�ɑ���C�����[���ɔ���������K�v������B���̂܂܂ł͐}���ق����Ή�����J��������̂ŁC���Ă��������Ă��͂��肷�鎟��ł���B
| ���������|�ɍ���3�W��u�� | ||
| �@ | �����W�@�����W�@�Ǐ��w���W | |
| �����W | ||
| �@ | �{�w���E���E�w���y�юs�����J�}���ى{���҂ɑ��镶�������y�ѕ����{���̕X�Ɋւ��鈴�����Ȃ��ׂɍ��̎�����S������ | |
| �@ | 1�@�w���ڂɊւ��镶�����X�g�̍쐻 | |
| �@ | �@ | �i1�j�@�w�����������Ɋւ��郊�X�g |
| �@ | �i2�j�@�w�O���ݕ����Ɋւ��郊�X�g | |
| �@ | 2�@���v�����̏��ݒ��� | |
| �@ | 3�@�����Ɋւ���w��v���̒��� | |
| �@ | 4�@���v�����̉{�����͑ݏo�Ɋւ��鈴�� | |
| �@ | �i1�j�@�Ίw���I���� | |
| �@ | �@ | �i2�j�@�Ίw�O�I���� |
| �@ | �@ | �i�C�j�@�e���Ԃ̑��ݑݎ؎��� |
| �@ | �@ | �i���j�@���O�}���قɑ��鑊�ݑݎ؎��� |
| �@ | 5�@�}���̈ꕔ�ɑ���ʐ^�B�e�y�у^�C�v�ɂ��R�s�C�쐻�Ɋւ��鈴���@�A������͔Ō��y�щ{���K���Ɉᔽ���ʔ͈͂łȂ���Ȃ�ʁ@�ʐ^�B�e�ɂ͐}���ٓ��Ɏʐ^�B�e�����������Ă��Ȃ���Ȃ�� | |
| �@ | 6�@�}�C�N���E�t�@�C���E�t�B�����̏[���Ɋւ�����y�A�� | |
| �����W | ||
| �@ | ���������ɕK�v�Ȃ鎑���̏N�W���ɐ������Ȃ��ׂɍ��̎�����S������ | |
| �@ | 1�@�{�w�����}���Ɋւ��镶�����������̐��� | |
| �@ | �i1�j�@������q�ژ^�̊��� | |
| �@ | �i�C�j�@�a�����i�u��E�H�E���сv�ȊO�̑S���j | |
| �@ | �i���j�@�m���i�u�������s�����}���ژ^�v�ȊO�̑S���j | |
| �@ | �i2�j�@����������q�ژ^�ɑ��鑝���}���ژ^�̍쐻 | |
| �@ | �i3�j�@�J�[�h�ژ^�̐��� | |
| �@ | �i4�j�@���ꕶ���ژ^�̍쐻 | |
| �@ | 2�@�w�O���������Ɋւ��镶�����������̐��� | |
| �@ | �i1�j�@�����ژ^�E���v���E���̑����������ɕK�v�Ȏ����̏N�W | |
| �@ | �i2�j�@���{�S���̊w�p�}���̑����ژ^�i���j�I���E�J�^���O�j�̍�Ƃɑ��镪�S���� | |
| �@ | �i3�j�@�č�����c�@�}���كJ�[�h�̐��� | |
| �Ǐ��w���W | ||
| �@ | �{�w�w���y�юs�����J�}���ى{���҂ɑ���Ǐ��w�����Ȃ��ׂɍ��̎�����S������ | |
| �@ | 1�@�Ǐ��w���Ɋւ�����E�A���E�y�ш��� | |
| �@ | 2�@�Ǐ��w���Ɋւ��錤����E���k��E���_��E�u����̎�Ëy�єV�Ɋ֘A�����̎��� | |
| �@ | 3�@�Ǐ��w�������Ɋւ����̎����@�A���Ǐ��w���u���͐}���ٓǏ��w���ψ���Ƃ̖��ڂȘA�q�ɂ���ď�݂������̂Ƃ� | |
| �@ | �E�e���ڂ͕v�X����2��ނ̎����ɋ敪���čs���� | |
| �@ |
�i�C�j�@�w����ΏۂƂ��鎖�� |
|
| �@ | �i���j�@�s����ΏۂƂ��鎖�� | |
�@���������|�͖{�قł͂��łɏ��a19�N�ْ�����C�E���@�\�����v���ꂽ�Ƃ��C�͂��߂Ċ|�Ƃ��Đ��ꂽ���C���܂���̐V������w�}���ق̗��O�̂��ƂŁC����ɍ\�z��V�������Čv�悳��C���c��ɂ����Ă��ًc�Ȃ����F���ꂽ���C���̊ٓ��̐l�I�@�\�̂��Ƃł́C���̈Ă̎����͍���ł������B
�@����ɂ��̏��c��̐ȏ�C�������Ă��v�悳��Ă����}���ٖ@�ɂ��Ċْ��������������C�u�}���ٖ@���ł���ƁC�}�����戵���l�Ɏ��i�����邱�ƂɂȂ�B������}���يw���J�u����Ȃ���Ȃ�Ȃ��@�^�Ɍ����Ă���B�l���n�w���̕��X�̗ȉ��āC���w���Ő}���قɊւ���u�`���J���C�₪�Ă͐}���يw�̍u���ɂ������B�v�u����ɒu���Ƃ���C���w���ł��̂��悩�낤�Ƃ������ƂɁC�@�o���w���̗ȉ����̂ŁC�ْ��̕��ňĂ�����Ă���v���Ƃ����ꂽ�B���̌㕶�w���Ő}���يw�̍u�`�͂͂��߂�ꂽ�����w���̎���Ō��Ǎu���͒u���ꂸ�C�̂�����w���̐ݒu�ɂƂ��Ȃ��C����w���Ɉڂ��ꂽ�B
�@���a23�N�i1948�j2���C��w��������u�V����w�ɂ�����}���ق̏d�v���ɒ��Ⴕ�v�āC�}���ٌ����ψ�����݂��C�{�w�����{�������ψ����ƂȂ�C��w�}���ي�̐ݒ�ɒ��肵���B���̂��ߊ֓��E���̗��n��ɒn��ψ����݂��C���n��ψ����23�N��3��16������9��27���܂łɁC�ψ���4��C���ψ���4��������C��w�}���ي���Ă��܂Ƃ߂��B����ɑ��Ċ֓��n��ψ�����֓��Ă��܂Ƃ߂����C�����̈Ă͂�������C������������ɒP�Ȃ̑�w�����ӂ��ނ��ׂĂ̑�w�}���قɒʂ���Œ���ڕW�ɂ��č��ꂽ���̂ł��邩��C����������w�}�����̊�Ƃ��Ă͕s�\���ł������B�����23�N9���k�C����w�ŊJ�Â��ꂽ
����w�}���ً��c���ł́C����������w�}�������V�ψ�����ݒu���C������w�}���ق̗��ꂩ��C��w�}���ي�Ă��C�����邱�ƂɂȂ����B���̂悤�ɏ��a23�N�́C�V����w�ɂ�����}���ق݂̍�����C��w�}���يE�̍��{���Ƃ��ĂƂ�グ���C��w�}���يW�҂̔M�ӂ͊�̐���ɏW������Ă����B
�@����ɂ��̔N��9���ɂ��č��l���Ȋw�ږ�c���������āC��3�����̑؍݂̂̂������쐬�������C���̕��̌��тɂ�����u�����v�ł́C�����̎������C���{�̑�w�}���قɒʗL�ȁu���{�I�Ȍ��ׁv�ɔ�C���̌��ׂ�}���ٍs���̂�����ɋA���Ă���B���̎w�E�͐V������w�}���ق̂������͍����Ă�����w�}���يW�҂ɂƂ��ẮC�傫�Ȏw�j�ƂȂ肦���ł��낤�B
�@���̂悤�ȑ�w�}���يE�̓����ɑ����āC�{�قɂ����Ă�23�N12��24����24�c��ŁC�u�}���ِ��x�̉����āv���R�c���ꂽ�B�����Ċ�Ăɂ��C�}���s���̈�{�����̂��܂������C���̂��߂ɂ́C�{�w�̏ꍇ�C���c���w�S�ʂ̐}���s���̍ō��@�ւƂ��āC�����R�c���邾���łȂ�������s�Ȃ��C����������}���������s����悤�ɂ������Ƃ����Ă���o���ꂽ�B�������R�c�͐}���̑ݏo�C�����Ƃ����}��������̍������ɌX���C���nj��_��ɂ�����Ȃ������B
�@���̖��͂���ɂ��̌�̏��c��ɂ����Ă������Â��ĐR�c����C24�N�i1949�j5���ɊJ���ꂽ��26�c��ł́C�{�ق�������ɏڍׂȁu�}���s���̉��P�Ɋւ���āv����o���ꂽ�B���̈Ăł�
1�@�}���ْ��͐�C�������Ƃ��C�����܂��͎i�����̒�����I�C����B
2�@�}���ْ���������E�ł���ꍇ�͕��}���ْ���u����C�Ƃ���B���}���ْ��͎i�����̂�������I�C����B
3�@�}���ق���т��ׂĂ����ǐ}�������܂߂���w�S�ʂ̐}�����ѐ}���s����i�l�����ѕ�����j�̍��v�z�͑�w��z��20�����m�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
4�@�}���ٌo����͑�w�S�ʂ̐}�����ѐ}���s����̑��z��3����1�ȉ��ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
5�@�}���ق̐}����C�l����C����ѕ�����͐}���ٌo���ɑ��Ă��ꂼ����̔䗦�ł��邱�Ƃ��]�܂����B
�@�}����@30��
�@�l����@50��
�@������@20��
�Ȃǂ������ꂽ���C�������Ȃ������B
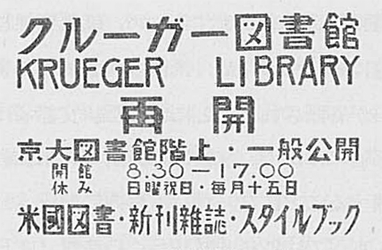 |
|
�N���[�K�[�}���ٍĊJ�̃|�X�^�[
|
 |
|
��8��ْ��@���v�V��
|
���ْ�����͋�����w����V����w�ւ̉ߓn���ł���C����ɂƂ��Ȃ��}���ٗ��O�̍���������C��w�����͐V������w�}���ي�̐ݒ�ɒ��肵�Ă����B���ْ�����ɐV����w�͂��悢��o���������C�܂�����ׂ��V������w�}���ق̗��O�͊m������Ă��Ȃ������B���������Đ��ْ�����̎g���́C�V������w�}���ق̗��O���m�����C���̂��߂̑̐��𐮂��邱�ƂłȂ���Ȃ�Ȃ������B
�@��25�N�i1950�j10�������C���ْ��͏�����ăA�����J�̑�w�}���َ��@�̗��ɏo�C��26�N3���A�w�������Ƃ́C�}���ٗ��O�̊m�������܂��Ă����{�قɂƂ��ẮC�܂��ƂɍK���ł������B���̊ԁC���O�ْ����ْ��㗝�Ƃ��čݔC�����B
�@�܂����a25�N������C�l���@�͍��ƌ������̑S�E��ɂ��āC���̊��E�̊i�t�����邽�߂́u�E�������v�𗧈Ă��������B����ɂ��C��w�}���ِE���ɑ��ẮC�u�i���E�ʐE�������v���K�p����C�ꉞ�Ɨ��̐E��Ƃ��Ď�舵���C1���i������5���i���ɂ�����E�����ݒ肳��邱�ƂɂȂ��Ă����B���̐l���@�̗��ẮC���a21�N�̊����̉��v�ɂ��C�i�����E�i���Ƃ����}���ًƖ��̂��߂̐��E�킪�F�߂��Ȃ��Ȃ��Ĉȗ��C���̕����������v�]���Ă����S���̑�w�}���يW�҂̒��ڂ��W�߂��B������̔N��4��30���ɂ͂킪���ŏ����}���ٖ@�����z����C�����}���قɂ����Ă͐��E���Ƃ��Ă��i���E�i�������@���̏�ɖ��������ꂽ�B����ɂ��܂܂���w�}���قɂ����Ă�
�u�i���E�ʐE�������v���K�p����悤�Ƃ��Ă���B�������ď��a25�N�Ƃ����N�́C���ɂ�����킪���̐}���يE�������Ƃ��N���������N�ł������B���������́u�E�������v�̗��Ă͎��������C��w�}���يW�҂̊��҂����A�ɋA�����B
�@���̂悤�ȊيE�̓����ɂƂ��Ȃ��C�{�قɂ����Ă�25�N7���C�E���@�\�̗��̉����͂���C�a�����ژ^�|���m���ژ^�|�����̉��ɒu���C�܂�����|�E���Ɋ|������{���ݕt�|���^�p�ۊǕ��̉��ɒu���āC�����ɕ���C�������C���̓I�E���@�\�����������B
�@���a26�N�i1951�j����͖{�ٓ��������݂����C�����28�N�ɂ͒ɏ�݂̒�p�K���X�P�[�X���������ꂽ���ƂƂ����܂��āC�e��̓W�����C����Ɗ֘A����u���������ɊJ�Â���C�{�ق̏�������L�x���M�d�}�����L�����J����Ă����B
�@�܂�26�N����C�}���ٖ@��̎i���E�i����{���̂��߂̍u�K��{�w�ʼnĊ��J�Â���邱�ƂɂȂ�C�}���و��{���ɑ傫���v�������B
�@���a27�N�i1952�j2��22����28�c��J�Â���C���Ă��V���Ɋ����̑��i�̂��߁C���c��ψ������ő������ĂɊ������i�̐��菑���o���ꂽ�B�܂����̏��c��ŁC�S�w�̐}�������̍������ɂ��ē��c����C�S�w�̃J�[�h�ژ^�̍쐻�C�����}���̔����C�[���Ǝ������{�����čs�Ȃ����Ƃɂ��āC���㌟�����邱�ƂɂȂ����B
�@���̔N6���ɂ́C23�N�ȗ���������Ă����u��w�}���ي�v���C��w�}���ي�������甭�\���ꂽ�B�V����w�}�����̂���ׂ�����������̂Ƃ��āC��w�}���يW�҂̑傫�Ȋ��҂��������Ă������C���ۂɊW�������Ă݂�ƁC���ǂ����Ƃ��n��ȕ��ނɑ������w���C��w�Ƃ��Đݗ��̔F���悤�Ƃ���ꍇ�ɎQ�l�Ƃ����R����̂ЂƂł����āC�啔���̑�w�ɂƂ��Ă͉��̂��������̂ł������B����ł��C���E�Ƃ��Ă̎i���C���邢�͐��E�Ƃ��Ă̐}���ْ����������Ă���_�ȂǁC��w�}���ق̍���̖ڕW�������_���Ȃ��ł͂Ȃ��B
�@�u��w�}���ي�v�͍������̂��ׂĂ̑�w�}���قɓK�p�����ׂ���ł��������C27�N7������C�Ƃ���������w�̐}�����̂�������������邽�߁C�����Ȃ́u������w�}���ى��P������v��ݒu���C��28�N11���ɂ͐��ĂāC�u������w�}���ى��P�v�j�y�т��̉���v�Ƃ����S��26�ł���Ȃ����������s���ꂽ�B���́u���P�v���v�͍�����w�}���ق̂���������������̂ł���C�e��w�ɑ��čS���͂������̂ł͂Ȃ��������C���{�̑�w�}���ق��悤�₭�ɂ��ē��B�������O���������̂ł������B���ْ�����я��q�������͂������P�������ɎQ�����C��w�}���ّS�ʂ̔��W�ɍv�������̂ł������B
�@���̂悤�ȑ�w�}���يE�̓����̒���28�N�i1953�j10��26����29�c��J�Â��ꂽ�B�܂��C11���ŔC�������ƂȂ���ْ��̌�C�ْ��̌��ɂ��ẮC���ْ��̍đI������B���Ŗ���41�N����ȗ���������邱�Ƃ̂Ȃ��������c��K������̌����R�c����C���ْ����u��w�}���ى��P�v���v�ɂ��C�ْ��͐}���ى^�c�ψ���̈ψ����ł��邱�ƂɂȂ��Ă���|�̐������������̂��C���̉����Ă������ꂽ�B
| ���s��w�}���ُ��c��K�� | ||
| �@ | ��1���@���s��w�ɐ}���ُ��c���u�� | |
| �@ | 2�@���c��͍��̂��̂������đg�D���� | |
| �@ | �@ | 1�@�w���� |
| �@ | �@ | 2�@�w�������e1�� |
| �@ | �@ | 3�@���Z�厖 |
| �@ | 4�@�}���ْ� | |
| �@ | ��2���@�����ňψ��ƂȂ���͓̂��Y�w�������̌ݑI�ɂ���Ċw���������� | |
| �@ | 2�@�ψ����͈ψ����ݑI���� | |
| �@ | �@ | 3�@�ψ����͏��c������W���Ă��̋c���ƂȂ� |
| �@ | 4�@�ψ����Ɏ��̂�����Ƃ��͔N���̈ψ������̎������s���� | |
| �@ | �@ | 5�@�ψ������������Ƃ��́C��C�҂̑�����w���̒��ł���ψ����C�ψ����I�o�̂Ƃ��܂ł��̎������s����B |
| �@ | ��3���@���c��Ɋ����y�я��L�e1����u�� | |
| �@ | �@ | 2�@�����͐}���َ������������ď[�Ĉψ����̎�����⍲���� |
| �@ | 3�@���L�͐}���ق̎������������ď[�Ĉψ����̎w���������ď����ɏ]������ | |
| �@ | ��4���@�ψ��̔C����3�N�Ƃ��� | |
| �@ | 2�@�ψ����y�шψ��⌇�̏ꍇ�̔C���͑O�C�҂̔C���ɂ�� | |
| �@ | ��5���@���c��͍��̎�����R�c���� | |
| �@ | 1�@�}���قɊւ��C�w�����玐��̂��������� | |
| �@ | 2�@�}���ْ������c�̂��������� | |
| �@ | 3�@�}���قɊւ��ψ������c�̂��������� | |
| �@ | ��6���@���c��͈ψ���3����2�ȏ�̏o�Ȃɂ���Đ������c���͂��̉ߔ����ɂ��A���ۓ����̂Ƃ��͈ψ����������� | |
| �@ | ��7���@�ψ������K�v�ƔF�߂��ꍇ�͈ψ��ȊO�̖{�w�E�����ψ���ɗ�Ȃ����߂邱�Ƃ��ł���B�A���c���̐��ɉ����Ȃ� | |
| ���@�@�� | ||
| �@ | ���̋K���͏��a28�N�@���@������{�s����B | |
�@�ȏ�̔@���C�ψ��̒��ɐ}���ْ��������邱�ƂƁC��c�̐����������V���ɉ�����ꂽ�̂ł������B
�@�������Ȃ���C���̋K�������ł��C�܂��\���Ɂu���P�v���v�̎�|�ɂ͍��v�����Ȃ����C�ْ��̐ӔC���N���łȂ��B�����ōēx���{�I�ɏ��c��K�����������邽�߁C���N12��1���t���u�}���ُ��c��K�������āv�����c��ψ������ňψ��ɔz�z���ӌ������߂��B�����ĂɓY����ꂽ������
�@�}���ُ��c��K���ɂ��Ă͋���10��26�����̉����ɂ���R�c�����肢�������܂������C��w�̋���ƌ����̏�ɐ}���ق̏d�v�������X�傫����������܂��܁C�@��w�}���ْ��̐ӔC��N���ɂ����c��̊����������ɂ��錏�ɂ����}���ْ��Ƌ��Ɋw�����@�ւ̓���K�����Q�l�ɂ��Ď�X�����������܂������ʁC�K�������{�I�ɉ�������K�v��Ɋ��������ʎ��̔@�������Ă��쐬�������܂����B����ē������Ăɂ���ًc���тɌ�ӌ��̗L�������肽�������X������肢�������܂��B
�ł������B
�@�����Ăً͈c�Ȃ��ψ��̏��F��29�N1��26�����{�s���ꂽ�B���ꂪ���s�̋K���ł��邪�C���̉����͉����Ƃ������́C�S���V��������Ƃ����Ă������B���Ȃ킿�C�]���͗�Ȏ҂ł������}���ْ��͉�̎�Ɏ҂ƂȂ�C�܂������̎���@�ւł���Ƃ������i���������B�p��̏�ł́C����܂ŏ��c��ψ��Ə̂��Ă������̂����c���Ɖ��߂��C�ψ����͋c���ƂȂ����B�������Đ}���ُ��c��Ɛ}���ْ��Ƃ̊W�͍��{�I�ɕϊv���ꂽ�̂ł���B
�@����ɂ��̉�̏��c��ł́C�����}���ًK������ѓ����s�葱���������ꂽ�B���̉��������{�I�Ȃ��̂ł����āC�{�ّn���ȗ��u���s�鍑��w�����}�����n���s�鍑��w�m�}���������X�����g�X�v�Ƃ������{�ًK����1�����C�͂��߂āu���s��w�����}���ق́C���s��w�ɏ�������}���̊Ǘ��Ɖ^�p�������ǂ�v�Ɖ��߂�ꂽ�B�}���ق�}�������鏊�ƋK�肷��C�ÓI�ȁC���ɂ̔Ԑl�I�}���ٗ��O��E�p���āC�u�}���̊Ǘ��Ɖ^�p�������ǂ�v�ƋK�肷��C���I�ȁC�@�\�I�Ȑ}���ٗ��O�ɓ��B����܂łɁC�{�قł�54�N�̗��j������Ă���B�������C�����܂ł��Ȃ����C���̂悤�ȓ��I�ȁC�@�\�I�Ȑ}���ي������C���̋K���������܂��Ă͂��߂Ďn�߂�ꂽ�̂ł͂Ȃ��B�K���̉������R���ɂ��C�u�K����1���̉����͓��ق������ɐ��s������g�������̂܂Ƃ��ĉ��߂��ɂ������v�Ə�����Ă���ʂ�C�����͂��łɏ��ɓI�}���ق̂�������͂邩�ɉz���ė��ꓮ���Ă��Ă����̂ł���B�K���̂����ꂪ�C���܂����ɍ��{�I�ɉ������ꂽ�̂ł���B
�@����ɒ��ڂ��ׂ����Ƃ́C���̏ꍇ����܂ő����̋���K�v�Ƃ��邱�ƂɂȂ��Ă����̂��C���ׂĊْ��̋��邱�Ƃɉ��߂����Ƃł���B
1�@�����C�������C�u�t��2���ȏ�M�d�}�����ؗ�����K�v�̂���ꍇ
2�@�E���i�����C�������C�u�t�������j�C���ʉ{���[��L����ҕ��тɊw���ŋM�d�}�����{������Ƃ���ꍇ
3�@�ċG�x�ƒ��}���̎ؗ�����]����ꍇ
4�@���������͌����c�̂ɑ��Đ}���̑ݕt���s���ꍇ
5�@�������̐E�����͌����c�̂̑�\�҂Ɍ��p��}���̉{����������ꍇ
�@�������Đ}���̊Ǘ��Ɖ^�p�Ɋւ��邢�������̌������ْ��ɑ����邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@���̑��]���̕Љ�������̂��C�Ђ炪�Ȃ̌���̂ɉ��߂���ȂǁC�{�ًK������т��̎��s�葱�͂����ɑS����ς��C�V������w�}���قɂӂ��킵�����̂ƂȂ����B���̉����K����29�N1��26�����{�s���ꂽ�B
�@���̂悤�ɂ��̑�29�c��͖{�ق̐V�����E����͂��������ƂŁC�{�َj��d�v�ȈӋ`�������c��ł������B�܂��C���̏��c��ȍ~�͏��c��ɉ����Ȃ��Ȃ����B
�@28�N11���ɂ́C�^�p�ۊǕ����Q�l�|���ݒu����C�ߑ�}���ق̏d�v�ȋ@�\�ł���Q�l�������Ƃ舵�����ƂƂȂ����B
�@�����29�N�i1954�j�ɂ́C�{�ق��ߋE�n��}�C�N���t�B�����E�Z���^�[���Ƃ��āC�����Ȃ����ʂɋ@�ލw���\�Z�C���悢�斾�N�x����}�C�N���t�B�����ɂ���������ʋƖ����J�n���邱�ƂɂȂ����B
�@�܂����N�و��ꓯ�����̊�����Җ]���Ă����V������29�N�ɂ́C�G���x�[�^�[�H�����c���Ċ����C30�N�i1955�j7�����}���̔������J�n���C12���ɂ͔����\��̐}�������ׂĔr�˂��I�邱�Ƃ��ł����B�����ď��a11�N�{�����Ď��ȗ��C���ɂƉ{�����Ƃ̕����ɔY�܂��ꑱ���Ă����{�ق��C����Ɩ{���̎p�ɂ����邱�Ƃ��ł����B����ňꉞ�����͈�ʂ�ł���������C���̑唼�͂܂��R���N���[�g�̂܂܂ł���C�O�����R���N���[�g�̍r�ǂ̂܂܂Ƃ������肳�܂ŁC�������ɂ��������ߑ�}���ٌ��z�Ƃ͌����Ȃ��B�����̌v��ł������n��3�K���C�h�����Ēn��2�K�܂Ő����������݂̂ł���B���������Ĉ��������3�K�z���C�{�����̎��e�͂����݂�2�{�ɂ���ƂƂ��ɁC�ߑ�I�ȑ�w�}���قƂ��ėv������鑽�p�I�ȉ^�c���\�ɂ��錚���̗]�T�������C���ɂ�7�w�Ƃ����e�͂𑝂����C���̊����̑����������������҂���Ă���B
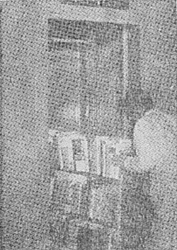 |
|
���ɓ��G���x�[�^�[
|
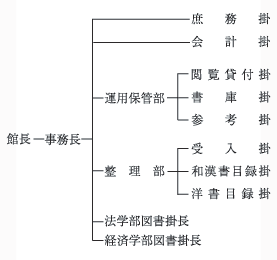
�@32�N�i1957�j1��10��������i�Ǘ��@���{�s����邱�ƂɂȂ����B���̖@���͍�����w�ɂ������}���Ǘ������ɂ��낢��ȉe��������ڂ��C��w�ɂ���ẮC���̖@���̎{�s�ɂ���āC�}���ɑ���]���̒����Ǘ����������āC�Ǘ����ǂ��Ƃɕ��U������w������C���̋@�ɏ]���̊Ǘ��̕��U��}���قɏW�����āC�}���ق��S�w�̐}���Ǘ����s�Ȃ��悤�ɂȂ�����w���������B�{�w�ł͑n���ȗ��S�w�̐}���͖{�قŊǗ�����Ƃ����C�W���Ǘ��������Ƃ��Ă����̂ŁC���̖@���̎{�s�ɂ���āC�S�w�̐}���̊Ǘ������}���َ������Ƃ��邱�Ƃɂ���āC�W���Ǘ�������@�I�����̂�����̂ɂ��邱�Ƃ��ł����B
�@���������ǖ@�̂��߁C�}���ًK�����ꕔ����������Ȃ��Ȃ�C32�N4��12���̏��c��ʼn����Ă��R�c���ꂽ�B���Ŋْ��C���̖�肪�R�c���ꂽ���C�����{�قْ̊��C����4�N�ł���C4�N�Ƃ����C���͑S��������w���{�ق݂̂ł���C���Œ��̔C���ł������B������4�N�̔C���ł͍đI������8�N�ɂȂ�C�Z���������E����ɏ]�����邩�����ْ��̐E�ɁC���̂悤�ɒ����݂邱�Ƃ͑�ςł��낤���C�������Ă��̂��ߍ���ْ��ɂ����Ȃ邨���������Ƃ������Ƃ�3�N�Ƃ������ƂɂȂ��āC�����}���ْ�������t���K�̈ꕔ���������ꂽ�B
�@���̔N�̉Ă������ْ��͉��Ċe���ɗ��t�܂ŊC�O�o�����邱�ƂɂȂ����B���ْ��̔C����32�N10��14���܂łł��邪�C7�����{���C�O�ɏo�邱�ƂɂȂ�Ίْ��㗝��u���˂Ȃ�Ȃ��B�������A���͗��N3���ł��邩��C�C�O�o�����ɔC������������B���������ĕs�ݒ��ْ��㗝��u�����C�C���O�Ɏ��E�������Ƃ������ƂŁC6��28����C�ْ���t�̂��ߏ��c��J����C�@�w�������c�����F���I�o����C7��15���t�Ŋْ��̌�ւ��s�Ȃ�ꂽ�B
�@���ْ��͏��a24�N�{�w�̐V����w�Ƃ��Ă̏o���ƂƂ��ɐ}���ْ��ɏA�C���C�ݐE8�N�ɂ킽��C�V���x���ɂ������w�}���ٗ��O�̊m�����ْ̊��Ƃ��āC���łɏq�ׂ����Ƃ��C���a28�N�ȗ��}���ُ��c��K���C�}���ًK���C�y�ѓ����s�葱���{�قɊւ��鏔�K�������{�I�ɉ��v���C�V������w�}���ى^�c�̊�b���m�������B����{�ِV�ق̓����{�݂̐����ɂ��w�͂��d�ˁC���a29�N�ɂ͐V���ɂ������C�{�����Ə��ɂƂ̕����Ƃ����C�}���قɂƂ��Ă̒v���I�Ȍ��ׂ��������C�ߑ�}���قƂ��Ă̖{�ق̊�b���ł߂��B������Q�l�|��ݒu���C�������ʋƖ����J�n����ȂǁC�{�ًƖ���傫��������̂ł���B
 |
|
���ْ��@�c�����F
|
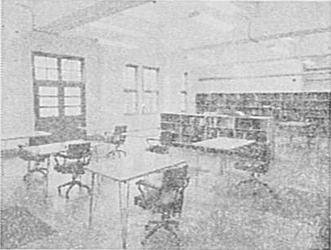 |
|
�A�����J�����Z���^�[�}����
|
| �@�i1�@�K�j | ||
| ���� | �L�T | |
| ������ | 115�D7�� | �i382�D5�u�j |
| �ْ��� | 19�D1�V | �i63�D1�V�j |
| �������� | 12�D3�V | �i40�D7�V�j |
| �� | 36�D0�V | �i119�D0�V�j |
| �u���� | 36�D0�V | �i119�D0�V�j |
| ��c�� | 18�D0�V | �i59�D5�V�j |
| �V���{���� | 17�D0�V | �i56�D2�V�j |
| �n���C������ | 7�D0�V | �i23�D1�V�j |
| �E���x�e�� | 7�D0�V | �i23�D1�V�j |
| �֏��i���k���j | 5�D5�V | �i18�D2�V�j |
| �֏��i���암�j | 4�D5�V | �i14�D9�V�j |
| ���g�� | 9�D0�V | �i29�D8�V�j |
| �L���y�ъK�i | 135�D4�V | �i447�D6�V�j |
| �v | 422�D5�V | �i1�C396�D7�V�j |
| �@�i2�@�K�j | ||
| �{���� | 187�D4�� | �i619�D5�u�j |
| �{�������� | 82�D8�V | �i273�D7�V�j |
| �ژ^�� | 24�D5�V | �i81�D8�V�j |
| ���_�����{���� | 8�D4�V | �i27�D8�V�j |
| ���E���{���� | 12�D3�V | �i40�D7�V�j |
| �֏��i���k���j | 5�D5�V | �i18�D2�V�j |
| �֏��i���암�j | 4�D5�V | �i14�D9�V�j |
| �L���y�ъK�i | 94�D0�V | �i310�D8�V�j |
| �v | 419�D4�V | �i1�C386�D6�V�j |
| �@�i�n�@�K�j | ||
| �������ʎ� | 50�D0�� | �i165�D3�u�j |
| �A�����J�����Z���^�[�}���� | 62�D5�V | �i206�D6�V�j |
| �q�� | 29�D1�V | �i96�D2�V�j |
| ���u | 5�D5�V | �i18�D2�V�j |
| �L���y�ъK�i | 53�D7�V | �i177�D6�V�j |
| �v | 200�D8�V | �i663�D9�V�j |
| �@�i���@�Ɂj | ||
| 1�w | 83�D4�� | �i275�D7�u�j |
| 2�D3�D4�D5�w | 316�D0�V | �i1�C044�D8�V�j |
| �v | 399�D4�V | �i1�C320�D5�V�j |
| ���v | 1�C442�D1�V | �i4�C767�D7�V�j |
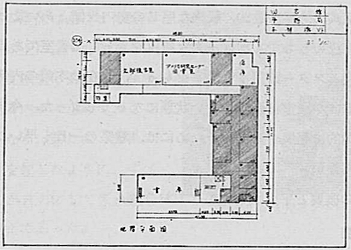 |
 |
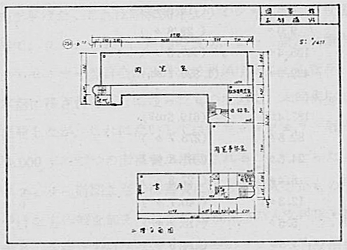 |
�@���a34�N�͖{�ّn��60���N�ɂ�����B50���N�ڂ͔s���̍�����������Ɣ����o�悤�Ƃ���悤�Ȏ����ł��������߁C�Ȃ��̋L�O�s�����s�Ȃ�ꂸ�ɏI�����B��y�e�ʂ̋ꓬ�ɂ���Ă���Ɣ��W�ւ̊�Ղ������C�[���ߋ��̗��j��T��C�����ւ̐V���Ȕ��W�����҂��邽�߁C�`�͂����₩�ł͂����Ă��C�S�ق������ċL�O�̍s�����s�Ȃ����ƂɂȂ����B���̂��߂��ł�33�N10��7���̏��c��ŁC�����}����60���N�L�O�o�łɊւ��錏���R�c����C�{�����ꕶ�ɂ̑����ژ^�̍쐬�C���邢�͋H�Q���̕��������낢��̈ӌ����o�����C����݂͂Ȃ������B
�@34�N3���C�{�w���㑍���ł���C�n�݊��̖{�ق̔��W�ɂ����鉇����^�����؉������̏ё���̏C�������������B���̖��G�ё��͊z�͉��C�v�����������Ԃ��ď��ɂɕۊǂ���Ă����B���̂��߉i�N�̊Ԃɉ�ʂ̖������w�ω������āC��F�ϐF���Ă����B������������O�����̏ё�����쐬�������I�����攌�Ɉ˗����ďC���C�V���Ɋz�����쐬���Ă�������̂ł���B���̏ё������䒉�攌�̍�Ƃ����Ă������C���x�̏C���ɂ��C��ʂɂ͂������1907�NC.
Asai�Ƃ����T�C�����łĂ��āC���攌�̕M�ɂȂ���̂ł��邱�ƁC1907�N�̍�Ƃ������Ƃł���C���̉悪���攌�̐�M�ƍl�����邱�ƁC�S���������邱�̉�͓��攌�̉�Ƃ��Ă͍ő�̂��̂ł��邱�ƁC�܂��]���̓��攌�̍�i�ژ^�ɂ͏o�Ă��Ȃ���i�ł��邱�Ɠ����炵�āC�ɂ킩�ɐV���ʂ���킵�C���p���D�҂̖K�˂���̂��H�ł͂Ȃ������B�{�ق�60���N�ڂɂ�����N���؉������̏ё���̏C�����Ȃ�C�{�ى{�������̗�㑍���̏ё���̃g�b�v�ɏ����C����Ⴂ�w�������̕w���܂����ƂɂȂ����̂́C�S����Ƃ������ׂ��ł��낤�B�Ȃ��{�ى{�����ɂ͌��݁C�؉������̏ё���̂ق��ɁC�����d���i���q�ؖИY�M�j�C���䌳���i���q�ؖИY�M�j�C�l�c�k���i���c���Y�M�j�C���{���O�Y�i�{�c�����Y�M�j�C�����s���Y�i�{�c�����Y�M�j�C���K�C�i���I����M�j�e��㑍���̏ё��悪�f�����Ă���C���s�m��d�d���̂��Ȃ���ё���̉�L����ς�悵�Ă���B
�@12��11���̑n��60���N�̋L�O���T�C����т���ɂƂ��Ȃ��e��̋L�O�s���̂��߂̏����́C���X�Ƃ����߂��Ă������C�≎��������10�����2�������A�����J��w�}�������@�̂��߃A�����J�ɏo���𖽂����C�L�O�s���̏����ɎQ���ł��Ȃ��Ȃ����B�����������͒x�Ȃ��i�݁C12��11���L�O���T���J�Â����B
�@�L�O���T�͓����ߌ�3�����{���u�����ɂ����ĊJ�ÁC���͊≎�������̎i��̂��Ƃōs�Ȃ�ꂽ�B������͂��̒ʂ�ł������B
���s��w�����}����60���N�L�O���T������
�@1�@�J��̎�
�@2�@�ْ���������
�@3�@�����������i�㗝�@�_�w�����n�ӗf��Y�j
�@4�@�i�N�Α����\��
�@5�@���o�j���i�O�ْ��@�V���o���_�����j
�@6�@��̎�
�@���T��2�K�{�����ɐ݂��������ŊȒP�ȏj�����J���C�V���C���C���C����̊e�O�ْ��C�|�сC�����C�{���C���q�̊e�O�i�����C�����������͂��߁C�����̋��E������������C�����k�ɉԂ��炩���C�{�ق�60���N���j���Ă����������B
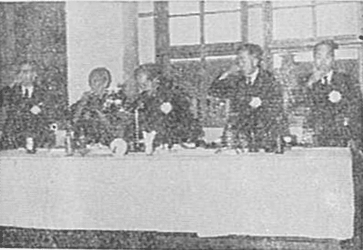 |
|
60���N�L�O�j���
������c���ْ��C�V���C�C���̊e�O�ْ��C�n�Ӕ_�w�����i�����㗝�j |