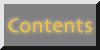
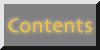 |
第2節 目 録
カードは近代図書館の機能に大きな役割を演じている。図書館の仕事といえば「カード書き」といわれる程,図書館の仕事の大きな部分を占めている。最近100年間の図書館界の先覚者達の努力は,カード記入の統一を目ざしていたといっても過言ではない。カードこそ図書館のアルフアでありオメガである。
本館においても明治30年の創立準備時代から,カードが作られたのは当然である。まず目録掛が原本から事務用カードを作り,原本にはさんで分類掛,捺印掛,ラベル掛に渡し,それぞれカードによって処理した後,検査掛が照合して現本とカードを分離し,カードだけが原簿掛を経て,謄写掛によって閲覧用カードが作られ,最後にカード箱に排列され,ここに始めて事務用カード目録および閲覧用カード目録が編成されるのである。このように事務用原稿カードは幾多の役割を果して後,その終着駅に到達するのである。明治時代にはカードを牌子または牌紙と訳していた。明治41年の本館図書館案内に,当時本館で作成していたカード目録について,次のように述べている。
……印刷セザル目録類ニシテ成レルモノハ牌紙形ニテハ閲覧室ニ出ダセル和漢洋分類目録,洋書著者名目録,事務室ニ備フル和漢書書名目録,洋書著者名目録,函架目録,特別取扱図書目録(近衛本,大中院本ノ如キ)アリ。
これを図示すると次の通りになる。
すなわち明治40年には以上の8種類のカード目録が備付けられていた。カードの大きさは事務室用は47mm×122mmの小形であり,閲覧室用は標準形を用いていた。この大小二様を使用することは当時の一般的傾向のようである。たとえば日本図書館協会編「図書館小識」(大正4年刊)によれば,「目録用のカードは我国にては目下一定の型式無く,各館各様のものを使用せり。通例大小二様を具へ,大形のものを閲覧室用目録に充て,小形のものを事務室用目録に充つ……」とある。
昭和11年の火災で閲覧室用カード目録が焼失したので,その復旧は焦眉の急務であったから,直ちに計画が立てられ,同年4月からその作業が始められた。
| 閲覧用カード目録復旧計画書(昭和11年2月5日起案) | |||
| I. 事務ノ概要 | |||
| 1. 今回復旧ヲ要スル閲覧用カード目録ハ謄写カード枚数凡ソ74万枚ニシテ内和漢書約50万枚,洋書約24万枚ナリ。 | |||
| 2. 目録ノ体系ハ和漢書ニアリテハ第一種分類目録,第二種書名目録トシ,洋書ニアリテハ第一種分類目録,第二種著者名目録トス。 | |||
| 3. 右4種ノ目録ヲ1カ年間ニ完成スルモノトス。 | |||
| II. 要 員 | |||
| 1. 所要人員ハ主任1名,庶務1名,指導員2名,整理員6名,謄写員22名トス。 | |||
| 2. 主任ハ司書官ヲ以テ之ニ充ツ。 | |||
| 3. 庶務ハ書記ヲ以テ之ニ充ツ。 | |||
| 4. 指導員ハ司書ヲ以テ之ニ充ツ。但シ,2名ヲ専務トシ,其他ノ司書又ハ嘱託中ヨリ随時之ニ参加協力セシム。 | |||
| 5. 整理員ハ高等ノ教育ヲ受ケタルモノ又ハ語学,書誌学ニ通ジ斯種ノ事務ニ堪能ナリト認ムルモノヲ採用ス。 | |||
| 6. 謄写員ハ写字正確,筆蹟優秀ナルモノ又ハタイプライターノ技術ニ練達セルモノヲ採用ス。 | |||
| III. 分 掌 | |||
| 1. 主任 目録復旧事務ノ全般ニツキ監督ス。 | |||
| 2. 庶務 庶務会計ニ関スル事務ヲ処理ス。 | |||
| 3. 指導員 | |||
| a. | 整理員及謄写員ニ目録法ノ大要並ニ現在備付事務用カード目録ノ一般ニツキ説明ス。 | ||
| b. | 整理員ノ分担復旧スベキ個所ヲ指示ス。 | ||
| c. | 復旧スベキカードノ内整理員ノ疑問ヲ生ズル虞アル個所ニツキテハ予メ之ヲ調査シ,其説明ヲナシ又整理員ノ質問ニ応ズ。 | ||
| d. | 目録ノ記入事項,分類等ニ於テ不統一アルモノニ対シテハ整理員ヲ助ケテ整頓セシメ,書庫ヨリ実本ヲ出シ,カードト照合シ,其レッテルトカードノ分類記号ヲ統一シ,同時ニ函架目録ヲ修正ス。 | ||
| e. | 整理員ノ複製シタルカードヲ検閲シ誤謬ナキコトヲ期ス。 | ||
| f. | 謄写済カードノ排列ニ際シ,排列法ヲ詳細ニ説明シ且ツ指導ス。 | ||
| 4. 整理員 | |||
| a. | 指導員ノ方針ニ従ヒ,事務用カード中ノ本館図書ノ基本カードヲ指示シ,謄写員ヲシテ之ヲ謄写セシム。 | ||
| b. | 必要ニ応ジ書庫ノ実本トカードトヲ照合シ其レッテル及カードノ分類記号ヲ統一ス。 | ||
| c. | 各カードニ対シテハ記入事項特ニ其標目ヲ完全ニ統一整理シ,謄写ニ便ナラシム。 | ||
| d. | 謄写員ノ内甲班ヲシテ事務用カードニヨリテ謄写ニ当ラシメ,乙班ヲシテ甲班ノ謄写シタルモノヲ更ニ複写セシム。 | ||
| e. | 謄写済ノカードヲ検閲シ其記入事項,インデンシヨン,誤字,誤写等ヲ調査シ,若シ誤謬ヲ発見シタルトキハ直チニ訂正セシム。 | ||
| f. | 基本カードニツキテ参照又ハ分出スベキ個所ヲ指示シ,謄写員ヲシテ其等ノ参照又ハ分出カードヲ作製セシム。 | ||
| g. | 新ニ分類ヲ要スベキカードハ指導員ノ指示ヲ受ケ之ヲ分類ス。 | ||
| h. | 謄写済ノカードハ之ヲ分類別用又ハ書名別用,著者名別用ニ区別シテ之ヲ整理保管シ,検索ヲ可能ナラシム。 | ||
| i. | カードノ排列ハ指導員ノ指示ニ従ヒ,謄写員ニ之ヲナサシメ且ツ検閲ス。 | ||
| 5. 謄写員 | |||
| a. | 謄写員ヲ甲乙二班ニ分チ,甲班ハ事務用カードニヨリ謄写スルモノトシ,乙班ハ甲班ノ作製シタルカードヲ複写スルモノトス。 | ||
| b. | 整理員ノ指示ニ従イ正確ニ謄写ス。若シ疑問ヲ生ジタル場合ハ整理員ニ質問ス。 | ||
| c. | 作製シタルカードハ整理員ニ廻附シテ検閲ヲ受ケ,修正スベキ場合ハ其都度修正スルヲ要ス。 | ||
| d. | 排列ニ際シテハ整理員ノ指示ヲ受ク。 | ||
| e. | 謄写員甲班ノ特務 | ||
| 1. 記入法,標目,インデンシヨンヲ完全ニス。 | |||
| 2. 参照又ハ分出ヲ要スルモノハ整理員ノ指示ニ従ヒ,カードヲ作製ス。 | |||
| 3. 1日平均80枚謄写スルヲ要ス。 | |||
| f. | 謄写員乙班の特務 | ||
| 1. 甲班ノ謄写シタルカードヲ忠実ニ複写ス,若シ不審アルモノヲ発見シタル場合ハ整理員ニ申出ヅ。 | |||
| 2. 1日平均120枚謄写スルヲ要ス。 | |||
| 3. 右ノ外乙班ハ適時指導員ノ命ヲ受ク。 | |||
| IV. 要員ノ配置 | |||
| 1. 要員ハ和漢書部及洋書部ノ2部ニ分チ,各部ヲ更ニ甲乙ノ2班ニ分ツ。 | |||
| 2. 和漢書部ニ於テハ甲班ハ第1種分類目録ノ作製ニ充テ,乙班ハ第2種書名目録ノ作製ニ充ツ,其配置ハ左ノ如シ。 | |||
| 指導員 | {甲班 整理員 3名 謄写員 9名 | ||
| {乙班 整理員 1名 謄写員 5名 | |||
| 3. 洋書部ニ於テハ甲班ハ第1種分類目録ノ作製ニ充テ,乙班ハ第2種著者名目録ノ作製ニ充ツ,其配置ハ左ノ如シ。 | |||
| 指導員 | {甲班 整理員 2名 謄写員 5名 | ||
| {乙班 (整理員ハ甲班兼務) 謄写員 3名 | |||
| 閲覧室用全学総合カード目録作製費 | ||||||
| 学術研究ノ進歩ト共ニ他面分化ニ伴フ弊ノ避ケ難キ事ハ既ニ述ベタリ。故ヲ以テ甲ノ学部ハ乙ノ学部ノ研究ノ現状ヲ知ラズ。丙ノ教室ハ丁ノ教室ノ現状ヲ知ラザルモノ十中八九然リト云フモ過言ニハアラズ。尤モ互ニ隣接セルノ故ヲ以テ相互接触ノ機会ハアリト雖其ノ間ノ有機的積極的連絡ニ至リテハ多大ニ遺憾ノ点アルヲ否ミ得ザルベク,茲ニ中央図書館トシテノ本館ノ使命ノ一端ヲ見ルナリ。即チ現在各学部及教室ハ公用借用ノ形ニヨリテ活溌ニ本館ノ蔵書ヲ利用シツツアルモ,互ニ他ノ図書ニ接シ,又之ヲ利用スルノ便宜ノ甚乏シキ現状ニアルヲ以テ,本館ハ先ツ全学蔵書ノ総合カード目録ヲ作製シ,之ヲ閲覧室ニ備ヘテ学内一般ノ自由調査ニ提供シ,更ニ進ンデ所属教室ニ支障ナキ限リ相互閲覧ノ希望ニ対シ斡旋ノ労ヲ取ラントス。 | ||||||
| 而シテ昭和十二年度以降受入図書ノ総合目録ハ既ニ本館ノ経常費ニヨリテ作製ノ道ヲ樹テタルニヨリ,十一年度以前ノ分ハ之ヲ臨時費ニヨリ完成セントス 。 | ||||||
| 総合カード目録作製案大要 | ||||||
| 総合カード目録ハ事務用トシテ一組本館事務室ニ備附アリ。其内ヨリ学部蔵書カードヲ摘出謄写シ之ヲ検査分類シテ分類別ニ配列ス。 此ノ計画ニ含マルル図書数概算左ノ如シ。 |
||||||
| 昭和十一年度末現在 | ||||||
| 和漢書 126,610部 330,775冊 | ||||||
| 洋 書 351,730部 546,353冊 | ||||||
| 而シテ必要カード数ハ本来部数ヲ基礎トシテ算定スベキナルモ,整理ニヨル部数ノ減少ト,参照用副カードノ増加トヲ相殺セバ寧ロ冊数ニ其3割5分ヲ加ヘタル数ヲ必要カード数ト算定スル方実際ニ近キガ如シ。此算定ニヨレバ必要カード数ハ | ||||||
| 洋書カード 737,577枚 和漢書カード 446,141枚 | ||||||
| トナル。 | ||||||
| 謄写ハ和漢書カードハペン書筆写ニヨリ,洋書カードハタイプライターニヨル。 謄写能力ハ各帝国大学図書館報告1日1人ノ謄写数ヲ平均シ之ヲ基礎トシテ予定ヲ立ツル事左ノ如シ。 |
||||||
| 和漢書カード謄写1人1日95枚 | ||||||
| 1年(勤務日数278日)26,410枚 | ||||||
| 1カ年必要延人員17人 | ||||||
| 洋書カード謄写1人1日175枚 | ||||||
| 1年(勤務日数278日)48,650枚 | ||||||
| 1カ年必要延人員16人 | ||||||
| 和漢書,洋書共各々3カ年継続事業トシ一般ニ図書購入ニ時日ヲ要スル洋書ノ目録ヲ先ニ着手シ,和漢書ヲ後ニス。 | ||||||
| 臨時費 | ||||||
| 閲覧室用総合目録作製費 | ||||||
| 昭和13年度ヨリ18年度ニ至ル6カ年継続事業費総額34,635円ナリ。 | ||||||
| 初年度8,445円ノ内訳 | ||||||
| 雇(謄写) | 6名, 年420円 | 2,520円 | ||||
| 嘱託(検査,分類) | 4名, 年600円 | 2,400円 | ||||
| カード30万枚 | 1万枚ニ付30円 | 900円 | ||||
| カード箱15箱 | 1箱ニ付35円 | 525円 | ||||
| タイプライター4台 | 1台ニ付450円 | 1,800円 | ||||
| 消 耗 品 | 300円 | |||||
| (第2年度以下略) | ||||||
閲覧用カード目録のうち和漢書カード目録は書名主記入で,五十音順に排列せられていたが,昭和27年に標記を訓令式ローマ字に改め,ABC順配列として現在にいたっている。
2 辞書体目録への動き
本館において辞書体目録の必要が称えられたのは,昭和16年5月起案の17年度概算要求に始まる。その一節に
| (イ)カード目録の整備………サレバ和漢書ニアリテモ著者目録ヲ具備シ,書名目録ト件名目録トヲ作製シ,更ニ此等ヲ綜合スル辞書体目録ノ完成ニ至リテ,始メテ運用ノ万全ヲ期シ得ベキモノトス。凡ソ図書目録ノ技術ハ複雑多岐,知識アル熟練者ヲ要シ,設備モ亦コレニ伴フヲ要ス。 |
| 辞書体カード目録ノ編成整備 | |||
| 図書館ニ於ケル図書ト図書カード目録トハ霊肉不離ノ関係アル事ハ周知ノ事実ナリ。図書カード目録ノ整備ナキ図書館ハ魂ノ入ラザル人間ニモ比スベキカ。図書カード目録ノ完備トハ即チ辞書体カード目録ノ編成整備ナリ。書名カード目録,著者名カード目録,及ビ題目ニヨル件名カード目録,以上3種類ノ目録ヲ完備セシメ,更ニコレヲ例ヘバ五十音順ノ検索名ニヨリテ検出シ得ル如ク編成シタルモノ之ヲ辞書体カード目録トス。………今辞書体カード目録ノ整備アリトセバ新規購入,寄贈ノ図書モ収蔵ト同時ニ時々刻々健全溌剌タル活動ヲ持続スル事ヲ得ム。米国大学図書館ハスベテ辞書体カードヲ完備ス。大東亜戦争ハ文化戦ナリ。文化戦ノ根柢ハ図書ノ敏活溌剌タル利用ナリ。今日ナサザレバ何時ノ日カ成スベケンノ勇猛心ヲ以テコノ目録ノ編成整備ニヨル根本的刷新ヲ企画セムトス。即チ今マヅ第1期計画トシテ左ノ経費ヲ計上ス。 | |||
| 人件費 司書4,嘱託2,雇員6 | 9,120円 | ||
| 備品費 机,椅子其他 | 4,320円 | ||
| 耗消品費 | 2,970円 | ||
| 計 | 16,410円 | ||
| カード目録改善整備(10年計画)に要する経費理由書 | ||
| 図書館のカード目録の編成は極めて不備で和漢書は書名目録,洋書は著者目録で,各一種を備えるのみで分類目録は図書館所蔵図書のみのものがあるだけである。しかも閲覧用カード目録は昭和12年以後のものを和漢書は書名目録,洋書は著者目録を備えるのみである。全学を統一する分類目録は1枚もない。目録の完備しない図書館がその存在の意義を失うこと多大である。しかも今日までこの状態が放置されたことは尨大な蔵書に対して早急に目録を整備することが殆んど不可能に等しい事情にあると同時に,殆んど累年要求するカード目録改善のために要する概算要求が全然無視されて来た実情にも依るものである。目録の編成は多数の人員と長年月と多額の経費を必要とする。図書館に整備すべきカード目録は著者目録,書名目録,分類目録,件名目録及辞書体目録の5種のカード目録である。 しかし著者目録を基本カードとして和漢書はカード18枚,洋書は17枚の謄写複製をなし,謄写されたカードにつき他の各種カードにそれぞれ必要な標目記入をなして,それを所定の規凖によって編成すれば他の4種のカードは容易に作製することが出来る。 但しその標目記入及編成にはそれぞれ専門技術者を要することは言うまでもない。しかし5種のカードを各種毎に新規に作製することは閑人の愚とすべきである。従って一種の基本カードを作製する以上は直ちにこれを謄写複製する簡単な操作を経て他の4種のカードを作製すべきことは常識の問題である。 本学蔵書157万冊余につき和漢書の既製書名目録,洋書の既製著者目録を原稿として作製すべき基本カード枚数は概算で和漢書は90万枚,洋書は70万枚,計160万枚,従ってこの基本カード1枚につき和漢書18枚,洋書は17枚を要するので,所要カード枚数は和漢書1620万枚,洋書1190万枚である。基本カード160万枚を作製するには1年16万枚を処理すれば10年を要し,1年16万枚を作製するには1人1日40枚の能率にて1年を250日とすれば1人1万枚,1年16万枚の作製にはこの能率にて16人を要することになる。1人1日40枚とするはカード記入作製及謄写複製を含めるもので最高能率と見做すべきであり,所要カード枚数は最低概算である。 この数字の示す通り現下極めて困難な事業ではあるが,これをいつまでも放置していては百年河清をまつに等しく附属図書館の最も重要な事業としてここに概算を要求する。 |
||
| 所要人員 | ||
| 基本著者カード作製 | 16人 | |
| 書名カード編成 | 2人 | |
| 分類カード編成 | 4人 | |
| 件名カード編成 | 4人 | |
| 辞書体カード編成 | 4人 | |
| 計 | 30人 | |
| 和漢書 | 洋書 | |||||
| 事務用 | 閲覧用 | 部局用 | 事務用 | 閲覧用 | 部局用 | |
| 著者目録 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 書名目録 | 1 | 1 | 1 | |||
| 分類目録 | 2 | 2 | ||||
| 件名目録 | 3 | 3 | ||||
| 辞書体目録 | 6 | 6 | ||||
| 計 | 2 | 14 | 2 | 1 | 14 | 2 |
| 総計 | 18 | 17 | ||||
しかし辞書体目録への動きも,その計画があまりにもぼう大であったため実現せず,今日にいたっている。
本館では和漢書の著者名カードは作られていなかったが,戦後いよいよその必要を感じてきた。また一般に書名主記入よりも著者主記入が重視される気運となったので,本館も昭和23年度より著者主記入に切り替え,しかも標凖型カードを採用した。これが本館における和漢書著者名カードの起源である。しかしこれは昭和23年度以降に限られているから,和漢書についてはなお過去50年間が欠けることになる。そこで昭和24年度の概算要求に,次の和漢書著者名カード目録作製費が出されたが,実現せず,現在依然として昭和23年度以前にはさかのぼることができない。
昭和24年度概算要求
1. 和漢書著者名カード目録作製費
近来和漢書目録は著者名で採ることが通念になって居るが,本学附属図書館では書名カード1種類を備えて居るに過ぎない。而も索引の大抵は著者名からするものである。書名カードでは著者名による索引は出来ない。著者名カードは書名カードに比べて2倍乃至3倍のカード枚数を要するが,索引上の便宜から言へば書名カードに優ること数倍に値するものである。他の国立大学附属図書館ではすべて著者名カード目録を採用している。本学附属図書館が今に至って著者名カードを採用することは至難な大事業であるが,図書館本来の任務として完逐しなければならない事業であるので,ここに万難を排して新規企画を敢てするものである。
現在の書名カード枚数は約45万枚と推定される。著者名カードにすればその約2倍と見て作製すべき著者名カード所要枚数は約90万枚であるとし,この目録作製に要する人員は1人1日50枚,1年200日と見て年1万枚の能率となるるので,90万枚を1年で作製するには1日当り90人,5年で18人,10年で9人,15年で6人となる。これに要するカード及カード函も整備して行かなければならない。この種の事業としては出来る限り短年月に完成することが望ましいので,ここには5カ年事業として所要費を計上した。
人件費 425,682円 事務官 3級 3人 雇員 15人
備品費 258,000円 机,椅子 各18個
消耗品費 180,000円 カード 180,000枚
しかし一方50年来継続してきた事務用書名カードが中断されて不便を感ずる声が起り,翌年より再び著者名カードから書名カードを謄写して,事務用書名カードを作製することになり,事務用カードは連綿として60年の歴史を保有することになった。この時から和漢書には著者カード(大),書名カード(大,小)の三種類が作られることになった。
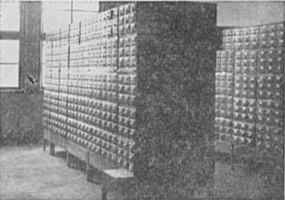 |
|
全学綜合目録(事務用)
|
和漢書におけるこのカード作製手続は昭和28年まで続いたが,いちいち謄写することの非能率性を解消して,同年4月より,ユニツトカード制を採用することになった。すなわち目録掛は小形書名カードを原稿として作り,謄写掛はこれを著者主記入に直してカード印刷原紙を作るのである。この流れ作業はかなり能率をあげたが,なお難点は残った。それは書名主記入カードから著者主記入に直すに当り,すべてが著者主記入に変更できないからである。依然として書名主記入であるものもあり,また複雑な図書では著者性の決定に迷うものがあるから必ずしも機械的にスムースには作られない。同一図書がある時は書名主記入であったり,ある時は著者主記入であったり,不統一が生ずるのである。
昭和32年頃から館界の一部に記述分離独立の説が起り,その能率性が認められるにおよび,本館でも旧の如く書名主記入カードをユニツトカードに採用することにして,著者名はローマ字で標記する方針に変更した。これで能率はすこぶる上ってきた。
昭和33年4月より学内の希望部局へ本館のユニツトカードを配給する事業が始められた。目録作業を2ヵ所以上で行うことの不合理性を除去し,部局図書掛の事務量を軽減するためである。この主旨に賛成して,工学部の大部分の教室,理学部の2,3の教室,その他研究所がユニツトカードの配給を受けている。なお中央図書室のある医学部,農学部,教育学部,教養部の4部局に対しては本館で作ったユニツトカードの印刷原紙を渡し,部局で必要枚数を印刷して部局用とし,本館にも所要枚数を送付する方法をとっている。
他方,法学部図書室は創設以来独立の形をとり,本館より司書を派遣して,図書整理は法学部図書室で行っている。経済学部も同様である,従って本館では両学部の図書のカードは作らず学部図書室で作製した事務用及び閲覧用カードが本館に送付されている。さらに昭和34年度より文学部も独立して整理を行い,閲覧用カードだけを本館に送付している。
函架目録は初期以来カード型式を採用し,1枚のカードに5件記入している。まず分類綱目順に配列し,同一綱目中では和漢書は標目(書名)の五十音順,洋書は標目(著者名)のABC順にならべ,その中では到着順に記入して図書記号を決定する仕方である。
和漢書においては現在もなお明治時代記入のものに書き足しているが,洋書では昭和11年に閲覧用カード復旧の際,同時に函架目録をも更新して,1件1枚のカードをもちいて新しく作製し直した。この様式は分類変更や書庫点検には極めて便利であるが,カードの枚数が以前の6倍となり,従ってカード箱の容積が6倍になった。
目録規則に関しては,洋書部では初期の頃は Cutter の Rules for aDictionary Catalog. 1876. や,Dewey の Library
School Rules. 1898. に従い,後には A.L.A, の Catalog Rules. 1908. に従ったが,和漢書部では初期以来「日本文庫協会編和漢書目録編纂規則 1983.」を使用していた。これは書名主記入を標榜していたから,本館の事務用カード作製には十分役に立つものであるが,記入が複雑化してくると,改正の必要が起ってきた。
大正期に入ると和漢書にも著者主記入を採用する傾向が一般的になり,このための和漢書目録規則を制定する必要が叫ばれて来た。帝大図書館協議会においても昭和3年頃よりこの問題が議題として提出され,東北大の田中敬が主査となってその起草を始めた。各帝大図書館よりも委員を出して協議研究し,ついに昭和7年に一応その規則が完成した。
しかるに一度完成したかに見えたこの和漢書目録規則は,なお細部に不備があって,その後毎年協議会の議題に上り,昭和12年第14次協議会にも「図書目録規則ニ関シ特ニ委員会ヲ常置スルノ件,コノ委員会ハ次ノ事項ヲ考究スルモノトス。(1)第13次協議会ニ提出サレタル和漢書目録規則,(2)洋書目録規則制定,(3)洋書目録規則ト和漢書目録規則トノ統一」を決議して,この統一目録規則制定の前途はいよいよ多難を思わせるものがあった。
昭和14年第16次協議会で市河委員長は「和漢書目録規則常置委員会ハ過去一カ年間相当ニ努力シ研究シテ来タガ今日ニイタルマデ未ダ成案ヲ得ルニイタラナイ。尚コノママ存続シテ行キタイト思フ。成ベク近イ中ニ成案ヲ得タイト考ヘル」と述べ,さらに昭和17年第19次協議会では「和漢書目録規則案第一編ハ一昨日ノ夜,目録小委員会ノ審議ヲ経タ後昨日目録委員会ニ於テ多少ノ修正ヲ見テ成立シタ。成立シタノハ第一編ダケデ,第二編以下ハマダ残サレテイルカラ規則トシテハ不充分デアルガ,コレダケデモ相当ニ役立ツト思イ,私トシテハ欣快ニ存ズル次第デアル」と述べている。
この目録規則は翌昭和18年2月号の図書館雑誌に「帝国大学附属図書館協議会制定和漢書目録規則第一編」と題して発表され,その抜刷は各館に配布された。
一方昭和初年頃より結成された「青年図書館員聯盟」においても,和漢洋に通ずる目録規則の編纂を企て,新進気鋭のひとびとの研究協議の結果,昭和19年にはその完成を見て「日本目録規則」と題して発表された。
このように目録規則には日本図書館協会案と帝大図書館協議会案と青年図書館員聯盟案の三種類が存立することになった。いずれも根本においては一致していても,枝葉においては差違のあることは免れない。昭和27年に日本図書館協会が主導して,「日本目録規則」(NCR)を制定したことは慶賀すべきことである。
本館においてもこのNCRを参考としているが,なお細かい点例えばローマ字飜字法等には,本館独特の内規を研究協議中である。
米国議院図書館カード目録は本館の誇りとするものの一つであるが,それが本館に寄託されるに至った経緯は,大正4年の学友会誌第13号に次の通り出ている。
寄贈に至る迄の経過 明治42年12月本学前総長理学博士男爵菊池大麓氏日米交換教授として官命により北米合衆国に差遣せらるるや,講演の余暇,議院図書館を視察し同館発行の牌紙形印刷図書目録が世界有数の完全なるものにして学術研鑽上,図書館経営上莫大の裨益あるにも拘らず我国公私の図書館中一も之が備付なきを遺憾とし同館長パツトナム氏に謀り,本邦にも試験的に2部の配付を受け,其1部を本大学附属図書館に,他を適当の個所に備付けんと欲し,翌43年4月帰朝の後該件に就き文部省専門学務局に禀請せり。而して専門学務局より外務大臣官房記録課図書部に移牒し,議院図書館並に華盛頓府斯密遜館万国図書交換局と数度の交渉を経,先づ1部のみ本大学附属図書館に寄贈を受くべき約束成り,44年7月斯密遜館より既刊の分及び向後刊行の分無償配付を受くに至れり。
かくて明治44年7月に本館に到着した第1回分のカードは,10年間分約40万枚でこれの排列整理は直ちに着手せられ,大正2年には過半の整理を終ったようである。大正2年の学友会誌第8号は次のように記述している。
北米合衆国議院図書館寄贈の同館所蔵図書牌子形印刷目録の整理は其後漸次進捗し, 第1回に受領したる40余万枚の牌子に対する第一歩の整理即ち分類別は係員多大の努力に依り,分明せる部分の分類を了り,今や第二歩の整理即ち著者名順排列に着手するに至れり,然れども同目録は引続き印刷すべき性質のものなるを以て整理上段落の劃すべき期なく,現にスミソニアン,インスチチューシヤン万国図書交換局経由の交換寄贈図書着荷の都度,更に新刷の分は続々として到来し,大小数十箇の梱包は事務室の一隅に堆うして,整理の前途の甚容易ならざるを思はしむ。さり乍ら一朝之が整理成り,予定に随って之を本館裡閲覧室内に備付け,将に新調せむとする牌子函に納め主として本学教官及び本館職員等の図書購入或は分類の参考に供し,更に進んで篤志家の需要に応じて之を公開するに至る時は我学界の進運に裨益すること尠からざるべし。
さらに大正4年の学友会誌第13号には
本大学附属図書館に既着の議院図書館牌紙形印刷図書目録は大約70万にして,尚今 後毎年発行の分凡5万枚は続続来着すべき筈なり。是等の目録は印刷順に梱包として送付せられ,毫も整理の手を経たるものにあらず。本館は去る45年7月以来専任係員1名を置き,他は館員業務の余暇交互整理に従事せしめつつあり。完成の暁には本館教官閲覧室に備付け,本大学教官は勿論,篤志家にして相当の手続を経たるものには公開せらるる予定なれば我国読者界の指鍼として学界の進運に貢献すること蓋し尠少にあらざるべし。
このようにしてL.C.カードは着々整理せられ,大正8年までは全部分類別著者名順として,約90万枚が排列されていたが,大正11年の概算要求説明にある如く,大正8年度を以てカード排列作業は一時中止の止むなきに至った。以後昭和13年に再開されるまで約20年間は未整理のまま堆積せられていた。
米国議院図書館ヨリノ寄贈カード目録整理事務ニ付テハ大正7年マデハ臨時費ヲ以テ支弁整理ヲナシ来リシモ大正8年度以降ハ経費不足ノタメ整理事務ヲ中止スルノ止ムナキニ至レリ。然ルニ該カード目録ハ年々約4万枚ヲ寄贈シ来ルモ,之レヲ堆積シタルママ整理シ能ハザルハ甚ダ遺憾トスル所ナリ。此ノカード目録ハ将来ト雖モ寄贈セラルベキモノニシテ常務トシテ之ガ整理ヲナサザルベカラザルモノニシテ本費ノ増額ヲ要求シ,嘱託員2人増員ノ上整理セントス。(大正11年度概算要求説明)
昭和13年に至り,次の概算要求が認められて,その整理事業は再開せられるに至った。
米国議院図書館カード目録整理費
議院図書館ノ如ク欧米其ノ他ノ有ユル図書ヲ蒐集シツツアル世界的大図書館ノ目録ヲ参照スル事ハ図書目録ノ作製,分類,整理上多大ノ利便アリテ,単ニ図書館ノミナラズ,教室及研究者側ニ於テモ之ニヨリテ利スルトコロ少カラズ。幸ニシテ本館ハ明治ノ末年ヨリ同カード目録ノ寄贈ヲ受ケ,大正6年頃迄其ノ整理ヲ継続セシガ,其後整理ノ事ハ絶エタルモ寄贈ハ継続シ,昭和5年以後ハ寄贈止ミシヲ以テ年々約百円ヲ支払ヒテ其供給ヲ受ケ,以テ今日ニ至レリ。本邦ニテハ唯ダ東大図書館ノミ整理利用シツツアリテ,本館ニ於テモ予テヨリ其必要ヲ痛感シナガラ財源ナキヲ以テ未整理ノママ今日ニ至レリト雖,新館ノ竣成モ3年ノ後ニ迫リテ本館ノ利用モ益々増進セントスル秋ニ当リ今日其整理ニ着手セザレバ悔ヲ後日ニ残サントス。
而シテ其カードノ増加ハ年々約5万枚ニシテ過去20年間未整理ノ分ヲ合スレバ100万枚ニ達スベシト雖,差シ当リ利用ノ多キ現在ノカードヨリ着手シテ未来ニ整理ヲ継続スルト同時ニ他方過去ニ溯ラントス。
計画案
1人1日整理数450枚 1ケ年125,100枚 100万枚ノ整理ニハ1ケ年8人ナリ,コレヲ2ケ年計画ニヨリテ次ノ如ク要求ス。
| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|
臨時部、L.C.カード目録整理費 |
2,400円 | 嘱託4名、年600円宛 |
そこで臨時雇員4名を以て,未整理の100万枚のカード整理に突進した。この際は前回の分類排列を採らず,新たに著者名順排列の新規方針に従って整理を始めた。時により5名で従事したこともあって,昭和18年頃には2名に減少していたが,昭和16年初冬太平洋戦争の勃発により,カードの輸入途絶し,手持ちの約100万枚のカードは全部整理し終った。戦後,国際図書交換の再開に伴い,昭和24年に,これまで保留されていたカードがふたたび続々到着して来たので,新たにその整理の必要が生じて来たが,まだその整理事業再開の曙光が見えないのは残念である。
昭和15年11月京都大学において開催された第17次九帝国大学附属図書館協議会の館長懇談会の席上で,大阪帝大より協議題「現時科学振興の要望せらるるに際し帝大図書館として之れに対する協同策を講ずるの要なきや」が提出された。これにつき意見を交換し,その方法として全帝大図書綜合目録の編纂が取上げられ,直ちに立案に移り,各大学図書館にその主旨を撤底さすと共に,事業計画への具体的資料の提出回答を求めた。越えて昭和16年3月事業計画案ができたので,東大図書館長に意見を求めた。
まず最初「帝国大学綜合図書目録編纂刊行事業綱要」として立案されたが,これでは採録範囲が狭く,従って利用価値少く,文部省や大蔵省の了解も得難いことを察して,次に採録範囲を国立私立の大学,公共図書館,研究所,会社資料室等に迄拡張参加せしめる方針の下に立案したのが「日本綜合図書目録編纂刊行事業綱要」であって次の通りである。
| 日本綜合図書目録編纂刊行事業綱要(第1回案) | |||
| 1.日本綜合図書目録ハ内地及ビ外地ニ在ル九帝国大学所蔵ノ和漢洋図書ノ綜合目録ヲ編纂シテ刊行スルモノトス 但シ宮内省図書寮,帝国図書館其他内外地主要図書館研究所等ノ参加ヲ拒ムモノニアラズ | |||
| 2.日本綜合図書目録(以下本目録ト称ス)ハ和漢書及び洋書ノ2部ニ分チ逐次刊行書(主トシテ雑誌)ヲ除ク | |||
| 3.本目録ノ編纂刊行ハ10年間ノ継続事業トシ,現在所蔵シ及ビ将来7箇年間ニ所蔵セラルベキ図書ヲ網羅ス | |||
| 4.本目録ハ和漢書ニアリテハ書名標目記入トシ,洋書ニアリテハ著者標目記入トス | |||
| 5.本目録ノ編纂刊行ハ能フ限リ敏速ヲ期シ現下ノ要求ニ応ゼントス | |||
| 基 本 調 査 | |||
| 1.九帝国大学所蔵図書総数ヲ5,000,000冊トス | |||
| 2.九帝国大学ニ於ケル1年増加図書冊数ヲ200,000冊ト推定ス | |||
| 3.上記ノ所蔵図書及ビ増加図書ヨリ重複図書ヲ除キ,実際ニ本目録ニ収録スベキモノハ総数ノ100分ノ16トス,即チ所蔵図書ニアリテハ800,000記入冊数,増加図書ニアリテハ32,000記入冊数ト算定ス | |||
| 事 業 ノ 進 行 | |||
| 1.九帝国大学附属図書館ハ事業第1年度ニ於テ其所蔵図書冊数及ビ1年間ノ増加図書概数(前5年間増加図書冊数ノ平均)ヲ本目録編纂部(仮称)ニ報告スルモノトス | |||
| 2.本目録ノ基本カード目録ハ所蔵図書ニアリテハ第1年度ヨリ第5年度マデニ,毎年1,000,000枚ヲ,増加図書ニアリテハ其年度ノモノヲ(推定200,000枚)調製スルモノトス | |||
| 3.各帝国大学附属図書館ハ第1年度ヨリ第5年度マデニ毎年其所蔵図書ノ5分1ヲ下ラザル基本カード目録ヲ,又第1年度ヨリ第7年度マデニ毎年増加図書ノ基本カード目録ヲ調製シ,3個月毎ニコレヲ本目録編纂部ニ送致スルモノトス | |||
| 4.本目録編纂部ハ左ノ基本カード目録ヲ整理シ,印刷目録原稿ヲ作製シ第1年度中ニハ所蔵図書目録第1冊ノ刊行ヲ期スルモノトス | |||
| 基本カード目録調製費 | |||
| 1.基本カード目録調製費ハ100枚ニ付キ3円ト算定ス | |||
| 5,000,000枚 | 150,000円(所蔵図書) | ||
| 1,400,000枚 | 42,000円(増加図書) | ||
| 計 6,400,000枚 | 192,000円 | ||
| 2.基本カード目録調製費ハ各帝国大学ノ所蔵図書及ビ増加図書ノ数ニ応ジテ之ヲ配当ス | |||
| 3.他ノ研究所図書館等ノ参加シタル場合モコレニ凖ズ,以下コレニ随フ | |||
| 目 録 印 刷 費 | |||
| 1.印刷目録ニ収容スベキ記入冊数ハ1頁ニ付キ20ト算定ス | |||
| 2.所蔵図書ノ記入冊数800,000ニ対スル印刷目録ノ頁数ハ40,000, | |||
| 増加図書ノ記入冊数23,000ニ対スル印刷目録ノ頁数ハ1,600(1年分), | |||
| 7箇年分合計11,200頁,総計51,200頁トス | |||
| 3.印刷目録ノ組版代,紙代,印刷費,表紙代,製本代(仮綴)ヲ合シ印刷目録1頁ヲ20円ト算定ス,1冊500頁,103冊 | |||
| 4.印刷所要費(仮製本代ヲ含ム)所蔵図書800,000円,増加図書224,000円,合計1,024,000円トス | |||
| 基本カード目録整理並印刷原稿作製 | |||
| 1.備品器具 カード箱 70抽出附 | |||
| 1組単価550円 | 90組 49,500円 | ||
| 机及椅子 | 22組 2,200円 | ||
| カード仕分器 | 5個 100円 | ||
| 欧文タイプライター | 5台 5,000円 | ||
| 2.印刷原稿作製費 100枚ニ付キ3円ト算定ス | |||
| イ.所蔵図書 800,000記入冊数 24,000円 | |||
| ロ.増加図書 224,000記入冊数 6,720円 | |||
| 計 30,720円 | |||
| 3.編纂部人件費 | |||
| 主 任 | 2 年俸2,510円 | 50,200円 | |
| 編纂員 | 10 985円 | 98,500円 | |
| 嘱 託 | 10 月俸 70円 | 84,000円 | |
| 給 与 | 4,600円 | 46,000円 | |
| 計 | 27,870円 | 272,870円 | |
| 4.通信,運搬雑費 | 17,780円 | ||
| 総 計 | 1,600,000円 | ||
| 頒 布 方 法 | |||
| 1.本目録ハ1,000部ヲ印刷スルモノトス | |||
| 2.各帝国大学ハ其学部数ノ3倍ニ相当スル本目録部数ヲ無償ニテ取得スルモノトス | |||
| 3.各帝国大学ハ其教室,研究所ノ数ヲ超エザル本目録部数ヲ印刷実費ノ8割ヲ以テ買上グルヲ得ルモノトス | |||
| 4.他ノ学術団体ハ一部ヲ限リ本目録ヲ実費ニテ買上グルヲ得ルモノトス | |||
| 5.私人ハ前3項ヲ控除シテ余裕アル場合ニハ印刷実費ノ12割ヲ以テ買取ルヲ得 | |||
| 6.右ニヨリテ得ル収入ヲ400,000円ト算定ス | |||
| 本目録編纂部機構 | |||
| 1.本目録編纂部ヲ2乃至4帝国大学内ニ置ク | |||
| 2.本目録編纂所ニ左ノ職員ヲ置ク | |||
| イ.司書官 2名 附属図書館長監督ノ下ニ編纂部ノ事務ヲ掌理ス | |||
| ロ.司 書 10名 (1名ヲ書記トスルコトヲ得)上官ノ命ヲ承ケ日本綜合図書目録ノ事務ニ従事ス | |||
|
ハ.嘱 託 10名 |
|||
以上は本館作製の試案であるが,同年5月18,19日東大図書館において目録編纂協議会が開かれ,京大試案を修正して次の如く発表された。
昭和16年6月7日記
| 1 甲案 | |||
| 帝国大学綜合目録編纂刊行事業綱要 | |||
| (本協議会に於て検討修正を加へたるものを本館に於て計数を調製し且つ年次計画表を添へたるもの) | |||
| 2 乙案 | |||
| 日本綜合図書目録編纂刊行事業概要 | |||
| (文部省専門学務局長の意見に基き甲案を参考として本館に於て作製せるもの) | |||
| 1.日本綜合図書目録(以下本目録ト称ス)ハ日本内外地大学及大図書館(別表参照)所蔵ノ和漢洋書(逐次刊行物ヲ除ク)ヲ綜合採録シタル書冊型目録ニシテ各所蔵者相互ノ図書貸借ニ資シテ現下ノ要求ニ応ズルト共ニ日本現在書目録タラシメントスルモノナリ | |||
| 2.本目録ハ和漢書及洋書ノ2部ニ分ツ | |||
| 3.本目録ノ編纂刊行ハ10年間ノ継続事業トシ着手ノ前年度末ニ所蔵シ及其後5年乃至9年間ニ所蔵セラルベキ図書ヲ網羅ス | |||
| 4.本目録ハ著者標目記入トス | |||
|
基 本 調 査 |
|||
| 1.各館所蔵図書数 | |||
| 和漢書 6,900,000冊 | |||
| 洋 書 4,344,000冊 | |||
| 計 10,434,000冊ト推定ス | |||
| 2.各館ニ於ケル増加図書冊数 | |||
| 和漢書 9ケ年分 1,530,000冊 | |||
| 洋 書 5ケ年分 650,000冊 | |||
| 計 2,180,000冊 | |||
| 3.冊数ト部数ノ割合ヲ次ノ如ク算定ス | |||
| 和漢書 1部 2.5冊 | |||
| 洋 書 1部 1.5冊 | |||
| 上記ノ比率ニヨリ冊数ヲ部数ニ換算スレバ | |||
| 和漢書 2,436,000部 | |||
| 洋 書 2,896,000部 | |||
| 増加図書ニアリテハ | |||
| 和漢書 612,000部 | |||
| 洋 書 260,000部 | |||
| 計 和漢書 3,048,000部 | |||
| 洋 書 3,156,000部 トナル | |||
| 4.上記ノ所蔵図書及増加図書ヨリ重複図書ヲ除キ実際ニ収録スベキモノハ総数ノ100分ノ50ト算定ス 即チ | |||
| 和漢書 1,524,000記入部数 | |||
| 洋 書 1,578,000記入部数 | |||
| 合 計 3,102,000記入部数トナル | |||
| 事 業 進 行 | |||
| 1.各館ハ事業第1年度ニ於テ其所蔵冊数及1年間ノ増加図書概数(前5年間ノ増加図書冊数ノ平均)ヲ本目録編纂部ニ報告スルモノトス | |||
| 2.本目録ハ洋書ヨリ着手シ別紙年次計画ニヨル | |||
|
3.本目録編纂部ハ各館ヨリ送附シ来レル基本カードヲ整理シ印刷用原稿ヲ作製スルモノトス |
|||
| 基本カード調製費 | |||
| 1.基本カード調製費ハ100枚ニ付5円ト算定ス | |||
| 10,434,000枚 521,700円(所蔵図書ノ分) | |||
| 2,180,000枚 109,000円(増加図書ノ分) | |||
| 計 630,700円 | |||
| 2.基本カード目録調製費ハ各館ノ所蔵図書及増加図書ノ数ニ応ジテ之ヲ配当スルモノトス | |||
| 目 録 印 刷 費 | |||
| 1.印刷目録ニ収容スベキ記入部数ハ菊倍判1頁ニ付25ト算定シ1冊約500頁トス | |||
| 和漢書 1,524,000記入部数 60,960頁 122冊 | |||
| 洋 書 1,578,000記入部数 63,120頁 127冊 | |||
| 計 3,102,000記入部数 124,080頁 249冊 | |||
| 2.印刷目録ノ組版代,紙代,表紙代,製本代(仮綴)ヲ合シ印刷ヲ和漢書15円,洋書25円トス | |||
| 和漢書 60,960頁 914,400円 | |||
| 洋 書 63,120頁 1,578,000円 | |||
| 計 2,492,400円 | |||
| 基本カード整理並印刷原稿作製 | |||
| 1.備品器具 | |||
| イ.カード容器70抽出 1組 | 単価 550円 | 180組 99,000円 | |
| ロ.机及椅子 | 単価 100円 | 108組 10,800円 | |
| ハ.欧文タイプライター | 単価1,000円 | 20組 20,000円 | |
| ニ.邦文タイプライター | 単価 500円 | 5台 2,500円 | |
| ホ.雑品費 | 10,000円 | ||
| 計 | 142,300円 | ||
| 本目録編纂部ノ組織並経費 | |||
| 1.本目録ノ編纂部ヲ文部省ニ置ク | |||
| 2.本目録ノ編纂ニ要スル職員左ノ如シ | |||
| イ.司書官 4名 | 年俸 2,510円 賞与 251円 | 110,440円 | |
| 本目録編纂ノ事務ヲ掌理ス内1名ヲ主任トス | |||
| ロ.事務官 1名 | 年俸 2,510円 賞与 251円 | 27,610円 | |
| 主任ノ監督ノ下ニ庶務会計ヲ掌理ス | |||
| ハ.書 記 3名 | 俸給年額985円 賞与 98円 | 32,490円 | |
| 上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス | |||
| ニ.司 書 40名 | 俸給年額985円 賞与 98円 | 433,200円 | |
| 上官ノ命ヲ承ケ編纂ニ従事ス | |||
| ホ.嘱 託 50名 | 手当月額70円 | 420,000円 | |
| ヘ.傭 人 | |||
| 写字生 10名 | 年額 420円 | 42,000円 | |
| 給 仕 5名 | 〃 180円 | 9,000円 | |
| 小 使 5名 | 〃 380円 | 19,000円 | |
| ト.消耗品費 | 180,000円 | ||
| チ.通信運搬費 | 5,000円 | ||
| リ.内国旅費 | 10,000円 | ||
| 計 | 1,288,740円 | ||
| 経費総額 | 4,554,140円 | ||
収録予定図書館名
東京,京都,東北,九州,北海道,大阪,名古屋,京城,台北各帝国大学附属図書館内閣文庫,宮内省図書寮,帝国図書館
東京,広島両文理大附属図書館
東京,神戸,大阪各商大附属図書館
東京,旅順両工大附属図書館
東京,大阪両外語図書館
慶応,早稲田,明治,中央,同志社,竜谷大学附属図書館
航空研究所,理化学研究所両図書室
新潟,岡山,千葉,金沢,長崎,熊本,京都府立各医大図書館
満鉄東亜経済調査局其他各種会社資料室調査室
南方協会(台湾)資料室其他各種団体資料室
(なお同年11月12日次の図書館を追加報告している)
大谷大学,神宮皇学館,台湾総督府図書館,朝鮮総督府図書館,東亜研究所,国際文化振興会,国民精神文化研究所,日本貿易研究所,東洋文庫,静嘉堂文庫,岩崎文庫,天理図書館,上智大学,東方文化研究所
備考
1.第1年次前半ハ凖備期間トス
2.第5年次後半ヨリ和漢書ノ凖備開始
3.第6年次ヨリ着手スル和漢書ノ部基本カード所蔵図書中ニハ第1年次−5年次中ノ増加図書850,000冊ヲ含ム
4.洋書増加図書ハ第6年次ニ於テ和漢書増加図書中第6−9年ノ分ハ第10年次ニ於テ各一括印刷スルモノトス
5.備品費 カード容器ハ第1年次ニ於テ100組,第5年次ニ於テ80組購入 邦文タイプライターハ第1年次ニ於テ2台,第5年次ニ於テ3台購入
6.俸給第1年次ハ定員中司書官2人全年,1人半年,司書ハ30人,嘱託ハ30人トシ,第2年次以後全員充員,第4−7年次ニ於テ臨時嘱託10人宛増員ノ見込(第4−7年次ハ洋書ヨリ和漢書ヘノ経過期ニ当ルヲ以テ人員ノ移動多カルベシ)
以上の如く事業計画案はかなり具体的になってきたが,さらに,同年7月14,15日本館において開かれた和漢書目録法小委員会と並行して,綜合目録司書官打合会を開き,東京大学側委員(河合博)より,その後の文部省との交渉経過の報告として,時局下科学振興のため本省も大いに乗気になっている旨報告があり,次いで議事に入り,1.帝大綜目と日本綜目,2.著者名順,3.和洋別,4.目録法,5.採録範囲,6.予算と外地帝大,7.科学技術方面のみとして作る場合,8.編纂場所,9.係員の講習,10.用紙確保,11.印刷所の見通し,12.係員抜擢採用等の各項目について協議が行われ,具体化へ一歩前進した。さらに同年11月には次の文書となって,一層具体化への道を進んだ。
昭和16年11月5日
東北帝国大学附属図書館長 小宮豊隆
拝啓 愈々御清穆ノ段奉賀候
陳者第18次帝国大学附属図書館協議会館長懇談会ニ於テ東京帝国大学ヨリ提出相成リタル左記日本綜合図書目録編刊事業ニ関スル秘扱参考資料送附致候条御査収相成度此段及御通知候也 敬 具
記
1.日本綜合図書目録編刊事業ニ対スル文部省ニ於ケル予算要求概要並参考事項
1.科学課ヲ訪問シテ聴取シタル同課ノ意嚮
予算要求書抜抄
○科学振興等ニ関スル経費
日本綜合図書目録編纂刊行
内外図書文献入手困難ノ状況ニ鑑ミ国内所蔵ノ図書文献ヲ広ク調査整理シ之ガ綜合目録ヲ編纂刊行セントスルニヨリ左記経費ヲ要求ス
○実施要項
1.目録編纂本部ヲ専門学務局科学科内ニ,事務所ヲ適当ナル2,3ケ所ノ帝大附属図書館内ニ置ク
2.調査スベキ図書館研究所研究室ヲ選定ス
3.図書文献ノ分類項目ヲ決定ス
4.調査スベキ各館ヲシテ所蔵図書文献ノ冊数及1年間ニ増加スベキ冊数ヲ編纂本部ニ報告セシム
5.本部ヨリ各図書館ニ職員ヲ派遣シテ基本カード調製方法ヲ指導セシム
6.各図書館ハ一定様式ノ調査用基本カードヲ調製シ事務所ニ提出セシム
7.各事務所ハ各館ヨリ送附シ来ル基本カードヲ調査整理シ印刷用原稿ヲ作製ス
8.印刷ハ東京其他ノ大印刷所ニ於テス
9.最初5ケ年ヲ以テ洋書ヲ後5ケ年ヲ以テ和漢書ヲ調査編纂刊行ス
10.目録編纂ハ洋書和漢書共ニ時局下緊急ヲ要スルモノヨリ先ニス
11.目録ハ学問ノ系統的分類ニ則リ活用ニ便利ナル項目別ニ1冊トシ文献ノ配列ハ各冊共著者名アルフアベツト順ニ依ルモノトス
○職員配当表 ( )内ハ初年度
| 管掌事務 | 事務官 | 司書官 | 前 | 司書 | 嘱託 | 計 | ||
| 本 部 | 統轄並聯絡事務 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 第一地方事務所 | 単行書目録逐次刊行物 | 2(2) | 2 | 15(10) | 15(10) | 34 | ||
| 第二地方事務所 | 単行書目録 | 1 | 1 | 5(3) | 5(3) | 12 | ||
| 第三地方事務所 | 〃 | 1 | 1 | 5(3) | 5(3) | 12 | ||
| 計 | 1 | 4(2) | 5 | 25(16) | 25(16) | 60 | ||
| 1.帝大側立案トノ主ナル相違点 | |||
| 1.逐次刊行物ヲ加ヘタルコト | |||
| 2.項目別トシ時局下緊急ヲ要スル事項ヨリ着手スルコトトナシタルコト,尚項目別トナシタルタメ二項目以上ニ跨ルモノハ夫々ニ重出スル要アルヲ以テソノ為ノ重複割合ヲ全体ノ30%トシテ計算シタリ | |||
| 1.本省側ノ希望(帝大側ニ対シテ) | |||
| 1.事業開始前ニ講習会開催ノ要アルベク之ニ関スル具体的計画ヲ承リタシ | |||
| 2.分類項目決定ノ為ノ委員会等組織ノ必要アルベク之ニ関スル具体的計画ヲ承リタシ | |||
| 尚学問分類ノタメ科学課ニ於テ自然科学分類委員会ヲ設置シ近ク完成発表ノ予定ナルヲ以テ之ヲ参考トセラレタシ,人文科学ノ分類委員会モ設置ヲ考慮中ナリ | |||
| 3.本事業実施ニ関スル具体的計画ハ総テ帝大附属図書館側ニ期待シタルヲ以テ自主的態度ヲ以テ立案要請アランコトヲ希望ス | |||
| ○科学課ヲ訪問シテ聴取シタル同課ノ意嚮(文責筆記者ニアリ) | |||
| 経費概要 | |||
| 総 額 | |||
| 科学課立案当初要求額 6,394,847円 | |||
| 大蔵省ヘ提出ノ概算額 5,827,217円 | |||
| 昭和17年度要求額(9ケ月分) 121,991円 | |||
| 科学課ノ意気込 | |||
| 科学課トシテハ本事業ニ関シ先ニ帝大総長会議席上公約セル関係モアリ本事業予算ヲ優先的ニ通過セシムベク努力シツツアリ | |||
| 帝大側ニ対スル希望 | |||
| 帝大側トシテハ本事業ノ完成ハ邦家文運ノ昂隆上,又時局下緊急ノ要求ニ応ウルタメ最モ必要ナル所以ヲ強調スルト共ニソノ実施具体案ヲ用意シテ当局ヲ鞭撻スル態度ニ出ラレタシ 文部省ノ予算要求ニ便乗シテ事ヲ行フガ如キ印象ヲ大蔵省側ニ与ウル事ハ最モ不利ナリ予算ノ問題トハ別ニシテ大局的見地ヨリ本事業ノ緊急実施ノ要ヲ力説シテ輿論ノ喚起ト当局ヘノ要請鞭撻ヲ続ケラレタシ |
|||
| 「実施要項」ニツイテ | |||
| 主管課トシテハ予算要求書類ノ形式ヲ整ヘル為ニ「実施要項」ヲ一応作製セルモ予算通過ノ見通シツキタル後ニ於テハ更メテ実施具体計画立案ノ要アリ,之ハ現在ノ所帝大側ノ善処ニ期待シ居レリ | |||
| 全国図書館長会議 | |||
|
要求予算通過ノ見通シツキタル時期(11月中旬)ニ於テ本事業実施ノ凖備工作ノートシテ全国図書館長会議招集ノ用意アリ |
|||
以上は東大側委員が文部省科学課を訪問して,その意向を打診した結果の報告であるが,同年11月1日東北大学において開かれた帝大図書館協議会に引続き,綜目編刊委員会凖備打合会が持たれ,具体化へさらに一歩前進した。
| 日本綜合図書目録編刊委員会凖備打合会議事摘録 | ||
| 昭和16年11月1日午後 於東北帝国大学附属図書館 | ||
| 出席者 | ||
| 東京帝国大学司書官 水野 亮 | ||
| 京都帝国大学司書官 竹林 熊彦 | ||
| 九州帝国大学司書官 桜井 匡 | ||
| 名古屋帝国大学司書 半田 津 | ||
| 東北帝国大学司書官 重久篤太郎 | ||
| 議 事 | ||
| 第18次帝国大学附属図書館協議会ヲ機トシテ同協議会出席者中ノ日本綜合図書目録編刊委員(以下綜目委員ト略称)ガ参集シテ日本綜合図書目録(以下綜目ト略称)編刊事業実施ニ関シテ事務打合ヲナシ,左ノ意見ノ開陳ガアツタ。 | ||
| 1.日本綜目図書目録編刊委員会(以下綜目委員会ト略称)ニ関スル事務ハ暫定的ニ東北帝大ニ於テ引受ケルコト | ||
| 1.綜目委員ハ各帝大司書官(大阪,名古屋両帝大ハ適当ナル者)中ヨリ10名(東京帝大ハ2名,其他ノ各帝大ハ1名宛)ガ選出セラレルコトトナツタガ,本事業ハ文部省ノ企画でアルカラ綜目委員ハ正式ニ本省カラ任命セラレルヤウ科学課ニ交渉シタイ | ||
| 1.本省科学課ニ対シテ,本省ヨリ各帝大総長宛ニ綜目委員1名宛(東大ハ2)ノ選出方依頼ノ通牒ヲ出スヤウ取計ヒ方ヲ要請スルコト | ||
| 1.事務連絡上帝大側選出委員ノ他ニ本省側選出委員1名乃至2名ヲ加ヘルコト | ||
| 1.本省ノ綜目委員任命ガ遅延スルトキハ帝大図書館協議会選出ノ委員ガ暫定的ニ本事業計画ニ当ルコト | ||
| 1.本省科学課ニ対シテ本編刊事業ノ具体的実施計画ヲ立案スルタメ綜目委員打合会ヲ本年11月下旬又ハ来年1月ニ東京ニ於テ開催シ各帝大綜目委員ヲ参集セシメル方法ヲ講ズルヤウニ要請スルコト | ||
| 1.綜目委員ノ旅費ハ科学課ヨリ支弁スルコト,若シ不可能ノ場合ハ同課ニ於テ各帝大総長宛ニ帝大側ノ綜目委員派遣方ヲ申出ルヤウニ取計フコト | ||
| 1.以上ノ本省トノ事務的交渉ハ水野,重久両司書官ガ内交渉ヲナシタ上,帝大図書館協議会議長(小宮東北館長)ガ公文ニテ交渉ヲナスヤウニシタイ | ||
| 1.綜目委員打合会ニ於テハ本省側ノ実施要項ノ再検討ヲナスコト | ||
| 1.科学課案ハ逐次刊行物ヲ加ヘタモノデアルカラ編刊事業期間ノ2ケ年延長ト20パーセントノ費用増額ヲ要求スルコト | ||
このように大学側は非常な意気ごみを以て計画を立て,同年11月17日には過日東北大学で開かれた第18次帝大図書館協議会館長懇話会の申合せにより,綜目編刊委員として,本館は司書官竹林熊彦を選出し,各帝大もそれぞれ司書官を編刊委員に選出して,着々凖備はでき上りつつあったが,その後文部省と大蔵省との折衝の結果,太平洋戦争突入の時局下のため予算を認められず,計画も一時中止の止むなきに至った。
しかし翌昭和17年5月21・22日東大において,第1回日本綜合目録編刊委員会が開かれ,各帝大司書官によって,目録上の技術的細目について研究討議が行われた。その結果,「外国学術図書目録」として,外国文献に限定して綜合目録の編集を企て,18年度の予算折衝が行われたが,今回も実現しなかった。
昭和18年5月日本図書館協会総会開催を機とし,同総会出席の各帝大編刊委員は,5月22日東大図書館に集り懇談したが,その結果は次のように報告されている。
| 綜合図書目録編刊委員会 | |||
| 日時 5月22日午後2時−5時 | |||
| 場所 東京帝国大学附属図書館 | |||
| 出席者 | |||
| 北海道帝大 | 柴田司書官 | ||
| 東北帝大 | 重久司書官 | ||
| 東京帝大 | 市河 館長 | ||
| 同 | 水野司書官 | ||
| 同 | 中田司書官 | ||
| 名古屋帝大 | 三輪 館長 | ||
| 京都帝大 | 青山 司書 | ||
| 大阪帝大 | 田中 嘱託 | ||
| 九州帝大 | 桜井司書官 | ||
| 同 | 山崎 司書 | ||
| 当日文部省側より出席者はなかりしも中田司書官より文部省側意見として左の通り開陳ありたり | |||
| 1.文部省科学局に於ては自然科学(洋書)に関する綜合図書目録編刊の必要且つ緊急なるを認めその実現を期し19年度に於ても鋭意予算の通過を見る様努力する | |||
| 2.各帝大図書館に於て当然為すべき事業は各館に於てそれぞれ進渉されたきこと以上の意見に基き各自意見開陳懇談をなし左の如き申合をなせり | |||
| 申 合 | |||
|
綜合図書目録編刊委員会は今後文部省より何分の沙汰あるにあらざれば開催せず。但し文部省との交渉は東京帝大,通信事務は九州帝大これに任ずることとす。 |
|||
この昭和18年5月22日の打合会を最後として,日本綜合目録会議は当分の間開かれなかった。時あたかも太平洋戦争いよいよ熾烈となり,会議開催も不可能となった。
昭和20年8月,終戦を迎え,戦後の虚脱状態が続いている時,昭和21年7月には早くも文部省学術研究会議内に,学術文献調査研究特別委員会が設置され,本館沢潟館長は研究特別委員を委嘱され,本館には関西第一地方委員会が置かれた。
学術文献調査研究特別委員会はその最初の仕事として,医学書綜合目録を作製することになり,医科大学附属図書館協議会が作製中であった共同医学図書目録の完成を同会に委嘱した。
21年10月金沢医科大学で,第17回医科大学附属図書館協議会が開催されたが,その際共同医学図書目録編集の件が協議されることになり,本館から宮西司書官が出席した。その結果医学部所蔵の洋書目録を本館の事務用カード箱より選出してリストに作成し,翌22年3月に,それぞれ編集担当館(京府医大,金沢,千葉,東大,阪大,東北大,名大,新潟)へ送付した。これは戦後における学術文献調査特別委員会の発足第一の事業であった。
さらに昭和21年11月,京都大学において技術研究科会小委員会が開かれ,「外国学術雑誌焼失目録」作成の件が決定した。これは戦災による焼失雑誌を整理するためであった。本館は関西第一地方委員会として,次の文書で依頼した。
| 昭和21年11月 | ||
| 学術研究会議学術文献調査研究特別委員会関西第1地方委員会 | ||
| 委員 沢潟久孝 | ||
| 殿 | ||
| 学術文献調査研究特別委員会関西第1地方委員会設置並ニ「外国学術雑誌目録」ニ関スル焼失雑誌調査ノ件 | ||
| 文部省科学局ニヨリ昭和21年7月1日付ニテ学術研究会議内ニ学術文献調査特別委員会ガ設置発令サレ同時ニ京都帝国大学附属図書館ニ関西第1地方委員会ガ設置サレテ其担当区域ハ京都,滋賀,福井,石川,富山,岡山,広島,山口,鳥取,島根ノ10府県ト指定サレマシタ。同特別委員会ハ日本内ニ所在スル学術図書ノ綜合目録作製ヲ目的トスルモノデ同委員会ノ決議ニヨリ本年度中(昭和22年3月末日迄)ニ「外国学術雑誌目録」ニ関スル焼失雑誌目録及ビ医科大学所属欧文医学図書目録ヲ完成シ同時ニ自然科学及人文科学ノ和洋学術雑誌綜合目録作製ニ関スル凖備ヲナスコトニナリマシタ。就テハ関西第1地方委員会ハ担当地区ノ学校,図書館,研究所,会社等ニ所蔵スル図書ニ就キ所要ノ調査事項ヲ 京都帝国大学附属図書館ニ集結シテ整理スルコトニナツテ居リ目下緊急ヲ要スル事業ハ焼失雑誌目録デアリマス | ||
| 焼失雑誌目録作製ニ関スル要項 | ||
| 1.調査事項 | ||
| 学術研究会議編纂昭和8年末現在調査,昭和15年発行第3版訂正版「外国学術雑誌目録」ニ収録サレテ居ル雑誌ノ内,昭和21年3月末日現在ニテ焼失シテ居ル雑誌 | ||
| 2.調査方法 | ||
| (イ)焼失雑誌ハ「カード」ニ記載シ其他記載事項ハ「外国学術雑誌目録」ニ凖ジテ詳細ニ亘ルコト | ||
| (ロ)所要「カード」ハ京都帝国大学附属図書館ヨリ送付ス | ||
| 3.調査期限 | ||
| 「カード」ハ昭和22年1月20日迄ニ京都帝国大学附属図書館ニ到着スル様発送サレタキコト | ||
| 4.左記事項ニ就キ至急ニ遅クトモ昭和21年11月末日迄ニ京都帝国大学附属図書館宛御回答願ヒマス | ||
| (イ)焼失雑誌ノ有無 | ||
| (ロ)焼失雑誌記載ニ要スル「カード」ノ概数 | ||
以上の如く焼失雑誌調査依頼状を関西地区の各大学に送付して,学術文献調査研究特別委員会の戦後における発足第二の事業が開始された。本学はなんら戦災を受けなかったから,報告すべき該当事項はなかった。なお,関西第一地区(京都,滋賀,福井,石川,富山,岡山,広島,山口,鳥取,島根)の10府県より集まって来たカードは,本館経由で文部省へ転送した。
さらに同年3月19,20日東京上野の学士院で特別委員会が開かれ,今後の事業打合せのため宮西司書官が出席した。同年9月1,2日東京学士院において技術研究科会が開かれ,Union
Catalog およびその目録記入規則その他が協議されている。さらに10月23日には文部省科学資料課において特別委員会が開かれ,「マイクロフイルム地区活動」が附議せられた。マイクロフイルムは欧米ではすでに文献複写に利用せられていたが,わが国ではほとんど利用されていなかった。文献利用のためにはマイクロフイルムが極めて便利であることを認めて,文部省が大学図書館にその装置の設置方を勧奨した最初である。その後迂余曲折はあったが,とにかく現時の盛況を見せて,マイクロフイルムが学界に貢献しているのも,ここにその濫觴がある。
なお同委員会では,前回決定を見た「学術雑誌綜合目録記入要項」が配布せられ,いよいよこれに基いて22年3月末日現在で,学術雑誌綜合目録の原稿カードを作成することとなった。本館は欧文雑誌についてはすでに「欧文逐次刊行物目録」が完成していたから,比較的簡単にカードが作られたが,和文雑誌については最初からカード箱より摘出筆写しなければならないから,相当手数を要した。洋雑誌のカードは23年12月には完成し,和雑誌も24年3月には完成した。
欧文自然科学雑誌カード 11,959枚 (大阪大学ニ送付)
欧文人文科学雑誌カード 6,790枚 (東京大学ニ送付)
和文自然科学雑誌カード 2,919枚 (京都大学ニ保管)
和文人文科学雑誌カード 3,884枚 (東北大学ニ送付)
本館で作成したカードは以上の通りであった。この4部に分けてそれぞれの館でマスターカードに編成する仕事が残っている。本館は自然科学の和文カードをマスターカードに編成するため,さらにこの事業が継続した。
24年10月26,28日に本館で第5回綜合目録協議会が持たれ,その席上次の通り報告があった。
和文自然科学雑誌カード(京大に集結)
東大より 3,756枚 (名大および東北大を含む)
九大 2,421枚
北大 3,561枚
阪大 1,288枚
京大 2,919枚
計 13,945枚 (4,796種)
この自然科学和文雑誌のカード13,945枚について,4,796種のマスターカードを作成する仕事は,和漢書目録掛によって昭和25年末に完成され,越えて26年10月に文部省へ発送した。同時に洋書目録掛においても,阪大に集められた自然科学欧文雑誌のカードの半数を京大が分担してマスターカードに仕上げ,阪大へ転送した。このようにして4分担館が作成した4部門のマスターカードは,文部省に集められて印刷に附せられ,昭和27年7月より28年3月にかけて,4部に分れて逐次出版せられた。
これは昭和22年3月現在の目録であるから,その欠を補うものとして「新着外国学術逐次刊行物一覧,Finding
List of Foreign Scientific Serials」が計画せられ,各館より報告したものを編輯印刷して昭和25年9月,その第1輯を出版し,次後毎年その刊行を見た。
昭和24年7月学術奨励審議会令が発令せられ,従来の「学術文献調査特別委員会及同技術科会」は「学術文献綜合目録分科審議会」と改称せられた。同時に「学術用語分科審議会」が発足して各種の科学用語を審議し統一を計った。図書館用語も数次に渉って審議せられ,遂に昭和33年5月に「学術用語集図書館学編」として出版を見た。
文部省においては昭和25年末には7大学による学術雑誌綜合目録の印刷原稿が完成したから,昭和26年度よりは学術図書綜合目録の編さんに着手することになり,分類別に学術図書の目録を作ることとし,これのパイロツトワークとして言語学綜合目録が企画せられ,50校が参加して印刷原稿を完了した。ついで文部省は各科について予備版を作成し,その予備版を各図書館に配布して所在をチエツクせしめ,予備版に記載なきものはカードを以って補足せしめる方法を取ることとなった。予備版の原稿担当は次表の通り予定し,着々と実行せられた。
昭和27年12月,文部省は「学術文献綜合目録の作成事業は文部省と国会図書館とが競合することになり大蔵省の指示に従って国会図書館との間に覚書を交換して両者の限界を明かにし,両者は相互に協力して本事業の円滑なる運営に努力する」旨通達して来た。従って28年度以後は学術図書の目録は作成しないことになった。
昭和28年7月23日付で文部省は学術文献綜合目録(欧文化学編)の予備版による照合補足を依頼してきた。同年9月16日付で照合補足を完了して文部省へ返送した。同年9月1日付で欧文物理学,数学,動物学,教育学各編の予備版の照合補足の依頼があり,同年12月23日付で照合補足を完了して文部省へ返送した。その中で物理学編は本館で整理編集するよう依頼されたので本館に留置した。
越えて昭和29年1月,欧文物理学編の記入済の予備版30校分を受領し,総合整理編集に着手し,カードに編集して同年3月30日これを文部省へ発送した。いずれも洋書目録掛が本務の傍ら余暇に従事したものであった。同年11月,学術雑誌綜合目録(自然及人文科学欧文編)増補改訂版の照合補足の依頼を文部省より受けたので,今回は商議会に回り,部局図書室の協力を求め,部局所蔵の学術雑誌をカードによって報告を受けることとした。集ったカードを総合整理してマスターカードに仕上げる業務は先づ自然科学欧文編が4月7日完了し,照合カード4,444枚,補足カード1,918枚,計6,362枚を文部省へ発送した。続いて人文科学欧文編が5月10日完了し,照合カード2,004枚,補足カード2,811枚,計4,815枚を文部省へ発送して,この件に関する本学担当の分は一応終了した。
越えて32年1月23日,文部省は学術文献綜合目録(欧文地学編,図書館学編)予備版の照合補足を依頼してきたが,同年3月30日完了。欧文地学編照合記入済及び補足カード1,343枚,欧文図書館学編照合記入済及び補足カード222枚を返送した。同年12月13日,学術雑誌綜合目録(自然および人文科学和文編)増補改訂版の照合補足の依頼があったが,翌33年5月15日完了。予備版記入済各1冊宛,照合補足カード自然科学編3,122枚,人文科学編4,069枚,計7,191枚を文部省へ発送した。この学術雑誌綜合目録増補改訂版は昭和32年3月より34年3月にかけて印刷せられ,4部に分けて発行せられた。なお,文部省に対しては学術雑誌総合目録の追加補遺を毎年カードによって報告している。
一方,学術図書(洋書)については前述の通り国会図書館へ昭和29年度以降毎年カードによって報告しているが,国会図書館は昭和29年度より31年度までの新収洋書を4分冊として印刷発行し,更に昭和35年度以降は年刊として発行する方針を取っている。
これを要するに,昭和15年に第17次帝国大学附属図書館協議会が立案した「日本綜合目録」の計画は,わが国が無謀な戦争に突入したため関係者のあらゆる努力にもかかわらず,終に実現を見ることができなかった。しかしこの計画は戦後違った形でふたたびとりあげられ,前に述べたように,いくつかの部門別の学術図書綜合目録や学術雑誌綜合目録が産み出されてきたことは,まだまだ不十分,不満足な点は多いにしても,喜ばしいことである。