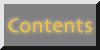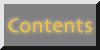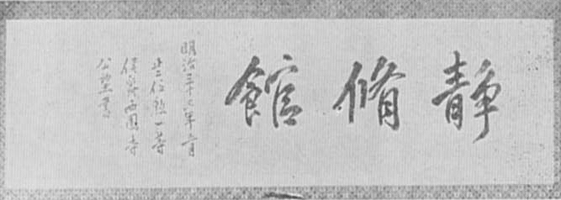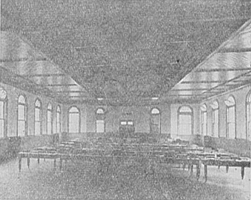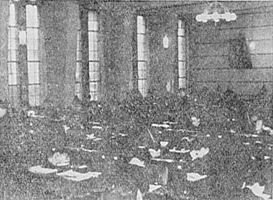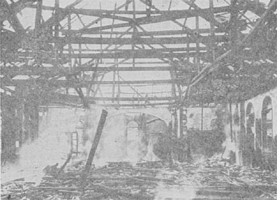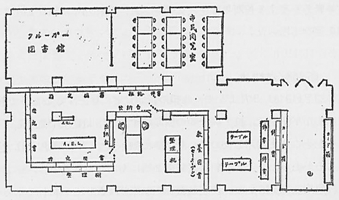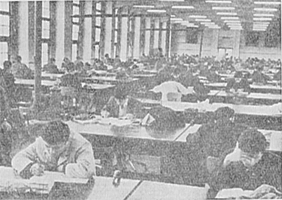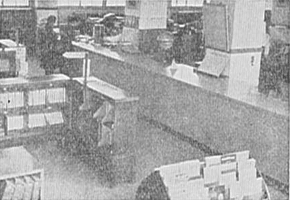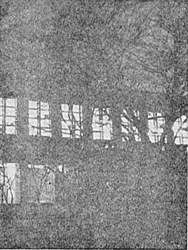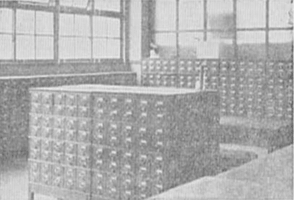第3章 図書の運用
第1節 閲覧貸出
1 閲覧室開室まで
明治30年(1897)京都帝国大学が創立されるに際し,木下総長は特に図書館について深い関心を払い,開学と共に理工科大学の一室において早くも附属図書館としての事務を開始せしめる一方,図書の収集についても自ら率先して,自己の所蔵する図書600冊を本学に寄贈して蔵書の基礎を築くと共に,知人・知己はもちろん,広く有識者に対し同年9月1日,下記の文面にて図書寄贈の勧説に努めた。
今般本学創立ニ付記念トシテ書籍・文書・標本等御寄贈下サレ候ハバ永ク之ヲ本学ニ蔵シ学術研究ノ用ニ供スベク候間成ルベク御寄贈ニ預リ度懇請ノ至リニ堪ヘズ候
追テ 本学図書館ハ其設備ノ完成ヲ待チテ本学々生ノ外一般公衆ノ閲覧ヲモ許シ候様致度希望ニコレアリ候
同時に帝国図書館を始め文部省・東京帝国大学・第三高等学校に対し保管転換を依頼,明治30年(1897)より32年(1899)の開館までの間に保管転換された図書の数は,帝国図書館より約2,000冊,東京帝国大学より約900冊その他約1,100冊という多数に達している。また特に学術的価値に富む集書については,一括購入の方法をもって急速な蔵書の充実を図ったため,本館は開館時において既に6万冊近くの蔵書を擁していた。丸善書店の京都支店の設置も本学創立を契機として,発足したと伝えられている。
かく木下総長は非常な熱意で図書の収集に努めるとともに,これ等の図書を蔵置する書庫等の建築,施設と整備の充実を推進した。翌31年(1898)7月には第1書庫に続いて閲覧室・事務室が新築され,従来理工科大学の一室で行っていた事務を,32年7月には新図書館内に移転し,開館の凖備にあたるとともに,夏期休暇中を利用して,各部局において購入した図書,また貸出されている図書の返却を求め,新たに原簿に登録の上一連の受入番号を付し,9月2日を以て完了,あらためてこれを各教室に貸付した。受入番号第1号の図書は東京帝国大学寄贈の「帝国大学一覧1896〜1897」である。
図書館を運営していく面については,31年(1898)12月2日「京都帝国大学図書館借受仮規則」が制定され,翌年11月29日には「京都帝国大学附属図館規則」,および「京都帝国大学附属図書館規則執行手続」が制定された。
図書閲覧票・図書閲覧証・図書借用証の諸書式も決定,さらに島文次郎も同年11月には初代の附属図書館長に補せられ,かくて人的機構においても陣容を整えるに至り,いよいよ閲覧室を開室するはこびとなった。
2 旧閲覧室時代
明治32年(1899)12月11日閲覧事務を開始した。本館ではその日をもって創立記念日としている。
この記念すべき日に先だち,木下総長は学生一同を集めて,図書館の利用について特に訓示を行なった。この時集った学生の数は100余名であったといわれている。
開館当時の図書館は現在の学生部・保健診療所の所在する場所であって,学生部の位置する所が閲覧室であった。その東側から北門・裏門にわたって松並木が連なり,幽邃ともいうべき環境で,夜間は狐狸の声を聞く事があったと伝えられている。この地を図書館に選んだのは「附属図書館は本学のみの図書館とせず,将来は当然市民一般に対しても広く開放すべきである」という木下総長の構想に基いたもので,現在の西門の場所に門を構え,そこから直ちに図書館に入り得る便宜を考慮したものといわれている。
また閲覧室は木造平家建,面積110坪余であって,160名を収容でき,当時としては広大なものであった。その入口には本学創立当時の文相,侯爵西園寺公望(のちの公爵)が諸葛亮の諭言をとって題した「静修館」の扁額が掲げられてあった。
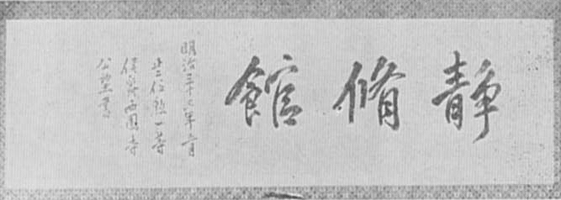 |
|
静 修 館
|
明治32年末に附属図書館が竣工した時,当時の文相の書記官であった中川小十郎氏が館名を西園寺公に委嘱したところ,「静修館」と揮毫して贈られたもので,その語の意味は文字通り静に修めることである。出典は小学巻ノ5外篇嘉言第5にあり,諸葛孔明が諭した言葉で,次の文章に基いている。「諸葛武候戒書曰,君子之行,静以修身,倹以養徳非担泊無以明志,非寧静,無以到遠」
この「静修」の語は平凡ではあるが,大変良い言葉であって,明治44年に学生監の山本良吉が編纂した学生必読書の目録である「静修書目答問」にも,その語が引用されている。
また故清国大官呉汝綸氏が来舘の節には,自ら「静修舘」の三字を大書して本舘に寄贈されたという。
閲覧室内には貴重図書閲覧席・特別閲覧席・目録検索席・参考図書閲覧席・新聞雑誌閲覧席があった。図書の閲覧に際しては,学生に対しては開館当日図書閲覧票を交付,また本学分科大学卒業者にして臨時に図書閲覧を出願,総長の許可を得た者に対しては閲覧許可証を交付した。また本館は篤志者の利用を許す意図であったから,特殊の研究者に対しては図書特別閲覧票を発行して,その希望を満すことになっていた。
この特別閲覧の制度は一つの伝統的なものとして,現在に至るもなお継承され,広く学外の篤志家に利用されている。12月11日開館以来32年中に開室した日数は僅か18日間ではあったが,その間に閲覧された図書の数は,和漢書402冊,洋書87冊合計489冊,利用人員は74名であった。12月24日には開館以来はじめて図書借用願が法学部助教授石川一より木下総長宛に提出され
等が貸出されている。
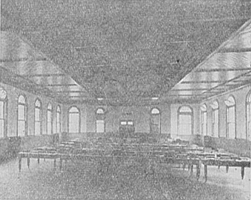 |
|
創立当時の閲覧室内部
|
図書館業務が軌道にのり,機能が発揮されるに従い,制度・書式の統一をはかることになり,33年(1900)5月には
従来各教室ヨリ本舘ヘ差入ルベキ図書借用証記入方ニ関シテハ一定ノ書式ヲ示シオキ候ヘ共様式用紙色々ノタメ大小区々ニ相成リ保管上不都合ノミナラズ其不体裁ニシテ一見不整理ヲ免レザルニ付別紙ノ通リ制定ノ上御調製相成リシカルベク候
という文書を各教室に回付した。これは図書館の図書を個人で借りる場合の借用証記入方式ではなく,研究用として教室に多数の書籍を長期間貸出す場合で,現在でいう公用貸付の制度に当り,書式に多少の変更は見られるが,この制度は今もなお続けられている。
また本館内に製本所を設け
本月ヨリ本舘ニ於テ仮製本所ヲ設ケ予メ左ノ標凖ニ依リ製本取扱候ニ付貴室ニ於テ製本ヲ要スル場合ハ便宣本舘ニ御送付相成度候 尤モ目下創設ノ際ニシテ未タ職工等人少ナルヲ以テ諸設備ノ完成ヲ告クルマテハ特ニ至急ヲ要スルモノノ他ハ送付時日ノ順次ニ依リ製本致サスベキ見込ニ有之候間右様御了承相成度 而シテ現品回付ノ際ハ必ズ製本送付簿ニ著者名・書名・冊数・製本種類(例ハ背革又ハクロース)送付年月日等ヲ記入シテ御送付相成度此段及御通牒候也
但 見本ハ本舘ニ落成致居候ニ付御来舘ノ上御検分相成度候
という案内状を配布し,本館の書籍はもちろん,学内各教室の製本業務を引受けるべく発足したのであるが,京都における製本の技術は未熟であったため,翌年9月には東京より職工を傭聘して当座の急に応じた。ところが37年3月末職工の辞職により製本所閉鎖のやむなきに至った。
明治33年(1900)の蔵書の数は,公爵近衛家よりの寄託による和漢書1万冊余,また宮内省より永久貸付のもの約5,200冊等をふくめ,購入・寄贈・保管転換によって逐年増加の一途をたどったため,当初の書庫では狭小となった。それで当年度より起工した書庫の増築の落成を待たずに,法科大学の2教室を本館の仮書庫に当てることとし,法律関係書をそこに分置するに至った。かくて開館1年にして早くも閲覧室および事務室の増築が要求されることとなった。
図書館の利用者が日増しに増加するにしたがい,特別閲覧を願い出る者も多数であったため,同年9月にはその資格を決めることになり,つぎのように規定された。
|
| 1 |
京都居住の大博士・博士・学士 |
| 2 |
京都居住の高等官(府庁・裁判所・諸官立学校等在勤の人) |
| 3 |
市長・助役・収入役 |
| 4 |
市府会議長 |
| 5 |
図書舘,博物舘長 |
| 6 |
商工会議所会頭 |
| 7 |
京都および附近の府,県,市立諸学校およびこれに凖ずる私立諸学校の校長,図書主任および教諭(但し―校五葉を限り其撰択は当該学校長に委任す) |
| 8 |
新聞記者(各社二葉を限り其撰択は当該社長に委任す) |
| 9 |
蔵書家・著述家・文学家 |
| 10 |
主要なる図書寄贈者 |
| 11 |
公共事業に熱心なる財産家 |
| 12 |
本学総長もしくは教授の特別に推薦せし人士 |
そして,特別閲覧券下附出願の場合には,総長の決裁を経てこれを受付するという事になつた。しかし翌年文部省主催による英語講習会が京都で開催され,本学の物理学講義室が講習会の会場にあてられた時には,その講習生に対しても願い出のある場合は,特別閲覧票を発行している,これはやはり広く一般研究者にも便宜をはかるという,創立以来の方針のあらわれであろう。
一方その頃は学内には各種の催し,式典等のさい,多数の人員を一時に収容できる設備がなかったため,33年7月14日には,分科大学の第1回卒業式の式場として閲覧室があてられたのをはじめ,新入生の宣誓式・本学の創立記念日の式典や展覧会の会場等,学内における主な式典・行事は殆んどこの閲覧室でおこなわれ,京都帝国大学における枢軸たるの観があった。この傾向は大正13年に本部大ホールが新築されるまで続いた。
開館当時の閲覧室には暖房の設備はあったが,点燈の方は完成されておらず,夜間の利用は全く不可能であった。したがって大祭・祝日・日曜日をとわず午前8時より午後5時まで開館するこになっていた。34年12月4日ようやく電燈の設備が完成され,従来の開館時間をあらため,平常は午前8時より午後9時まで,また夏期は午前7時より午後9時までという本館規則執行手続第16条および第17条の規定に従って開館されるようになり,ここに初めて夜間の開館が実施されるに至った。
一方法科大学購入による図書を前々年本館に引取り,精密な分類法により排架整頓していたが,35年附属図書館規則執行手続を補則した附属図書館および法科大学の図書の取扱手続が決定され,11月1日付で法科大学内に図書分館を設置し,同大学の3教室を仮書庫にあてて図書を収容することになった。しかしながら同大学内には閲覧室の設備はなく,そのために閲覧は本館の閲覧室において行うこととし,分館においては入庫検索および新着雑誌の閲覧のみを許可することになった。
蔵書の激増と機能の増強,事務の拡大に伴い,開館以来僅か5年にして,明治36年4月には3階建延289坪の新書庫(第2書庫)が落成,また閲覧室の設備においても現在までの普通電燈設備を改良し,「視力衛生上光線直射の害を避け,反射光を以て室内至る所に全く均一なる散光を与え,少しも陰影を止めず,恰も日中の室内に於ける光線の髪髴たる」,当時としては理想的ともいうべき散光式白熱電燈を架設,6月24日より点燈をはじめたので,閲覧者はますます増加し,狭隘を感ずるようになり,このためさらに教官閲覧室・特別閲覧室・新聞雑誌閲覧室・公衆閲覧室・事務室等の増築がのぞまれるにいたった。
ここに36年一年間の統計を見れば,増加図書冊数は和漢書5,454冊,洋書6,427冊合計11,881冊,当時の蔵書数は和漢書66,674冊,洋書48,906冊,合計115,580冊で,閲覧者は7,045名,閲覧された図書の数は和漢書22,763冊,洋書5,480冊,合計28,243冊,また図書を貸出した者の数は862名,貸出された図書の冊数は和漢書1,281冊,洋書1,634冊,合計2,815冊となっている,これを当時の学生数より見る時は,図書館の利用率は開館以来60年を経た昭和の現在よりも高い。
当時の本館利用者の9割までが法科大学の学生で占められている。この法科学生の利用率の高いのは,法科大学が閲覧室を持たず,同大学参考図書を展列せる書架を本館閲覧室内に増置し,また和漢書・洋書分類目録カードおよび洋書著者名目録カードを図書館内に備え,図書の検索に便したことによるものであろう。
一方規則に反した者に対する罰則はかなり厳しく,「授業料の未納者に対しては図書の閲覧を禁止する」むねを大きく閲覧室に掲示したのも37年頃のようである。図書の増加,図書館利用者の増加に伴い,図書の禁帯出制度を設けることが必要となり,閲覧希望の頻繁なものや,叢書の如き冊数の多いもので欠号が利用価値に大きく影響するもの,あるいは入手し難いもの等が禁帯出図書として指定され,38年9月1日付で実施された。開館以来10年目に当る明治41年4月には「京都帝国大学図書館案内」を作り,学生に配布して広く図書館について周知したのをはじめ,閲覧室の設備にも多くの改良を加えた。たとえば閲覧室西方の中央に高く出納台を設け,大卓子40を東西の方向に配列して監督に便し,西南入口に近く内外新聞の閲覧席を設置,西北の書架上には一般参考図書および法科参考書およそ1,100冊を排列し,共に自由展読に供したが,これは日本における自由接架式としてはきわめて初期に属するものと思われる。
また東南北の3方より自然光線を充分に導く設備が設けられているだけでなく,換気を完全なものにし,暖房は本館専用の機械(当時原価6,000円)によって,各部平均の温暖を保ち,厳冬にも陽春を思わせ,電燈は散光白熱式で,反射によって室内に平均した明るさを与えるようになっているのは,他にその類を見ないところといわれていた。また前年には教官閲覧室も新設され,室内には百科事典等が展列されていた。
大正時代に入ってからは本館の増加図書をカード目録に編成して,これを教官閲覧室に備付け,教官の閲覧の便をはかり,また事務室も増築され,43年(1910)の3月31日には電話も架設された(5225番)。これより電話によるサービスも可能となって,図書館機能・設備共にますます発展の途をたどったのである。
本館閲覧室は既述のように卒業式や,展覧会等の会場に使用されたため,宮殿下をはじめ貴顕の来館される機会が多かった。明治33年6月1日には東宮殿下(大正天皇)が有栖川宮殿下を従えて本館に行啓,閲覧室に陳列された貴重図書を御覧になった。明治44年には再び行啓があり,このたびは図書館の見学を主目的とされたため,書庫において教授の説明を御聴取になり,また閲覧室では学生の読書状況を御覧になって,お言葉を賜った。
年号も「大正」と変り,4年(1915)京都で行われた御即位の大典のため天皇御駐輦中は,図書館においても厳重な警備手配が講じられた。
代表当番者11月7日ヨリ同27日マデノ間各受持ノ日ニ午後9時前登舘シ事務所・小使室・書庫等ヲ巡回シ閲覧室夜間勤務者退出ノ時電燈スイッチノ絶縁戸締小使室消火ノ立会等ニ従事スル事
というような注意が伝達され,消火器のあり場所,警備用具の所在等を明記,あるいは職員の交替警備のため当番表が作られ,万全の警戒に当る等,当時の警備のものものしさがうかがわれる。
大正5年(1916)には従来普通閲覧室の一隅にあった新聞縦覧所を旧喫煙室内に移し,新しく新聞縦覧席を設け,自由閲覧させる方法をとった。これで新聞の縦覧が図書の閲覧と全く分離したため,統計の面でもこれまで閲覧人員の中に日刊新聞および新着雑誌の閲覧者が加算されていたのが脱落することになった。開館以来図書館の利用状況は上昇の一途をたどって来たが,大正5年に急に減少を見るようになったのはこのためである。また例年夏期休業中は午前7時より正午まで,規定の通り開館してきたが,大正6年(1917)には本館事務室の新築工事着手のため,旧事務室全部を移転する必要に迫られ,他に適当な場所がないため,閲覧室を一時仮事務所にあてることとなったので,卒業式のための休館(7月8日より15日まで)に引続き,9月10日まで長期間閉館した。これによってこの年も前年に増して利用者の減少を見るにいたった。
図書館創立20年に当る大正7年(1918)3月には,現在保健診療所に使用されている赤煉瓦平家建が新築される等のことがあって,当時の図書館の平面図を見ると,玄関入口のすぐ左手に新聞縦覧所があり,その向側東の方に出納台があり,次に閲覧室と広がり,この閲覧室には大正2年すでにリノリュームがはられていて,防音の考慮がなされていたことがわかる。また電燈も吊下式より隠見式に改良され,出納台の北側には教官閲覧室を配し,これを経て書庫に続いていた。また新聞縦覧所より西の方に事務室が配置されて,すべて最新の施設・設備がますます充実されたのであった。
ところがこの年全国各地に猛威を振った流感のため11月5日より14日までの長期間夜間閲覧を閉鎖するの止むなきにいたった。そのため年々に減少していた図書館の利用者は,この年更に大減少という結果になった。
大正8年(1919)には今まで使用されていた縦書きの借用証では,色々支障をきたすことが明らかになってきたので,以後横書きという新しい様式に改良された。
また明治の末年から図書の貸出人員が増加するに伴って,図書の未返却者もあらわれ,これに対して返却依頼状を出す事になった。
予而貸付中ノ左記図書本舘規則執行手続第10条ニ依リ期限満了ニ付一応御返却相成度此段御通牒候也
というのがその督促状の文面である。このようにして図書館も歴史を重ねるにしたがい,些細な部分にまで気をくばらねばならぬようになったのであるが,大正9年(1920)1月29日学生有志者総代より館長宛に
本学附属図書舘ノ燈火近来殊ニ不十分ニシテ殆ド細字ヲ読ムニ耐エサルモノ有之哉ニ被為感候ニ付テハ特ニ御調査ノ上可然御設備相成度此段奉懇願候也
という願い書が出されたことも,発展途上にある本館としては,考えさせられるところであった。
また京都府警察部より大正10年(1921)11月に
左記出版物ハ安寧秩序ヲ妨ルモノト認メラレ本日8日内務大臣ニ於テ発売頒布禁止並ニ差押処分ニ附セラレ候条一般ノ閲覧用トシテ備付相成ラザル様御注意相成リ度此段及御通知候也
追テ爾今禁止処分有タルトキハ其都度御通知可致候条御承知相成度
という通告を受け,「自由評論11月号・憲政公論第1巻8号・工業之大日本第18巻11号」等が相次いで閲覧禁止となり,時代の流れにともなって,図書館にまで暗い影がきざしてきたのを感じることができる。
大正11年(1922)には学位論文を図書館で保管学位論文を図書館で保管する事となったが,保管の方法および閲覧借受に関する手続については確定的なものはなく,時に応じて処理していたが,昭和35年2月「京都大学附属図書館の保管にかかる博士論文の保管および運用は,貴重図書に凖じて取扱う」と云う内規が設けられた。
大正12年9月には関東地方に大震災があり,東京帝国大学および東京商科大学図書館が焼失したため,その学生にして本館利用を希望する者に対しては,非常事態を考慮して特別閲覧の便を計ったが,これを契機として大正14年5月に開かれた第2次帝国大学附属図書館協議会にこの問題が取上げられ,帝国大学相互間において,休暇中学生が帰省先の図書館の閲覧希望を申し出た場合には,図書館対図書館の間で互に依頼状を交換し,学生の図書閲覧の便を計るという申合わせが成立した。以来現在もなおその制度が続けられている。
稀覯書を多数に蔵する当館としてはその保全を考慮し,大正14年(1925)7月には鉄筋4階建延143坪の書庫(第3書庫)が増築され,ここに貴重書を蔵めることになった。年と共に図書館の新設される数も全国的に増すにしたがい,すでに20余年の歴史をもつ当館に対して参考資料の寄贈依頼や,実地見学に来館する者も多くなった。
図書館の記事が学内新聞にもたびたび載るようになったのも,この頃からで,京都帝国大学新聞大正15年2月15日付には「試験を前に賑う図書館,大入満員で席が足らぬ」と題して,当時の図書館の盛況ぶりが語られ,5月1日付では「学内紹介」として図書館の利用状況が説明される等,新聞の話題に上ることが頻繁になった。
また前年10月には文部省主催として,図書館職員講習会が本学において開かれ,「図書運用法・図書の分類法及排列法」等が講義され,日本の図書館界もいよいよ大きく動き出したことを知ることができる。
昭和時代となると,図書館活動の進展と共に,1冊でも多くの図書を広く利用させたいという理想のもとに,昭和4年(1929)には全国の帝国大学附属図書館相互の間において,図書貸借の申合わせが成立した。
図書の相互貸借
|
| |
この制度は帝国大学相互間においておこなわれるもので,本舘では明治32年11月すでに東京帝国大学附属図書舘に対し下記のような借用依頼を提出している。これは図書相互貸借の最初と思われる。
|
| |
|
「貴学所蔵ニ係ルGareis著 Allgemeines Staatsrecht本学ニ於テ本年中入用ニ付十部程借用致度別紙借用証相ソヘ此段御依頼ニ及ビ候也」 |
| |
昭和4年9月に台北で開かれた「第6次帝国大学附属図書舘協議会」において,この件についての申合わせがなされ,制度化された。 |
| |
|
1.帝国大学附属図書舘相互ノ間ニ於テ図書ノ相互貸借ヲナス |
| |
|
1.同時ニ貸出シ得ル図書ハ3部3冊以内トシ,尚和漢装書ハ3部9冊以内トス但シ当該舘ノ規程ト抵触スル場合ハ此ノ限リニアラス |
| |
等図書の貸借についての大略が定められた。また「第8次帝国大学附属図書舘協議会」において,図書申込より返却までの通知書等の様式(A〜Eの5種類)が定められた。
|
| |
昭和5年(1930)5月には京都帝国大学新聞にも「他の帝大の図書でも郵送借覧が出来る」と題し,周知宣伝を行なった結果,大正末年に制度化された「帝国大学相互閲覧に関する協定」とあいまって,多くの学生・学内研究者に利用された。戦時中は一時中絶の状態であったが,戦後は文献の複写装置が設備され,現物郵送に伴う色々な障害をまぬがれるため,特別の場合をのぞいては,すべてマイクロフイルムにより,その利用の増加は著しいものがある。 |
新城博士が総長に就任されるや図書館の改善を企図し,その頃議題に上っていた新館の建築計画にあわせて,学生の便益のため指定書制度が立案され,昭和5年4月より開始されるに至った。
指定書制度
|
| |
学生の参考用として設置されたもので,新城総長・新村舘長・山鹿司書官は,既設の東京帝国大学附属図書舘の指定書の状況を視察に赴き,いよいよ設置が決定されるや,大学会計課より図書の購入費として15,000円,3カ年継続事業として第1年度分5,000円が臨時支出された。 |
| |
また各学部教室主任に対しては指定書の選定を依頼し,予算の範囲内でまず第1年度分739冊(金額4,797円80銭)の選定を得た。 |
| |
これ等の図書を閲覧室の出納台附近の一部を仕切り,7学部別に分類陳列し,利用し易いように接架式とした結果,学生の好評を博し,指定書を利用する者の数は次第に増加し,今まで余り図書舘を利用しなかった自然科学系の学生の利用者も,とみに増加するに至ったことはとくに記すべきであろう。 |
| |
第2・3年度分も継続支出され,15,000円による購入冊数は約1,700冊に達し,これを基礎として,その後図書舘の経常費より,あるいは臨時費より新規購入をおこない,さらに法学部・経済学部・工学部電気科等よりは図書の提供を受けた。時代のうつりかわりと共に指定書に対する関心が低下したので,昭和12年(1937)3月には再び羽田舘長の名義をもって,
|
| |
|
今般本舘ニ於テ第二閲覧室備付ノ学生閲覧用指定図書購入致シ度存シ候ニ就テハ乍御繁忙中貴学学生用トシテ金300円ヲ超過セサル範囲内ニ於テ然ルベキ図書御選定ノ上,書名・冊数・発行所及ビ価格ヲ来ル25日迄ニ御回報ニ預リ度早急ノ御願ニテ恐縮ニ存シ候ヘ共宣敷御依頼申上候 |
| |
|
追而右図書ハ本年度予算ヲ以テ経理セラルヘキモノニ有之候ニ付即時購入シ得ルモノニ就テ御選定相成度且ツ持合セ書店名ヲモ附記被下候ハハ好都合ニ存シ候 |
| |
|
尚実際ノ経理ニ於テ前記金額ニ多少ノ増減ヲ生スルヤモ計リ難ク此儀併セテ御含置相成度候
|
| |
と各教室主任に対し指定書の選定を依頼した。以来指定書は増加の一途を辿り,若干整理返還されたものを差引いて,昭和18年(1943)4月にはその冊数は3,939冊に達した。しかしその後戦争のため指定書の補充が不可能となり,戦後は世の中の変化と共に,従来の備付図書ではその利用価値は甚だ稀薄となるに至った。
|
| |
その後は部局教官よりの指定を得る途も中断されていたので,学生の勉学に必要と思われるものを本舘の見解によって購入し,当座の要求を満してきたが,昭和33年(1958)4月の図書舘商議会で「指定書制度」が取上げられ,同年秋には各部局に対し指定書の選定を依頼した。しかし指定書に対する認識が徹底していなかったためか,和書33冊・洋書36冊という少部数しか指定されなかったので,35年(1960)にはあらためて,助教授以上の教官に依頼し,和書308冊の指定を得た。
|
当時の閲覧室は座席敷も 100余にすぎず,学生・職員の増加にともない,狭くなってきたので,幾度か新館の建築が計画されたが,それをまたず昭和8年(1933)に新築なった法経学部研究室の2階に,臨時施設として第2閲覧室を開設した。もとの第1閲覧室には新着書・趣味書・教養書および内外新聞と百科事典等を備付け,新設の第2閲覧室には指定書および辞書類等を配して,9月25日より開室した。
新設された第2閲覧室の座席数は224席で,第1閲覧室の座席数144を加えると計368席となり,従来の約3倍となったが,これでも到底所要の半ばをも満すことができず,本学に即応した図書館の誕生が待望された。
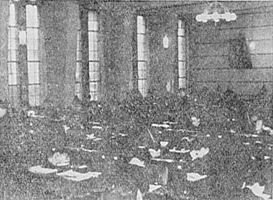 |
|
第2閲覧室
|
昭和9年(1934)3月末の調査によれば,全学の蔵書数は遂に1,022,632冊(和漢書457,438冊・洋書565,194冊)に達し,大正の初年より20余年にして約70万冊の増加を見たのは驚くべき現象である。しかもこの外寄託本として近衛公爵家の近衛文庫10万冊,久原房之助氏の久原文庫数万冊があり,建物こそ貧弱ではあるが,その内容においては正に東洋一を誇り得べく,これが完全な保存と利用のためにも,図書館の新築が学の内外から待望されつつあった。100万冊目に当る図書は昭和8年6月8日に受入れされ,同年12月13日焼失した工学部電気工学教室所属の「電気協会発行・電気鉄道車輛基本要項1」である。
また9年7月より10月にかけて下記の通り約200冊に上る多数の雑誌および新聞等の閲覧禁止が通達され,事変の進展と共に,国内の緊迫した空気がうかがえる。
|
| 7月11日 |
|
大亜細亜 |
2巻 7号 |
|
進 メ |
180号 |
|
太 陽 |
5巻 7号 |
|
愛国新聞 |
78号 |
|
日ノ丸新聞 |
76号 |
|
進 メ |
183号 |
|
自由聯合新聞 |
92号 |
|
社会運動通信 |
1,392号 |
|
帝国新報 |
6,633号 |
|
帝国新報 |
6,634号 |
|
新聞研究詳報 |
号 外 |
|
大阪無産新聞 |
号 外 |
|
社会運動往来 |
6巻 7号 |
|
労働者新聞 |
29号 |
|
| 7月13日 |
|
文学通信 |
10号 |
|
帝国新報 |
6,636号 |
|
改造戦線 |
39号 |
|
青年日本新聞 |
24号 |
|
労働通信 |
367号 |
|
日本思想問題通信 |
273号 |
|
| 7月24日 |
|
昭 和 |
5巻 8号 |
|
日の丸新聞 |
77号 |
|
日本神話ノ新解説 |
(日本歴史の再認識) |
|
進 メ |
191号 |
|
関西文学 |
7月号 |
|
石川啄木ノ研究 |
|
|
富山日報 |
1,716号 |
|
社会運動通信 |
1,405号 |
|
大成新聞 |
6,868号 |
|
文 芸 |
2巻 8号 |
|
大和新聞 |
13,567号 |
|
進 メ |
190号 |
|
大正日々新聞 |
5,665号 |
|
社会運動通信 |
1,403号 |
|
婦人日々新聞 |
2,408号 |
|
法学論叢 |
7月号 |
|
経済往来 |
9巻 8号 |
|
新聞時代 |
1,555号 |
|
| 7月31日 |
|
啄木研究 |
8月号 |
|
社会と国体 |
8月号 |
|
進 め |
199号 |
|
社会運動通信 |
1,412号 |
|
土地と自由 |
124号 |
|
日本歴史大観 |
里見岸雄著 |
|
近畿防空演習ニ関スル調査 |
7月20日 |
|
女性雑誌 |
2巻 8号 |
|
読 書 |
3巻 8号 |
|
新聞改造 |
519号 |
|
日 本 |
2,268号 |
|
バンティスヱァー |
4巻 5号 |
|
オール性慾科学大系 |
松浦清訳 |
|
酒井将軍ノ大古日本ピラミット |
7月25日 |
|
| 8月3日 |
|
近江新報 |
14,449号 |
|
報国新聞 |
1号 |
|
大阪万朝報 |
5,683号 |
|
帝国日々新聞 |
719号 |
|
日満時代 |
2巻 7月号 |
|
世論時代 |
8巻 8号 |
|
逓友倫理会の倫理講演集 |
382号 |
|
月刊日本 |
123号 |
|
大阪万朝報 |
5,682号 |
|
帝国日々新聞 |
718号 |
|
道の友 |
44巻15号 |
|
回転時報 |
9巻 7号 |
|
黒色新聞 |
30号 |
|
| 8月7日 |
|
進 メ |
205号 |
|
大阪日々新聞 |
11,846号 |
|
自由聯合新聞 |
93号 |
|
泉州日報 |
5,034号 |
|
進 メ |
206号 |
|
大阪政治新聞 |
149号 |
| 8月11日 |
|
進 め |
210号 |
|
帝国新報 |
6,663号 |
|
日本精神 |
60号 |
|
月 報 |
70号 |
|
大和新聞 |
16,438号 |
|
社会運動通信 |
142号 |
|
毎夕新聞 |
11,983号 |
|
| 8月17日 |
|
泉州日報 |
5,037号 |
|
大正日々新聞 |
1,682号 |
|
社会運動通信 |
147号 |
|
皇道新聞 |
18号 |
|
日刊大和 |
1,541号 |
|
夕刊帝国 |
10,496号 |
|
大正日々新聞 |
592号 |
|
泉州日報 |
5,038号 |
|
大阪日々新聞 |
11,847号 |
|
毎夕新聞 |
11,982号 |
|
錦旗公論 |
8月号 |
|
現代詩人 |
8月号 |
|
労働問題通信 |
610号 |
|
合同通信 |
2,804号 |
|
| 8月26日 |
|
新女性鑑 |
林 逸馬著 |
|
合同通信 |
3,604号 |
|
中央公論 |
49年10号 |
|
文芸術 |
9月創刊号 |
|
内外公論 |
13巻 8号 |
|
錦 旗 |
3巻 7号 |
|
大正日々新聞 |
569号 |
|
進 め |
217号 |
|
経済往来 |
9巻 9号 |
|
大正日々新聞 |
570号 |
|
国民運動 |
9号 |
|
詩精神集団 |
5号 |
|
| 9月8日 |
|
黒色新聞 |
31号 |
|
進 め |
229号 |
|
新使命 |
9号 |
|
東京毎夕新聞 |
12,006号 |
|
月刊日本 |
124号 |
|
北陸日々新聞 |
104,180号 |
|
民衆解放 |
12号 |
|
講 壇 |
9月号 |
|
肉体驚異 |
8月30日 |
|
巨 雲 |
5号 |
|
社会運動通信 |
1,439号 |
|
大衆経済雑誌 |
9巻 9号 |
|
進 め |
228号 |
|
社会運動通信 |
1,442号 |
|
週間時局新聞 |
70号 |
|
新興日本仏教新聞 |
170号 |
|
進 め |
231号 |
|
北陸日々新聞 |
9月5日朝刊 |
|
報 国 |
2巻 3号 |
|
東京日の出新聞 |
1号 |
|
作家郡 |
2巻 9号 |
|
青年運動 |
2号 |
|
進 め |
227号 |
|
愛 国 |
8巻 8号 |
|
| 9月9日 |
|
進 め |
235号 |
|
満鮮情報 |
12巻 8号 |
|
自由聯合 |
16巻 9号 |
|
明徳論壇 |
9号 |
|
サラリーマン |
7巻 9号 |
|
女性の敵 |
本田源吉著 |
|
| 9月13日 |
|
文学通信 |
12号 |
|
社会運動通信 |
1,451号 |
|
政界春秋 |
10月号 |
|
勤労日本 |
3号 |
|
港 説 |
88号 |
|
人 生 |
4巻 9号 |
|
作家郡 |
2巻 8号 |
|
日本思想問題通信 |
28号 |
|
改造戦線 |
43号 |
|
政治批判 |
9月15日 |
|
護国新報 |
1号 |
|
進 め |
237号 |
|
内外情報 |
17号 |
|
短歌評論 |
2巻 8号 |
|
| 9月27日 |
|
実業大阪 |
10巻 10号 |
|
社会新聞 |
65号 |
|
大 日 |
87号 |
|
労働新聞 |
62号 |
|
大亜細亜青年 |
6号 |
|
核 心 |
1号 |
|
週間時局新聞 |
73号 |
|
社会運動通信 |
1,462号 |
|
社会運動通信 |
1,454号 |
|
実業界 |
10巻 9巻 |
|
太 陽 |
5巻 9号 |
|
維 新 |
2号 |
|
大阪国粋大衆新聞 |
24号 |
|
日本思想問題通信 |
287号 |
|
政経評論 |
10月号 |
|
青年運動 |
3号 |
|
| 10月8日 |
|
日本労働通信 |
2,627号 |
|
航空時代 |
5巻 10号 |
|
1936年ノ嵐ヲ前ニ狂弾何オカ撃ツ |
|
|
二陸タイムス |
1,645号 |
|
文学建設者 |
1巻 8号 |
|
自由評論 |
14号 |
|
歴史科学 |
3巻11号 |
|
血 涙 |
11号 |
|
興国運動 |
17巻 10号 |
|
社会運動通信 |
1,464号 |
|
思想問題集 |
2号 |
|
月刊日本 |
125号 |
|
明徳論壇 |
91号 |
|
新聞研究評報 |
号 外 |
|
土地と自由 |
127号 |
|
日本思想 |
4巻 7号 |
|
国 論 |
1巻 7号 |
|
日 暦 |
6号 |
|
1936年 |
2巻 10号 |
|
社会と国体 |
129号 |
|
囚われた大地 |
|
|
| 10月20日 |
|
日本精神 |
64号 |
|
報知新聞 |
20757号 |
|
婦人公論 |
19巻 17号 |
|
大衆倶楽部 |
3巻 11号 |
|
読売新聞 |
20718号 |
|
海と空 |
3巻 12号 |
|
航空時代 |
5巻 10号 |
昭和11年(1936)1月24日不幸にして第1閲覧室の一部より火を発し,当初よりの木造閲覧室は烏有に帰したが,書庫および事務室の類焼を免かれたのは,不幸中の幸ということができる。しかしながら当時における図書館の諸施設が,あらゆる面においてすでにその機能を到底満し得ない実情にあったことは何人も認めていたため,この火災を機会に真に本学にふさわしい図書館を新たに建築することになり,直ちに現在の建物である新館の設計が始められた。
本舘閲覧室の火災
1月24日午前10時50分頃,附属図書舘閲覧室玄関入口に接する新聞閲覧室の天井裏および西側壁面内より火を発した。当時閲覧室には約140名の閲覧者と,新聞閲覧室にも数名の学生がおり,新聞閲覧中の学生がいち早く火を発見し,直ちに職員・消防手が出動,その他も協力して消火に努める一方,学生・青年団員等の援助を得て,書籍・器具等の搬出に努めたのであるが,建物が木造のため,火はたちまち天井に燃え拡がり,火勢は強烈を極め,遂に閲覧室および附属建物をほとんど全部焼失して,同11時30分ようやく鎮火した。
焼失した建物中に収容されていた書籍・器具の一部分は搬出したが,水浸しになったものも多く,また散逸するものもあって,使用に堪えないものが少なからずあった。事務室は出火の場所と近接していたが,直ちに器具・書籍類を搬出し,焼失はまぬがれたが,散逸破損等かなりの被害をうけた。火災による損害は,
|
| |
図 書 |
焼失したもの |
破損したもの |
| |
|
和 書 1,919冊 |
和 書 151冊 |
| |
|
洋 書 1,021冊 |
洋 書 163冊 |
| |
|
合 計 2,940冊 |
合 計 314冊 |
| |
閲覧用カード 36万枚 |
|
| |
金 額 |
建築物損害 |
27,940円 |
| |
書籍の損害 |
11,700円 |
| |
その他 |
5,630円 |
| |
合 計 |
45,270円 |
であった。
附属図書舘の雇吉田耕三は火災中図書搬出に努めていた際,落下した焼材が着衣に燃え移り,顔面・両手等に全治約3週間の火傷を負い,また理学部地球物理教室雇の香川勇も頭部に負傷した。
出火場所に近く,それでいて焼失を免れ関係者一同を喜ばしたのは,閲覧室正面の奥にかけられてあった西園寺公の書になる「静修舘」の大額が工学部の土田幾久・倉内正の両学生によつて無事持ち出されたことであった。
 |
|
猛火に包まれた図書館(昭和11年1月24日)
|
本館の罹災について松井総長をはじめ本部当局は至急善後措置について協議したが,法・経両学部の好意により,第4教室を火災の当日より3月一杯借用して,一時をしのぐことになった。
一方図書館では折柄の試験期を前にして,館員一同文字通り昼夜兼行の整理に当った結果,臨時に貸出し規程を発表し,閲覧貸付の便をはかることになった。
|
|
1.在庫書籍の閲覧は当分のうち第2閲覧室のみを用いる。 |
|
2.閲覧希望者は,第2閲覧室で備付の閲覧用紙に記入して差出されたし。但し次の通りに時間を制限する。 |
|
第1回 申込時間 午前9時 貸出時間 午前10時 |
|
第2回 申込時間 午前11時 貸出時間 午前12時 |
|
第3回 申込時間 午後3時 貸出時間 午後4時 |
|
但し日曜・祝祭日は貸出の申込みを取扱わない。若しこの日に閲覧したい時は,前日の午後3時の締切りまでにその旨を申込んで置かれたい。 |
|
3.舘外の貸出は,従来通り,図書舘事務室で行う。なお第4教室を一定の期間中臨時閲覧室にあてるが,ここでは貸出事務は取扱わない。
|
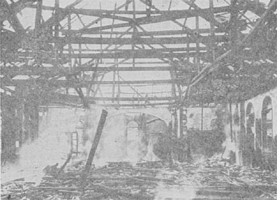 |
|
焼け落ちた図書館閲覧室
|
かくの如く臨時措置はこうじられたが,閲覧用カードが全焼した上,閲覧室と書庫との距離が遠く,また人手が少ないため,その不便はとうてい免れられなかった。
閲覧室焼失以来本館では,その後数度の会議を開いて,少なくとも100万円程度の,すなわち地上3階・地下1階・書庫7層として総面積延2,200坪,閲覧室も2階と3階にそれぞれ第1・第2の2室を設け,優に全学生数の10%近くを同時に収容することができ,同時に各室の施設・設備においても近代図書館の機能を充分に果し得るものであり,耐震・耐火の点においても,名実共に最高学府の名に恥じないような図書館の建築を計画し,その実現に邁進することになった。しかし学生の受けている不便を少しでも緩和するため,使用頻度の少ない本部の大ホールを臨時閲覧室として代用することになり,机・スタンド等が設置され開室凖備が進められた。
3 仮閲覧室時代
昭和11年(1936)9月15日をもって本部階上大ホールを仮閲覧室として,とりあえず昼間のみ開室することになったのであるが,大ホールは本学唯一の式場であるために,事ある毎に,仮閲覧室を休室しなければならぬことがしばしばであった。一つの式典が行われるとなると,閲覧室の設備を撤去しなれけばならず,式典後はまた設備の複元に手数を要するというわけで,少なくも3〜6日がそのために空費され,頻繁な時は開室3〜4日にしてまた閉室という有様であった。昭和13年における仮閲覧室の開室日数は172日で,一年の約半数しか開室しておらず,休室時は臨時に法経第4教室もしくは第6教室を閲覧室に当てたこともあるが,閲覧者の不便は多大であった。この状態は昭和14年3月仮閲覧室が第2閲覧室内に移転するまで続いた。
 |
|
仮閲覧室(本部階上大ホール)
|
この昭和11年9月15日は仮閲覧室開室の日であると同時に,構内西門の初めて開かれた日でもある。西門は木下総長が図書館の建築を構想した当時,すでに本学の西門の位置として想定していたのであって,図書館をこの門の附近に配し,学外者にも図書館の門戸を開放利用せしめる理想から,もっとも便利な位置として考えられたものであった。その西門が開かれる同じ日に図書館閲覧室の方は不慮の火災のためとはいえ,西門からは相当遠い本部階上の仮閲覧室に移らねばならぬ破目に立到ったことは,運命の皮肉ともいうべきものであろうか。現在新図書館はこの西門の近くに屹立し,登館者の多数がこの門より出入りしている。
翌12年(1937)4月に至り,焼失した閲覧用カード目録の複元完成と共に,仮閲覧室も昼夜開室することになったが,書庫が離れているため,借覧の申込みは取りまとめて出庫することとし,1日7回に制限していた。
申込時間 貸出時間
午前 8時半 午前 9時半
〃 9時半 〃 10時半
〃 10時半 〃 11時半
〃 11時半 午後 1時
午後 1時 〃 2時
〃 2時 〃 3時
〃 3時 〃 4時
この不便を少しでも緩和する方法として,書庫より出した図書に対しては「保留制度」を採用,これにより書庫より一度出された図書を,次の日も続いて閲覧したい場合は,掛員に「保留紙」を請求し,それに所要の事項を記入して,これを図書に挿入しておけば,4日間は書庫に収めず閲覧室に保存し,次回からは前記の貸出時間に関係なしに借覧することができる方法をとったのであるが,この方法は学生の間に大変好評を博した。しかし大ホールと書庫との距離は遠く,閲覧図書の運搬には数百メートルも往復に要するので,閲覧者のみならず,本館職員も如何に大きな不便を忍んでいたかがわかるのである。
前記火災により焼失した教官閲覧室は,その後急ぎ再建され,翌12年(1937)8月には,焼け跡附近に新築が成り,各教官に対し
|
|
「予テ建設中ニ係ル教官閲覧室竣工致シ,御利用下サルヨウ周知方可然御取計被下度此段御依頼旁々右得貴意候也 |
|
追テ右閲覧室ハ所在場所ハ本舘書庫前ニ有之候条此段申添候」 |
という文書を発送,利用方を勧請した。
満州事変の進展に従い,学生に対しても国民精神総動員の高揚という見地から「国体及国策よりみたる満支・軍事・産業及び国際関係」等に関する解説・記述書を,閲覧室内に特別の書架を設置して展列する施策がとられ,貸出手続も簡易にし,学生に親しみやすいよう計ったのも昭和13年(1938)頃である。またこの頃より防空演習が実施されるようになり,そのため第2閲覧室を午後6時に閉室,以後の閲覧は防空の設備ある仮閲覧室で規程の時間まで行う等,閲覧室焼失後の不便を忍んでいる学生達を,ますます困らせることが多くなっていった。
図書館の再建も昭和11年12月には文部省の認可をみるに至り,12年には起工の予定であったところ,たまたま勃発した日華事変による非常時局のため,着工延期の止むなきに至ったが,昭和14年(1939)5月になってようやく工事に着手,翌15年(1940)1月20日戸田組により地鎮祭をおこなった。しかしますます激化してゆく事変は遂に太平洋戦争へと拡大し,この余波を蒙って図書館新築の当初の設計も地上2階に縮少され,しかもその工事はわずかに外郭のみに留まり,他は一切未着手のまま放置されるに至り,永い間廃墟のごとき不気味さをただよわせていた。
|
|
川端警察特高課検閲係より |
|
毎度御繁忙中恐縮ノ至リニ候ヘ共別紙本年中ニオケル読書ノ傾向ヲ条知致度ニ付キ本月7日迄ニ必着ノ様御依頼申上候 |
という通告を受け,読書傾向の検閲を受けることになったのも昭和14年頃からであり,いよいよ緊迫した国内の状勢を感じとることができる。
昭和15年(1940)2月には今までの旧式な借用証の様式を改良,3連式の様式に改められ,それを整理すれば「誰が」「何を」「いつ」の3方面から追求できるようになった。また本館創立以来「図書閲覧票」を発行してきたやり方も,「学生票」によって閲覧できる方法に簡便化される等,すべての点において簡単な方法がとられるようになり,閲覧者に対しても何かと便したのであった。
昭和16年(1941)本学教官より,その著書の出版されたものの寄贈を受け,これを教官文庫と名づけて閲覧室内に展列する事になった。
|
| 教官文庫の設置 |
|
本学の教官の著述を蔵置し,学生の閲覧を許して研学と訓育とに資したいという構想のもとに考案されたもので,昭和16年1月30日に開かれた第17回図書舘商議会で「教官文庫の設置」の件が議題に上り,舘長名にて下記のような依頼状を各教官に対し発送することになった。 |
|
|
拝啓倍々御清穆奉賀候 |
|
|
陳者去1月30日開催相成候図書舘商議会ノ御同意ヲ得テ今般第二閲覧室ニ「教官文庫」ヲ設置シ各教官ヨリ著書ノ寄贈ヲ仰ギ学生生徒ニ閲読セシムルコトト致度斯クシテ一面ニハ本学ノ学問的業蹟ヲ蒐集展開シ他面ニハ著者ヲ通シテ研学ト訓育トニ資シ度存居候就テハ寔ニ卒爾ナガラ今後新著御発刊ノ場合ハ一部本舘ヘ御恵贈ニ預リ度尚過去ノ御著書ヲ余部有之候ハハ此際御贈与願度此段御依頼申上候 敬 具 |
|
|
猶乍勝手貴学事務室ヘ御差出被下候カ又ハ電話ニテ御一報被下候ハハ舘員差遺シ可申候間何卒宣敷御願申上候 |
|
かくして昭和16年中に合計31名の教官より,86冊の図書が寄贈されたのであるが,元来この文庫は学生指導上多大の効果を与えるものと考えられるので,以後もその発展に協力を求め,毎年3月または随時各教官に対し寄贈依頼を求めた。現在では約600冊となり,新刊書は他の新刊と同様閲覧事務室内に展列している。しかし本館では,これに先だち明治42年(1909)2月1日すでに本学教官に対し著作の寄贈依頼を出しており,これが教官文庫の最初と思われるが,その時の依頼状はつぎの通りである。 |
|
拝啓本学教授ノ著述ハ之ヲ総羅シテ本図書舘ニ備付,永久保存致オキ度,就テハ内外国語ヲ論ゼズ御著述若クハ御論文御座候ハハ此際一部御寄贈ノ栄ヲ得度,右ハ菊池総長閣下ノ御意見ニモコレアリ候間特ニ御依頼申上度,得貴意度候 |
同16年(1941)より,4月に「新入生就学案内の会」が開催されることになり,図書館長もこれに出席し,図書館の利用について述べると同時に,「京都帝国大学附属図書館案内」を配布した。この方法は新入生の間に大変好評を博し,現在に至るも毎年続けられている。また戦争の拡大は学生の勉学にも影響を及ぼし,同16年度からは卒業時期が繰上げられ,講義も従来のように完全を期し得ないようになったため,講義補充の意味で図書館を利用する者がますます増加することを考慮し,図書館では学生の希望図書をできるだけ閲覧室に備付ける方法をとり,学生に希望図書を申込ませ,要望に応じるようつとめた。
昭和17年(1942)度の本館における学生の読書傾向を第2閲覧室に見ると,昭和15年教養書を設置して以来その利用者は増加し,中でも「健康読本 高木逸雄著」・「健康と長寿 小沢修造著」等健康に関するものが良く読まれ,科学書では「科学の勝利 アントン・チシュカ著」・「南方文化の探究 河村只雄著」等気軽な随筆的なものが受けており,この傾向は美術書にも見られる。次に「信仰と生活 梅原真隆著」が仏教書と共に多く読まれ,特殊なものとしては「病床受洗 中村明著」等を上げることができ,「生」へのひたぶるな探求がうかがわれる。「杉兵長の手記と憶い出 立命館大学編」・「若き哲学徒の手記 弘津正二著」が一貫して良く読まれているのも,この傾向を物語っている。昭和17年10〜12月にかけて一番良く読まれた「如何にして学ぶべきか 加田哲二著」は,この時代としては注目に値する。その他読書の方法論に関するものが多くの%を占めているのは,読書方法自体に関する混迷が学生側に残っているものというべきであろうか。「戦争を通じて人生への探究が一方に根強い力で貫かれながらも,一方では逞しい知性のかがやきがすべての分野に貫かれ」ていると,当時の京都帝国大学新聞は報じている。時局は遂に大東亜戦争となり国民総厥起の意味から昭和17年10月以後は,勤務時間が1時間延長され,また時間外の非常時態に備えて宿直制度も設けられた。18年(1943)11月からは空襲に備えて毎日当番制でつめきり,第3書庫の西側に防空壕を堀り,「京都帝国大学附属図書館防衛団」が結成され,規則および規定も定められた。一方閲覧室においても時局の緊迫から,節電と暖房設備不能のため,開室時間短縮の止むなきに至るとともに,学徒動員による学生数の急激な減少により図書館利用者も激減し,昭和19年(1944)4月からは仮閲覧室と第2閲覧室を併合縮小された。同年6月には図書館所蔵の貴重書を戦火から守るため,安全な場所に疎開させる事になり,計3,054冊を嵯峨大覚寺宝蔵・府下南桑田郡保津村等に移した。また人文科学研究所文庫70冊余りを,常時閲覧室に備付けるとともに,学部の図書を学生の閲覧に供する目的で,19年11月から「教室文庫」が閲覧室に設置されたが,戦時中の混乱状態のためいずれも充分その成果を上げる事ができなかった。
昭和20年(1945)8月ようやく終戦を迎え,いち早く閲覧室の状態を元にもどすべく,電気スタンドおよび電燈の取付け等がなされ,10月1日より夜間の閲覧を開始したが,戦後の物資不足から暖房の設備はなく,また停電のため12月に入ってまたまた開室時間を4時迄に短縮しなければならなかった。
21年(1946)2月以後何度かにわたり連合国最高司令官の日本政府宛の覚書きにより,戦前とは違った面での禁止本についての伝達があり,出版物についての取扱い,宣伝用刊行物の没収等についての通達が幾度か流されて,その都度指示により処置された。一方学生の復員による急激な増加と,講義の充実にともない,法経の建物の一部を借用していた閲覧室も,今後経済学部の教室として使用されることになったため,21年(1946)5月末には本部2階西側の教官食堂を新たに閲覧室とすることに決定され,6月6日より開室した。
昭和22年(1947)には戦争時の人手不足からくる書庫内の図書の混乱を正すため,11月11日より12月10日まで欠本調査を行うことになり,書庫内図書の閲覧貸付を1カ月停止した。
図書館新館の工事も,前述の通り外郭のみで放置されて終戦を迎えたのであるが,図書館の完成についてはつとに羽田総長の最も心を痛めたところであって,終戦後における最悪の諸条件のもとで,取りあえず学生閲覧室と事務室等緊急を要する箇所の仕上げに着手され,昭和23年に至りようやく新館に移る運びとなった。
4 新閲覧室時代
昭和23年(1948)3月ようやく待望の新閲覧室に移転することができたが,設備はまだ不完全で,机・椅子等の備品はすべて旧閲覧室で使用していた古いものをそのまま利用したので,最初夢に描かれていた図書館とは大分違ったところがあった。しかし新図書館の2階にあるこの閲覧室は,広さ180坪余り,座席数は268あり,照明装置のみは京都で最初といわれるもっとも近代的な螢光燈が使用され,これまでの電燈と違って全く白昼のような明るさで,戦後の混乱時を経てきた学生や職員を充分に満足させたのであった。
10月には今まで階下に設置してあった「教育課程文庫」を2階閲覧室内に移し,閲覧室を一部区切って「市民閲覧室」とし,同文庫と共に本館蔵書を一般市民にも開放,本館創立以来の理想である参考図書館としての機能を発揮しようと志したのである。しかし一方前記の通り閲覧室と書庫との距離がはなれている関係上,在庫の図書を貸出しするにも手数を要するので,書庫からの出納は1日7回と定められた。それも人手不足のため昭和23年12月1日よりは,1日5回に制限せざるを得ないことになった。
また当時の図書購入費では新聞・雑誌の購入さえも充分に満たすことができず,閲覧室の教養書の棚には新刊書はほとんど見当らず,寄贈されたもの以外は利用されそうもない古い図書が,背中をさらしている状態であった。たまたまその頃,昭和24年(1949)1月より4回にわたりCIEの好意により巡廻文庫が送られることになって,見た目にも立派な新刊の洋書がずらりとならび,館員を大変喜ばしたのであった。
同年6月24日閲覧事務室の整備・完成を待って,出納事務はすべて閲覧事務室で行うことになり,図書類を移転し,閲覧室内には全部閲覧用の机と椅子が配され,フルに学生が利用できるようになった。しかしこのように閲覧室と閲覧事務室とを2分したため,両者の入口近くに各々監視が必要となって,閲覧の掛員が交代でこれに当らねばならぬことになった,その上25年(1950)よりは経済学部の図書に対する貸出手続も,本館で取扱うことになる等,人手不足のためそれでなくても繁忙な掛員は,ますます応接に忙殺される結果となった。クルーガー図書館が閲覧事務室の一部に仮設されていたのもその頃である。
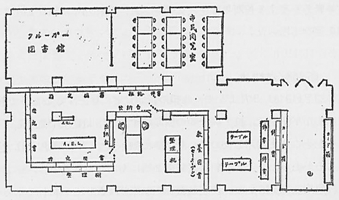 |
|
図書出納室平面図 昭和24年6月
|
図書の自然増加に比例して,カードケース等の増加は必然的であるが,その購入備付がこの10数年来極端に縮限されていたのと,人員が逐年縮少された結果,事務用カードのみを作成して,閲覧用カードまでは手がまわらなくなり,ために排列されていないカードの数が約3万枚,カードケースが無いために繰込みのできないまま放置されているものの数が5万枚に達していた。かくて学生は図書検索の鍵を全く失い,新刊書の購入杜絶の事実とあいまって,図書館に対する信頼感を失い,図書館に寄りつかなくなったため,図書館の利用法やその恩恵についても知る機会もなく,年が来れば卒業して学園を去るという有様であった。そこで閲覧用カードの整備充実が重大かつ焦眉の急を要する問題として要望された。
昭和25年(1950)には閲覧者の激増と共に,漸く新刊書の購入にも力を入れることになり,この新刊書を学生にPRする方法として「ライブラリー・ニュース」が考案された。これは新しく購入された図書を列記して,構内の各門の掲示板に張り出すもので,学生間に好評を受け,現在も本館掲示板だけにはこれを続けている。
天井の高い新閲覧室では螢光燈の性能を以てしても照明度がまだ不充分であったため,夜間の勉学に支障をきたすという声がしきりで,同年9月には電気スタンドが机上に取付けられた。新聞閲覧台も昭和11年旧閲覧室の火災の折に焼失して以来,新調されることなく,新聞は机上に置いて自由に閲覧させていた。これでは破損を生じる機会が多く,また学生の無断持出等もあったために学生から早急に新聞閲覧台の備付が要望されていた。
当時電力制限のため,市中一般では停電に悩まされることが多かったのであるが,学内だけはそれを免れていたので,特に夜間の閲覧者は激増し,そのため臨時措置として階下の講演室等を閲覧室として開放した。また教職員の内からも教職員専用の閲覧室設置に対する要望が高まり,昭和27年(1952)6月16日よりそれを開設することになった。教職員閲覧室は本館の2階,学生閲覧室と閲覧事務室との間にあり,夜間の照明についても充分意を用い,常に快適な条件のもとに読書できる設備がなされたのであったが,実際に開室してみると利用者は案外に少なく,施設不足のおりから現在では他に転用されている。
閲覧室・事務室等はこのようにしてどうにか新館に移すことができたが,書庫に至っては思うにまかせず,100メートル以上を隔てた旧書庫に図書は収められたままであったため,図書の出納能力は極度に制約を受けていた。昭和29年(1954)には夏期休暇を利用して学生閲覧室の床にリノリュームが張られ,照明の点についても螢光燈を天井に取りつけ,閲覧用の椅子も新式で軽快な移動性を有するものに取替え,以後逐年その計画が進行して400余の座席がくまなく利用できるようになった。
新書庫はエレベーター工事を残して昭和29年に一応完成を見た。翌30年(1955)には旧書庫に蔵置されている図書を新書庫へ移転させることになり,7月1日着手,アルバイト学生の応援により,館員総動員でこれに当ったが,エレベーターもなく,車も充分なものがなかったため,図書の運搬上げ下しの労はなみたいていのものではなかったが,全員の努力によって12月6日には予定通り普通書の和・洋1〜10門を全部運び終った。これにより1日数度の書庫への往復・運搬という重荷が一応取り除かれることになった。
同年10月5日には受入部数が100万となり,本館所蔵の「世界大思想全集哲学・文芸思想篇1」には,1,000,000という受入番号が押印された。蔵書に おいても設備においても逐年充実され,火災・戦争・戦後の混乱という受難のうち続いた時代を過ぎ,本館にもいよいよ明るいきざしが見え出した。
前年12月より着手した閲覧事務室内のカウンター工事も31年(1956)2月に完成,大理石による長さ13m余の立派なものができ上った。またこれと同時に着手した閲覧事務室の天井照明工事もほとんどでき上り,これまで照明不完全のため,図書の検索が至難であったが,これにより緩和されるようになり,また夏休みを利用して着手した閲覧事務室の間仕切り工事も11月15日には完成を見,カード室との区切りができた。それと前後して書架も新調されるなど,次第に整備が進んでいった。
閲覧事務室内に配架されている図書に対しては,戦後NDCによる分類が付されていたのであるが,これも書庫と同様の分類ラベルに張りかえ,事務の煩雑を緩和するようになった。また休暇中等を利用して,館員総出によりカードの繰込み作業を行ったのも30年(1955)頃からであり,これにより閲覧用カードの不備をかなり補うことができた。
かねて懸案となっていたマイクロフィルムによる文献複写の業務が,31年(1956)7月より実施されることになり,33年(1958)12月文献複写室が開室されるまで,閲覧事務室のカウンターにおいてマイクロ複写に対する業務を取扱った。
火災以後書庫と閲覧室とが遠く離れていたため,時間を区切って在庫図書を出納していたのであるが,新書庫も完成し,図書の移転も一応終り,エレベーターもでき上って,書庫の図書を常時出し得る状態になったので,昭和32年(1957)4月より時間制を廃止し,要求あるたびに出納するようになった。
同年8月〜9月にかけては,2階の廊下にリノタイルが張られた。また同年1月より施行された物管法に基き在庫図書全部の調査を実施することになり,7月10日〜9月7日を期限として館員総動員でこれに当った。
昭和25年4月以後廃止されていた毎月15日の図書整理のための休室日を32年9月以後復活し,完全な調査を行うことになり,毎月月末の1日は閲覧事務を停止して,オープン図書の調査および新刊図書の配架・整備等を行い,また春・夏・冬の休暇期間には一層くわしい整理や,模様がえを行うことになった。このため2・3年続けられた休暇中のオープン図書の貸出は中止することになった。
32年10月17日には図書館利用者の実態調査を実施した。
一方図書館の運営面については,「京都帝国大学附属図書館規則」の部分的な変更は,何度かなされたのであったが,今や世の中は大きく回転し,従来のものでは運営に支障をきたすことも往々起るので,時代に即応したものに改正され,昭和32年12月17日より施行した。これに伴って閲覧事務室においても一部書式や取扱いを変更しなければならなくなった。
昭和34年(1959)は本学蔵書が200万冊を突破した年で,200万冊目は34年2月26日受入の「蘇悉地羯羅経略疏」である。同年12月11日には本館も創立60年を迎えた。60周年の祝賀式は閲覧室を宴会場に使用した。前にも記した通り創立当時は,図書館閲覧室の他には一時に多人数を収容できる施設が学内になかったため,式典・会場等に利用されることが度々であったが,本部大ホールの新設以後はたえて無かったことで,閲覧室がこのような催しに使用されたのは何十年ぶりであろうか。
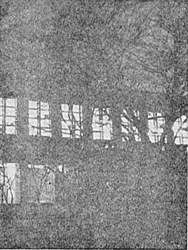 |
|
閲覧室夜景
|
現在の閲覧事務室には,普通図書約4,000冊, 辞書類約2,000冊, 合計約6,000冊が左右にわかれて配架されている。また雑誌架には和雑誌約600種,洋雑誌400種余り,合計1,000余種がならべられている。戦後物資不足のため不可能であった雑誌・新聞類の製本,破損図書の修理も28年頃より逐次できるようになり,特に近年は計画的に作業を運ぶようになったため,34年の分を例に上げて見ても,和雑誌約200種, 600冊余り,洋雑誌約130種, 250冊余り,修理本和書30冊,洋書70冊合計約1,000冊が製本・修理されている。
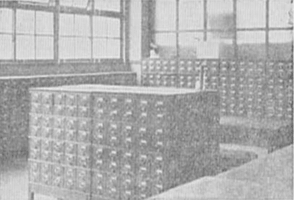 |
|
閲覧用カード室
|
現在のカード室には本館の分類カード(和・洋共),および和書については昭和28年以後の著者名目録および27年以後の書名目録がABC順(訓令式)に配列されており,洋書については著者目録があり,その他法学部および経済学部の分類目録や,特殊文庫目録が備付けられている。このカードについてもまだ不備な点が多く閲覧者のために早急に完備されるよう望まざるをえないし,設備の点についても,新館へ移転した当時の図書館からみれば漸次改善され,相当充実してきたのではあるが,まだまだ今後にまつところが多い。