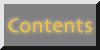
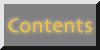 |
第1節 出版
本館が蔵書の質においても,また量においても国内屈指の図書館であることはいうまでもないが,とくに質においては重要文化財をはじめ多くの貴重書を架蔵している。本館はこれら学術上の価値の高い蔵書を学内外に広報し,研究者の利用に供するため,図書館案内をはじめとして,蔵書目録・影印本等を刊行してきた。以下本館刊行の出版物を刊行年順に列記し,それぞれについて簡単な説明を試みよう。
京都帝国大学法科大学欧文図書目録 (Katalog der FremdsprachigenBucher in der Bibliothek der Juristischen Fakultat der KaiserlichenUniversitat zu Kyoto) 明治37年3月刊(1904)
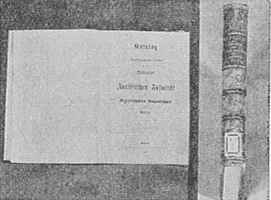 |
|
京都帝国大学法科大学欧文図書目録
|
京都帝国大学図書館案内 明治41年4月刊
図書館創立当初より明治40年2月までに図書,標本等を寄贈した全国各地の個人,または団体に配布した本館の案内書である。本文28頁,口絵図版2葉の片々たる小冊子に過ぎないが,明治41年4月の刊行で,本館最初の案内書である。
本書刊行の趣旨,およびその内容は,次の序文によっておおよそ想像することができる。
此案内ハ図書寄贈者諸氏ニ贈ランガタメ編纂セルモノナリ。諸氏モシ之ニヨリテ寄贈ノ図書ガ本館ニ入リテ後如何ニ処理セラルルカヲ知リ玉ハバ即幸甚シ
沿革,建築,閲覧,貸付,分類,目録等の14項目を収録し,特に寄贈芳名の一項目を設けている。本書は寄贈者の厚意に対する答礼用として刊行されたものであるが,また本書の配布によって,本館の活動情況を広く江湖に宣伝しようとするPRをかねたものであった。
京都帝国大学外国逐次刊行書目録 明治42年6月刊
本学法学部,医学部,文学部,理工科学部の各部局と本館が架蔵する外国逐次刊行書の綜合目録で,明治42年6月の刊行である。本学創立以来明治43年3月末までに受入れた,欧米の逐次刊行書を収録している本学最初の逐次刊行書目録でである。
なお本書の欧文標題は“List of ForeignPeriodicals received at the Kyoto Im−perial University”である。
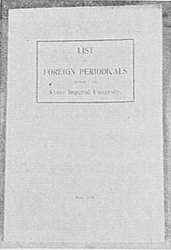 |
|
京都帝国大学外国逐次刊行書目録
|
大典奉祝陳列品目録 大正4年11月刊
大正天皇即位の大典を奉祝するため,大正4年11月12,13日の両日,本学文科大学陳列館および本館の尊攘堂において,人文科学に関する稀書,珍籍,標本等の展示会を開催した。本書はその展示図書および陳列標本の解題目録である。
昌平叢書 682巻246冊 大正6年刊
昌平叢書は岩崎久弥男爵が大正6年に寄贈した,島田蕃根旧蔵の昌平黌官板板木6,565枚を板下として,京都の山田聖華房(茂助)に摺刷させた36種246冊の漢籍の叢書である。30部を限定出版した。
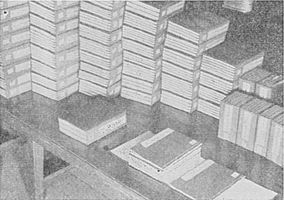 |
|
昌平叢書
|
京都帝国大学附属図書館洋書目録 大正8年3月刊
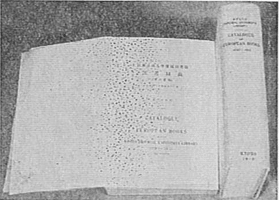 |
|
京都帝国大学附属図書館洋書目録
|
尊攘堂遺品仮目録 昭和3年11月刊
明治28年8月12日,品川弥二郎子爵が自ら編成浄書した尊攘堂蔵品目録の原本を翻刻したものである。原本の巻首より第114号までは子爵の自筆であるが,第115号以下は余人の筆である。原本の第161号より第682号までは書籍の部であるが,その多くは明治以後の印本であるため,本目録には収載されていない。
なお本目録は昭和3年10月の尊攘堂特別祭典に伴う尊攘堂蔵品大展観を機として発行されたもので,祭典参列者,来観者に尊攘堂蔵品の案内書として配布したものである。
尊攘堂誌 昭和3年11月刊
吉田松陰歿後70年に当る昭和3年10月27日,吉田松陰,品川弥二郎両先賢および勤王諸家を祀る大祭を,尊攘堂において執行した。時あたかも大典期間であったため,秩父,高松両宮をはじめとして滞洛中の朝野名士多数の参列があり甚だ盛儀であった。
しかし昭和3年は尊攘堂創立以来40余年を経過し,尊攘堂の詳しい由来や沿革を知る者はほとんどなかった。尊攘堂保存委員会はこのことを遺憾とし,堂の由来,祭典,蔵品および子爵の略伝等の執筆を本館の金子正道司書に委嘱した。この要請に答えて金子司書が執筆編纂したものが本書である。本書は本文28頁の小冊子に過ぎないが,尊攘堂の内容が簡明に紹介されている。
なお昭和6年9月「尊攘堂補遺」が刊行されたが,本文6頁のパンフレットである。本書は同年5月東伏見宮大妃殿下が尊攘堂に来臨されたことを記念して刊行したものである。
尊攘堂遺墨集 昭和3年11月刊
昭和3年11月18,19日の両日尊攘堂の特別祭典を行い,その際蔵品を展示し,特に祭典に参列した来賓の諸士に頒布するために,尊攘堂保存委員会が刊行したものである。編纂は本館の山鹿誠之助司書官と市村有済嘱託が担当した。
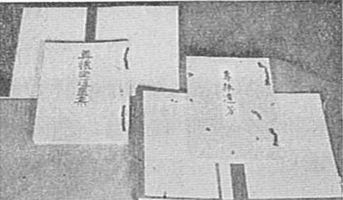 |
|
左 尊攘堂遺墨集 右 尊攘遺芳
|
台覧品目録 昭和3年11月刊
昭和3年11月18日執行した尊攘堂大祭の前日に当る17日,秩父宮,同妃,高松宮,ならびに賀陽宮,同妃五殿下が尊攘堂において勤王志士の遺墨を台覧された際贈呈した出品目録で,出陳品名を収録している。
有栖川宮熾仁親王筆「尊攘」二字の額他27点を掲載した本文4頁のパンフレットであるが,特製の紙を用いて結綴とし,台覧の案内として特に謹製したものである。
満蒙関係図書目録 昭和7年8月刊
本館所蔵の満洲,蒙古に関する文献目録で,本学の各学部,教室,研究所等に架蔵のものは含まれていない。収載範囲は本館創設以来昭和7年4月現在までに受入れられた和漢図書である。昭和7年以降の受入図書についても,追補続刊を予定していたが,ついに実現を見なかった。謄写刷55頁の質素な小冊子に過ぎないが,満蒙の政治経済,歴史地理,宗教教育等,すべての分野におよび,満蒙研究の一参考資料である。
尊攘堂之由来及年譜 昭和12年10月刊
昭和12年10月の尊攘堂大祭に当り,その創立50週年を記念するために刊行された本文6頁,年譜10頁,図版2葉の小冊子である。
本書は「尊攘堂の由来」と「尊攘堂五十年譜」の2編よりなり,「尊攘堂の由来」は昭和3年11月大祭執行の際刊行した「尊攘堂誌」を集約補修したものである。また年譜は尊攘堂の重今事件と,吉田松陰,品川弥二郎両先賢に関する主要事項を摘録したものである。題簽は羽田亨館長が揮毫し,編纂は本館の金子正道司書が,尊攘堂委員の委嘱を受けて担当した。
京都帝国大学附属図書館 案内 学生用 昭和13年3月刊
本館案内書は明治41年4月1日始めて刊行されたが,30年を経た昭和13年3月,「京都帝国大学附属図書館 案内 学生用」が刊行された。最初の案内書は図書館の現況を報告し,あわせて本館の活動の宣伝広報を目的としたものであるが,本書は全く前者とはその趣きを異にし,学生のための図書館利用の手引用である。内容は,本館の沿革略,案内,および附表の三部からなり,案内は(1)図書の種類,(2)館内規律,(3)仮閲覧室,(4)第2閲覧室,(5)貸付および書庫検索の5項目を内容としている。附表には分類表その他がある。
本案内書は本文に多少の増補修正を施して,昭和15年まで,3年継続刊行して学生に配布し,本館利用の伴侶とした。この案内書は吉田孫一司書官の企画で,その執筆編集も,主として同人の手になるものである。
昭和16年以後は,本学発行の「学生便覧」中に吸収され,その後昭和34年「京都大学附属図書館要覧」が出現するまで,その刊行を中絶した。
京都帝国大学附属図書館和漢書目録 第1総記 昭和10年末現在 昭和13年3月刊
大正8年刊行の本学所蔵洋書目録に対する本学所蔵和漢書目録の刊行が,早くより学内外より待望されていた。本館においても全学的な和漢書綜合目録の重要性を痛感し,すでに大正13年よりを和漢書綜合目録の編成を企画し,その実現に努力したが,容易に目的を達することができなかった。しかし昭和9年5月よりいよいよ「京都帝国大学附属図書館和漢書目録 第1総記」の編纂に着手した。
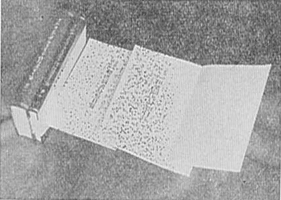 |
|
京都帝国大学和漢書目録 第1〜第4
|
京都帝国大学附属図書館和漢書目録 第2理学 昭和12年末現在 昭和14年12月刊
昭和13年3月刊行の「京都帝国大学附属図書館和漢書目録」に引続いて,同年6月理学部門の目録の編成に着手した。翌14年5月中旬には原稿の増補校合等その整理を終り,印刷に着手して9月中旬本文の校了,索引の作成を終り,12月和漢書目録第2理学を刊行した。本書は本文283頁,書名索引55頁で,昭和12年末現在の本学所蔵の理学に属する和漢図書を収録している。なお昭和12年2月山鹿誠之助司書官の退官により吉田孫一司書官が新たに本目録の刊行を主宰し,山本辰一,柴田清,藤田至善,山元一郎が編纂を担当した。
京都帝国大学附属図書館報 第1〜5号 昭和15年7月〜10月刊
昭和15年7月「京都帝国大学附属図書館報」第1号を刊行し,本館新着図書の速報を主とし,閲覧統計・報告等を載せ,学内各部局に配布した。この館報は謄写刷で,7月15日第1号を発行し,学内各方面からその発展を期待されていたが,支那事変による物資欠乏等の事情もあって,同年10月わずかに第5号をもって中止された。
皇紀2600年記念 尊攘堂誌 昭和15年10月刊
昭和15年(1940)は皇紀2600年に当り,また3年毎に執行される尊攘堂大祭の年であり,また本年の大祭は旧祭典委員から本学が引継いだ最初の年であった。
時あたかも第2次世界大戦の前夜で,国家総力を挙げて戦うために,愛国精神の昂揚が最も要請された時代であった。このため殉国志士の顕彰を本旨とする尊攘堂の設立の由来を語る尊攘堂誌を刊行して,国民精神の作興に資せんとしたのである。
本書は昭和3年刊行の尊攘堂誌と同一内容であるが,巻末に昭和12年刊行の「尊攘堂之由来及年譜」中より重要事項を抜萃して編成した「年譜」を添付している。
雁の草子 昭和15年11月刊
昭和15年皇紀2600年を記念して,影印頒布会を組織し秘蔵の貴覯書「雁の草子」を影印複製して会員に頒布した。原本「雁の草子」は慶長7年(1602)6月に書写された天下の孤本である。近古小説のうちの異類物語で,雁の一生を擬人化した未刊の絵巻である。
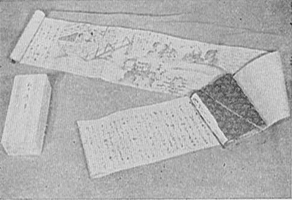 |
|
雁の草子
|
京都帝国大学和漢図書分類目録 第3工学 昭和14年3月現在 昭和16年3月刊
本目録は昭和14年刊行の「京都帝国大学和漢図書目録 第2冊理学」に続く第3冊工学である。昭和15年4月より収録書の選定,原稿記入等を開始し,7月より分類に着手,9月編纂事務を終り印刷を始めた。編纂開始より約1カ年後の昭和16年3月に刊行。前目録の書名「京都帝国大学附属図書館和漢書目録」を「京都帝国大学和漢図書分類目録」と改題した。
収録図書は昭和14年3月末現在の工学の属するもので,本文343頁,巻末に90頁の書名索引を附し検索に便している。さらに同年9月本目録に対して著者名検索の便宜を計り,別冊「著者索引」を刊行した。別冊「著者索引」は著者とその著者名のみを記載し,著者より本目録を索引する文字通りの著者索引であって,著者目録ではない。しかし和漢書目録に対する著者索引の刊行は,本館としては最初の画期的な試みであった。この企画は図書検索者の利用が書名索引より著者索引に次第に移行する新しい時代の要求に答えんとしたものである。
なお編纂は竹林熊彦司書官の監修の下に小川寿一,三田全信,赤松恭一郎,村上千秋,今井俊子が担当した。
尊攘遺芳 昭和16年5月刊
本書は別冊「尊攘堂誌」と共に紀元2600年記念事業の一つとし編纂されたもので,先賢諸士の遺墨遺品その他約90点の図版を収載している。体裁はだいたい昭和3年11月刊行の「尊攘堂遺墨集」によっているが,同書収載の図版「吉田松陰画像」の外は本書に再録することを避け,本書収載の図版はすべて新しく選定したものである。題簽は本学総長羽田亨博士,編纂は本館嘱託山鹿誠之助,金子正道の両人が担当した
。
旭江文庫目録 昭和16年9月刊(Catalogo della Collezione Dante−sca donata da Giukici Oga)
武田製薬株式会社員大賀寿吉氏の旧蔵旭江文庫の目録で,新村出館長の監修の下に,黒田正利嘱託を編纂主任として本目録の編成に着手した。谷口寛一郎,城戸善一,佐々木乾三,木寺清一各司書は協同して編成を分担し,同年九月印刷完了,同10月刊行された。なお本目録の出版については京都日伊協会会長田中博氏多額の出版費を受けた。ここに氏の厚志を追記して,感謝の意を表したい。
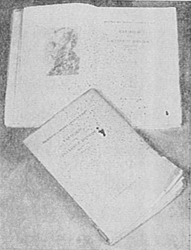 |
|
旭江文庫目録
|
車僧草子 昭和16年11月刊
本館内の影印頒布会は昭和16年11月本館所蔵の稀覯書「車僧草子」1帖を影印複製して,再び会員ならびに学界におくり好評を博した。本書の用紙は先の複製本と同じく,越前五箇荘産の別漉を使用し,玻璃版数度の彩色刷によって,原図の奈良絵をほうふつさせる等,原本の風趣を最大限に再現するようにつとめた。装幀等の造本においても,また納本箱等の意匠においても,京都の特殊工芸の粋を集めて製作した。
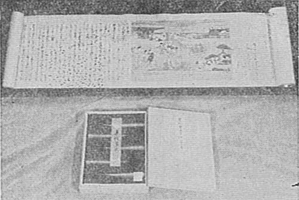 |
|
影印本車僧草子
|
京都帝国大学和漢図書分類目録 第4医学,附富士川本目録 昭和12年8月現在 昭和17年7月刊
本目録は前3部門に引きつづいて刊行された第4冊医学部門で,昭和13年10月編纂に着手し,同17年7月,5カ年の長年月を費して,ようやく完成したものである。本文355頁,書名,著者両索引ともで計494頁,昭和13年3月現在の目録である。
本目録の完成がこのように長期にわたったのは,富士川文庫約9,017冊の収録編成に,多大の時間と労力を消費したためである。富士川文庫は日本医学史研究の最も貴重な根本資料として,学内外の学者,篤志研究家に重視され,その印刷目録の出現は早くから待望されていたものである。そのため本目録中より富士川文庫を抽出して,別本の目録1冊を編成した。すなわち「京都帝国大学附属図書館富士川本目録」である。本目録ならびに「富士川本目録」の編纂は,竹林熊彦司書官の監修の下に,柴田清,小川寿一両司書が主として編纂に当り,館員赤松恭一郎,今井俊子等が協力した。なお昭和16年2月より
水梨弥久,鈴鹿蔵両司書および館員青山清が,第4冊医学に引続き第5冊として農学部門の編纂に着手し,同19年1月収録図書の原稿記入と,その項目分類を終了し,印刷に着手する一切の準備を完了した。しかし時あたかも終戦前の最悪の時期に当り,その刊行を見るに至らず,編纂者の3ヵ年の労苦も水泡に帰した。しかし原稿は分類別に整理されて保存されている。
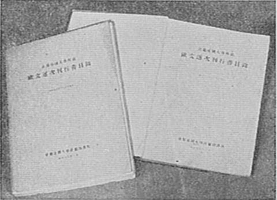 |
|
京都帝国大学所蔵欧文逐次刊行書目録
|
国女歌舞妓絵詞 昭和23年3月刊
奈良絵本「国女歌舞妓絵詞」は本館の最も誇りとする貴覯書の一つで,大正3年本学の所蔵に帰した。同年本学教授藤井乙男博士によって考証され,その価値を坪内逍遙博士に称讃され,諸学者の注目するところとなり,「大日本史料第12篇21」に収載された。元来奈良絵本の絵はおおむね粗雑であるが,これは頗る巧みな筆致である。絵も古雅で,詞書の書体も優美である。歌舞妓図として伝存するものの内,梅原龍三郎氏蔵(中村福助氏旧蔵)のものとならんで,歌舞伎発達史の研究資料としても,また日本美術史の参考資料としても,極めて貴重なものである。昭和26年3月,本書を影印複製し,和英両文の別冊1冊を添えて公刊した。複製に当っては,成立年代を慶元年間と推定せられる原本の古雅と風趣の復元に最も意を用い,印刷技術の粋を集めた。ただ別冊解説の口絵に原色版1葉を付した外は,本文の挿絵にまで原色刷を用いることのできなかったことは甚だ遺憾である。
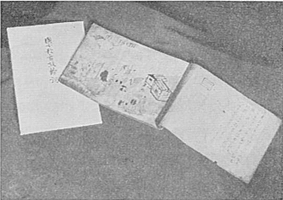 |
|
国女歌舞伎絵詞
|
官板李長吉歌詩 昭和27年8月刊
大正7年昌平黌官板の板木を摺刷して「昌平叢書」63種を30部限定刊行したが,昭和28年8月「李長吉歌詩」1種3巻を本叢書中より選んで重印した。
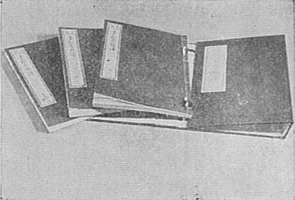 |
|
李長吉歌詩
|
医学関係図書展観目録 昭和30年4月刊
昭和30年4月1日より5日まで本学で挙行された第14回日本医学会総会に際し,同会と共催した「医学関係図書展示会」に出陳の展示図書目録である。
出陳図書はわが国医学の発展に寄与した平安朝より明治維新前に至る和漢の名著で,主として富士川文庫中より選出した珍籍逸書である。なお本学には新宮,山脇,江馬,高橋諸氏寄贈のオランダ書100余点の収集があるが,その内の江馬蘭斉(1747〜1838),および新宮涼庭(1787〜1854)の手沢本の1部をも展観し,成立年代順に排置した。本目録も展示図書の序列に従って収録し簡明な解説を附している。本目録の編纂と解説は,日本医学会の委嘱を受けて鈴鹿蔵和漢書目録掛長が担当した。
京都大学附属図書館覧要覧 昭和33年4月刊
戦中戦後の空白と虚脱をようやく克服した本館は施設の増強,事業の拡大等に伴い,本館規程類の改正,増補等をしばしば行ってきた。
本館はこの体質改善後の新しい現状を,学内外の利用者に広報することの必要に迫られ,昭和33年4月「京都大学附属図書館要覧」を刊行した。本書は昭和15年に刊行した「京都帝国大学附属図書館案内 学生用」とは少しく内容体裁を異にし,単なる学生に対する図書館利用の案内書ではなく,むしろその題名が示すが如く,昭和32年末の本館現勢の集約的報告というべきものである。本書は岩猿敏生事務長の企画編纂によるもので,本文39頁の小冊子に過ぎないが,本館運営の諸規程およびその施行細則等を収録し,本館利用者の指針ともなりうるよう配慮されている。
孝子伝 昭和34年12月刊
昭和34年12月11日は,本館が明治32年(1899)に創立されてより満60周年に相当する。この日を記念し,記念事業の一つとして,清家文庫中の「孝子伝」2巻1冊を選んで200部を影印複製し,内外の学界に送った。
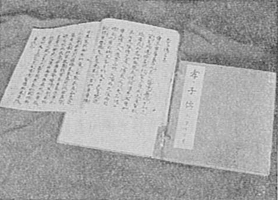 |
|
孝子伝
|