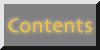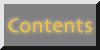第5章 尊攘堂
図書館の西北に位置する灰色の洋館の建物が,附属図書館の尊攘堂である。京都に大学を興し,尊攘堂を設けようとした最初の人はかの吉田松陰であったが,その志を果さずに刑死した。しかし,刑死の1週間前,すなわち安政6年(1859)10月20日,江戸伝馬町の獄中より松陰は書を門下の入江子遠(通称丸市)に寄せ,その志を述べた。
京師に大学校を興し,上天子,親王,公卿より下 武家,士民まで入寮寄宿等も出来候様致し,乍恐,天朝の御学風を天下の人々に知らせ,天下の奇才異能を,天朝の学校へ貢し候様致候得ば天下の人心一定仕るに相違なし云々
 |
|
尊攘堂
|
不幸にして子遠もまた元治甲子の難に殉じたため,その遺志は空しく20余年間埋もれていたのである。ところが偶然のことから子爵品川弥二郎が,この書状を水戸で得て感慨に堪えず,ついに独力をもって松陰の遺志を果さんと決心し,明治20年2月独都ベルリンより帰朝するや,3月直ちに京都高倉通錦小路上る元典薬頭三角氏の別邸(約700坪)を買入れ,これに修理,増築を加えて,その中に維新前後の勤王の志士の霊を祀った。同時に志士の殉難事蹟に関する史料・遺墨・遺品等を収集して毎年壮厳なる祭典を営み,一般公衆の参拝を許し,蔵品を縦覧せしめ,先賢追懐の意を尽した。子爵は日常多端の身をもって毎年これを継続執行すること10余年の永きにおよび,また四方の有志もこの挙を伝聞して,志士の遺墨・遺品を寄贈し来るもの相継ぎ,その数千数百点の多数に達したので,子爵はこれら貴重な記念品を一家の私物とせず,京都在住の有志中より尊攘堂保存委員20余名を選定して会員とし,将来のことを依託した。しかし蔵品の漸次増加するにともない,堂内は次第に狭隘となり,建物も80有余年を経たため,腐朽の箇所も少なくなく,また市街の中央にあって人家櫛比するため火災等のおそれもあったので,子爵は保存委員と計り,永久に維持保存の方法を考究中であったが,不幸にして病のため明治33年2月26日遂に逝去された。そこで保存委員松本鼎等は子爵の嗣子弥一,および子爵野村靖等と協議の結果,所蔵品全部を京都帝国大学附属図書館に寄贈し,かつ同学内に尊攘堂を新築することに決定し,その旨をただちに文部大臣に提出した。
| |
(前略)吾輩等熟議の上,諸書類を整理し,尊攘堂及諸蔵品共之を御省に獻じ,京都帝国大学図書館の附属と為し,蔵品を陳列し時々之を公衆へも拝覧せしむるに於ては永久保存の道立つのみならず,先師吉田松蔭,故品川弥二郎の遺志の如く士気を作興し,学風を振起するの一端とも可相成儀と奉存候。御省に於ても,其情況を御採納あって,前陳の通り御許可被下度,然る上は大学指定の地へ尊攘堂及文庫等を建築し相渡し可申,其方法の如きは大学総長と協議し其指揮に依り可申,此段奉懇願候也。 |
翌34年2月21日文部大臣松田正久はこれを許可して,京都帝国大学総長木下広次博士をして,その寄附を受理せしめた。
明治30年6月京都に帝国大学が建設せられ,数年たらずで尊攘堂がその構内に新築され,蔵品全部を収容して永久に保存の途が立てられるに至ったことは,まことに奇しき縁ともいうべきで,ここに松陰の宿志は達せられ,品川子爵の企図も始めて成就するに至ったのである。
明治34年6月に至り,品川弥一,野村靖,松本鼎および品川家の親族山県伊三郎,山根正次,中村精男,平田東助,および島地黙雷氏などの外,尊攘堂委員阿武素行氏以下31名は連署をもって,自今毎年10月27日(松陰忌)および2月26日(品川忌)の両日,尊攘堂を借受け,両先賢始め勤王諸烈士の祭典を営むこと,および同時に蔵品を陳列して,公衆に展覧せしめることの許可を京都帝国大学に改めて出願し,木下総長の許諾を得た。そこで前記諸員は翌35年3月会合協議の上,規約を設け,祭典資金として金3,000円を積み立て,毎年その利息をもって春秋2回の祭典費にあてること,その他祭典執行に関する詳細を協定し,この規約は委員歿後もその相続者が相承け,永くその履行に当ることを誓約した。この約定書に記名調印した委員は
子爵 野村 靖 子爵 品川 弥一 品川家親族 山県伊三郎
同 山根 正次 同 中村 精男 同 男爵 平田 東助
島地 黙雷 (以上東京)
松本 鼎 阿武 素行 伊藤 陶山
林 新助 田中治兵衛 今井貞次郎
八木 良則 深見伊兵衛 西谷 成造
伊藤平左衛門 飯田 新七 清水六兵衛
池田 清助 並河 靖之 西村総左衛門
川島甚兵衛 斉藤卯兵衛 田中 利七
佐々木清七 [辻]信次郎 [辻]忠三郎
[辻]忠四郎 安盛善兵衛 川端 弥七
内藤小四郎 竹村弥兵衛 藤村岩次郎
綿貫 吉秋 吉田 佐吉 鬼頭 玉汝
神坂 吉隆 森 勇太郎 (以上京都)
明治36年4月大学構内の尊攘堂が竣工し,蔵品1,249点が移搬されることになり,木下総長は寄贈品を島館長に命じて,特別に保管せしめることとした。館長は安全を期するため,平時はこれを図書館内の貴重書庫に収蔵し,必要に応じ随時これを堂内に陳列することとした。その後毎年2回の祭典を年1回4月第1土曜日に執行することに改めた。さらに大正10年より毎年秋季10月27日松陰忌に小祭を営み,3年目に大祭を行うことに改め,保存委員を単に祭典委員とした。そして例祭小祭当日は吉田,品川両先賢(各木像安置)を始め,勤王諸家の霊を祀り,総長をはじめ,学部長,図書館長,教職員,旧尊攘堂委員等が参列し,大祭の際には前記の外,朝野の名士を招待して講演会を開き,遺品・遺墨の展覧会を催し,学内はもちろん一般の観覧を許した。また当日は参列者に志士遺墨にちなむ記念品を贈呈することにした。
昭和12年はあたかも尊攘堂創立50周年に当り,盛大に大祭を執行したが,たまたま支那事変の勃発を見,時局はますます重大となったので,祭典委員は諸般の事情に鑑み,その資金を京都帝国大学に寄附し,自今大学側において適当な方法により,祭典を主催することとなった。そして昭和15年10月の大祭は,大学の主催による第1回の大祭であった。
ついで昭和18年10月には大学による第2回大祭が,岡部文相を迎えて厳粛に執行されたが,維新勤王烈士の遺品・遺墨を一般に公開する事を要望する声が学内外に高まったので,この要望に応ずるため規定を設け,11月より公開小展観を,7,12月を除いて毎月27日の松陰忌の正午より4時まで実施することに決定し,第1回を開催した。翌19年6月戦局はますます不利な形勢を示すに至ったため,蔵品中の貴重品を保津川,嵯峨方面に疎開し,さらに昭和20年には1月,3月の小展観は警戒警報発令のため中止となり,終に8月わが国の無条件降伏により,尊攘堂前の石標(皇紀2600年記念)は除去され,同堂は図書陳列館と改称された。
| |
長門尊攘堂 山口県長府に存し,品川弥二郎の遺嘱により,桂弥一の主唱で,毛利家その他の援助を得て,財団法人を組織し,昭和6年起工,同8年に竣工した。京都の尊攘堂と同じく,志士の遺品,遺墨類が陳列されている。 |
尊攘堂年譜
|
明治20年2月 |
子爵品川弥二郎ドイツより帰朝す |
|
3月 |
弥二郎先師吉田松陰の遺志をつぎ,京都市高倉通錦小路に尊攘堂を創設す。以後毎年殉難志士の祭典を営む |
|
21年8月26日 |
弥二郎尊攘堂において甲子殉難志士25年祭を執行す |
|
25年 |
有栖川宮熾仁親王「尊攘」額御染筆 |
|
33年2月26日 |
弥二郎逝去年58,昇叙正二位勲一等(旭日大綬章) |
|
10月 |
委員野村靖,松本鼎,品川弥一,阿武素行等協議の結果蔵品ならびに新築尊攘堂を京都帝大に寄附すべく,その旨を文部大臣に申請す |
|
12月 |
尊攘堂址は田中源太郎譲り受け銀行集会所となす |
|
34年2月21日 |
文部大臣松田正久,前記の申請を許可し京都帝大をして寄贈品を受理せしむ |
|
6月 |
品川弥一等委員は連署して毎歳2回(松陰忌・品川忌)尊攘堂を借受け,祭典を執行することを京都帝大に申請し許可さる |
|
7月 |
山県有朋筆「尊攘堂」額成る |
|
35年3月 |
松本鼎以下委員会合,規約を設け祭典資金3,000円を醵出し,毎年その利息を以て祭典費に当つることを決定す |
|
|
尊攘堂新築工事開始 |
|
夏 |
尊攘堂内に安置すべき松陰・品川両先賢の木像2体(疋田雪州作)成る |
|
36年4月 |
尊攘堂新築工事落成 |
|
|
松本鼎外2名の代表委員より吉田・品川両賢の木像2体を京都帝大に寄附す |
|
5月 |
昭憲皇太后京都帝大行啓,尊攘堂遺品台覧さる |
|
6月 |
毎年2回の祭典を年1回(4月第1土曜日)執行することに改む |
|
37年4月 |
例祭執行 |
|
6月 |
中沢岩太寄贈の松岡寿筆品川子爵肖像画成る |
|
38年4月8日 |
例祭執行 |
|
39年4月 |
例祭執行 |
|
7月 |
旧尊攘堂建物は平井熊三郎買受け,伏見堀内村に移築す。旧庭園は現在銀行集合所内に保存せらる |
|
40年4月13日 |
例祭執行 |
|
41年4月11日 |
例祭執行 |
|
10月16日 |
野村靖松陰自賛画像外11点を寄贈す |
|
|
大森鍾一(京都府教育会長)松陰の「山河襟滞」詩碑を岡崎公園に建つ |
|
42年4月10日 |
例祭執行 |
|
43年4月9日 |
例祭執行 |
|
44年4月8日 |
例祭執行 |
|
45年4月 |
例祭執行 |
|
大正2年4月12日 |
例祭執行 |
|
5月 |
川島元次郎に蔵品を調査報告せしむ |
|
3年4月11日 |
例祭執行 |
|
4年4月10日 |
例祭執行 |
|
5年4月8日 |
例祭執行 |
|
6年4月1日 |
例祭執行 |
|
5月9日 |
本年度より蔵品10点を限り6カ月間山口県教育博物館に貸付す |
|
11月 |
大正天皇京都帝大に行幸,図書館尊攘堂において標本,古文書を天覧さる |
|
7年4月12日 |
例祭執行 |
|
8年4月12日 |
例祭執行 |
|
9年3月25日 |
産業組合主催にて15日間萩町に品川子爵遺物展覧会開催につき蔵品28点を出展す |
|
4月10日 |
例祭執行 |
|
10年3月12日 |
京都在住の委員ならびに大学側係員会合協議の結果,自今10月27日(松陰忌)を例祭日となし,3年目に大祭執行のことに改定す |
|
10月27日 |
例祭執行 |
|
11年6月 |
久邇宮邦彦王,同多嘉王妃殿下京都帝大創立25周年記念式に台臨,蔵品の屏風を台覧に供す |
|
10月27日 |
例祭執行 |
|
11月15日 |
貞明皇太后台臨,陳列の蔵品を台覧 |
|
12年10月27日 |
大祭執行の年であったが関東大震災のため明年に延期し例祭を執行,自今神坂雪佳,今井貞次郎を常務委員となす |
|
13年5月16日 |
皇太子(摂政宮)殿下東山文庫台臨の機に京都御所内に先賢遺墨展観あり,蔵品数点を陳列台覧に供す |
|
10月27日 |
大祭執行,真木和泉の後裔真木長時参拝す |
|
10月27日 |
大祭執行,真木和泉の後裔真木長時参拝す |
|
14年10月27日 |
例祭執行,伯爵寺内寿一等参列 |
|
15年10月27日 |
例祭執行 |
|
11月19日 |
男爵田中義一等参拝 |
|
昭和2年10月27日 |
本年の大祭は明年の御大典期に延期することとし例祭執行 |
|
3年11月17日 |
秩父宮,同妃,高松宮,賀陽宮,同妃5殿下遺品台覧 |
|
18日 |
松陰70年祭を兼ね大祭執行,田中首相以下多数の朝野名士,志士遺族参列,午后は記念講演,遺墨展等を開催盛会を極む |
|
25日 |
久原房之助参拝 |
|
|
「尊攘堂遺墨集」「尊攘堂誌」「尊攘堂遺品仮目録」刊 |
|
4年10月18日 |
東京青山会館における安政大獄殉難志士遺墨展覧会に蔵品数点出展す |
|
27日 |
例祭執行 |
|
5年4月16日 |
大島健一参拝 |
|
5月18日 |
開学記念日に当り堂内に蔵品を陳列し一般の観覧に供す |
|
10月27日 |
例祭執行 |
|
6年5月19日 |
東伏見大妃殿下,遺品台覧 |
|
9月 |
山口県長府町桂弥一は品川弥二郎生前の依嘱により長門尊攘堂建設に着手す |
|
10月27日 |
大祭執行,松陰門人渡辺蒿蔵代(末女八百子)萩より参拝す |
|
7年1月23日 |
山口県知事長門尊攘堂設立を認可す |
|
10月22日 |
桂弥一上洛参拝 |
|
27日 |
例祭執行 |
|
8年6月 |
有栖川宮熾仁親王御染筆「尊攘」額を複製して長門尊攘堂に贈る |
|
8月22日 |
蔵品若干長門尊攘堂貸附に決す |
|
10月20日 |
長門尊攘堂ならびに万骨塔竣成式を挙ぐ |
|
27日 |
例祭執行,伯爵清浦奎吾参拝 |
|
9年3月7日 |
松岡洋右参拝遺墨観覧 |
|
10月27日 |
元治甲子70年祭をかね大祭を執行。伯爵東伏見邦英始め来賓多数参列,午後は久邇宮多嘉王,同妃両殿下遺品台覧,志士遺族男爵 寺島敏三,杉道助(民治孫)ならびに徳富蘇峯夫妻等参拝,蔵品展開催 |
|
10年3月26日 |
子爵毛利元秀夫妻参拝 |
|
7月 |
長谷川為治より志士の遺墨4点の寄贈を受ける |
|
10月27日 |
例祭執行 |
|
11年10月27日 |
例祭執行 |
|
12年3月22日 |
尊攘堂創立50周年記念として岡崎公園内「山河襟帯」詩碑の位置表示石標を建つ |
|
5月28日〜30日 |
関東庁開設30年記念に当り旅順博物館に蔵品40余点を出展す |
|
10月27日 |
創立50周年記念大祭執行,蔵品展開催 |
|
11月1日 |
文部大臣侯爵木戸幸一参拝遺墨観覧 |
|
|
尊攘堂委員編「尊攘堂の由来及年譜」刊 |
|
13年3月29日 |
公爵山県有道,子爵野村益三,飯田新七,神坂吉隆,今井貞次郎 |
|
|
等委員代表は祭典基金5,000円を本学に寄附す。本学はその基金により以後祭典執行に当ることに決す |
|
6月6日 |
文部大臣男爵荒木貞夫来学遺品観覧 |
|
10月27日 |
例祭執行,霊山品川子爵墓前祭を営む |
|
14年10月27日 |
例祭執行,品川子爵墓前祭を執行す |
|
15年1月14日 |
国史普及会員子爵町尻量弘等約50名遺品観覧 |
|
3月 |
図書館改築の為尊攘堂を約15間西方に移築す |
|
5月16日 |
中華民国山東省長唐仰杜一行8名来観 |
|
9月19日 |
東北帝大総長熊谷岱蔵遺品観覧 |
|
10月 |
旧尊攘堂委員石標を尊攘堂前に寄附建設す。中山太一,杉道助より各500円寄附 |
|
27日 |
皇紀2600年記念大祭執行,蔵品展開催 新編「尊攘堂誌」刊 |
|
16年5月 |
「尊攘堂遺芳」刊 |
|
10月27日 |
例祭執行,墓前祭執行 |
|
17年6月18日 |
本学記念日につき尊攘堂遺墨遺品展開催 |
|
10月23日 |
例祭執行,墓前祭執行 |
|
18年6月19日 |
本学記念日につき尊攘堂遺品遺墨展開催 |
|
10月27日 |
大祭執行,遺品遺墨展開催,墓前祭執行 |
|
|
佐久間象山筆「自賛山水図」(中山太一氏寄贈)を複製頒布 |
|
11月27日 |
尊攘堂の公開小展覧を7,12月を除いて,毎月実施することに決定し,第1回小展観を行う |
|
19年6月11日〜13日 |
尊攘堂蔵品中の貴重品を保津川方面と嵯峨方面に疎開 |
|
27日 |
大部分の蔵品を疎開したので2流品を展観 |
|
9月27日 |
木像を安置せず小展観を行う |
|
10月27日 |
例祭執行,今回は特に清風荘において特別展開催,墓前祭執行 |
|
20年1月27日 |
警戒警報発令にて小展観中止 |
|
3月27日 |
小展観臨時に中止 |
|
7月17日 |
再疎開追加品目選定 |
|
8月21日 |
尊攘堂前の石標(皇紀2600年記念)撤去 |
|
9月6日 |
大覚寺に疎開中の蔵品を他に移すことに決定。長門尊攘堂に貸附中の蔵品を回収することに決す |
|
10月27日 |
例祭執行,墓前祭執行 |
|
昭和21年5月15日 |
本年の大祭は中止と決定 |
|
30日 |
疎開中の蔵品を点検収蔵す |
|
8月2日 |
尊攘堂蔵品の刀剣類の所持願を川端署に提出 |
|
26日 |
墓前祭のみ執行 |
|
11月29日 |
刀剣類の中4点は美術品の価値なしとして没収せられ,6点は返還される。 |
|
12月26日 |
上記6点の許可証交附せらる |