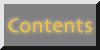
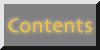 |
第2節 近畿図書館倶楽部(協議会)
関西文庫協会が京都近府県を中心に図書館活動を展開した後,大正2年にこの近畿図書館倶楽部の誕生を見るまで,京都における顕著な図書館活動はなにも見られなかったようである。
大正初期といえばやがて御大典記念として各所に公共図書館建設が見られようとする時期であり,それが全国の図書館運動にも新しい影響を与えるのであるが,それにさきがけた近畿図書館倶楽部結成の意義は大きい。発起は京都帝国大学附属図書館長新村出,京都府立図書館長湯浅吉郎,大阪府立図書館長今井貫一の三氏によってなされ,大正2年9月21日に第1回の総会(発会式)が京都帝国大学学生集会所において開催された。
当日の出席者は大阪府立図書館(9名),京都府立図書館(4名),奈良県立戦捷記念図書館(1名),和歌山県立図書館(1名),神戸市立図書館(1名),京都帝国大学附属図書館(13名)の29人であったが,まず京都帝国大学附属図書館の新村出博士が初回の当番幹事に選ばれ,開会の辞を述べたのち議長として次の数項を審議した。
|
1.本会ノ範囲ヲ奈辺ニ止ムベキカ(当分の間上記6館とし,ただ滋賀県立大津図書館および江北図書館に対して加入の勧誘をすることになり,その労を京都府立図書館が取ることになった) |
|
| 2.会合ノ時期ニツイテ(春秋の2回と決定した) | |
| 3.総会ノ記録其他諸般ノ報告等ハ如何ニ処理スベキカ(総会記事および報告事項等は,当番館にて謄写版にして各加盟図書館に配布することになった) |
ついで規約案が審議され,次の規約が成立した。
近畿図書館倶楽部規約| 1.本会ハ近畿地方ニ於テ現ニ図書館事業ニ従事セルモノヲ以テ組織ス | |
| 2.本会ハ主トシテ会員ノ親睦,各図書館ノ館務報告ノ交換ヲ目的トシ兼テ図書館事項ノ研究ヲナス | |
| 3.本会ハ毎年2回会員総会ヲ開キ懇話会食ス | |
| 4.本会ハ一図書館ヲ以テ当番幹事トシ一総会ヨリ次ノ総会マデノ間会務ヲ処理セシム 次回ノ当番幹事ハ総会ノ都度之ヲ定ム | |
| 5.館務報告ノ交換方法ハ会員協議ノ上之ヲ定ム | |
| 6.総会ニ於ケル会食ノ費用ハ出席会員ノ支弁トス |
当日午前中に決められた事項は以上であるが,正午以後については議事録に次のように報じられている。
| 時辰将サニ正午ヲ報ズ幹事休憩ヲ宣シ別席ニ於テ昼餐ヲ認ム数盃ノ麦酒ニ一座微醺ヲ潮シ快談縦横ニ湧ク既ニシテ食事終リ前庭ニ於テ記念ノ撮影ヲナス 午后一時又席ニ復シ新村幹事起テ次回ノ会合場所ヲ奈良市トシ幹事ヲ奈良県立戦捷記念図書館佐野早苗君ニ委嘱スル旨ヲ告グ 今井貫一君湯浅吉郎君交々起テ米国ニ於ケル図書館事業ノ実地見聞談ヲ試ミ伊達友俊君ハ本会経営ノ将来ガ常ニ平民主義ノ上ニ築カレ度シトシテ縷々抱負ヲ吐露セラル夫レヨリ各地図書館ノ実務取扱上ノ利害得失ニ関シ各員親シク談話ヲ交換シテ和気靄々ノ中ニ散会セシハ夕陽己ニ西山ニ没スルノ頃ナリキ |
第1回総会後春秋の2回に各館が順次当番館となり,ふたたび京都大学において開催されたのは第8回総会である。第8回総会は大正7年4月20日(土)午前10時に京都帝国大学本部階上会議室において開催された。
当日の参加者は大阪府立図書館(8名),京都府立図書館(2名),神戸市立図書館(3名),奈良県立戦捷記念図書館(2名),南都仏教図書館(2名),京都仏教大学附属図書館(1名),奈良吉野郡立図書館(1名),滋賀鵜飼文庫(1名),岸和田津田文庫(1名),彦根図書館(1名),京都帝国大学附属図書館(12名)の外に特別参加者として徳島県立光慶図書館(1名),石川県立図書館(1名)および東京帝国大学附属図書館(1名)を入れて37名であった。
まず司会者であった新村館長が開会の辞を大要次のように述べた。
| 前回和歌山県立図書館ニ於テ秋季第七回総会開催ノ際次回ノ当番幹事ヲ大阪府立図書館ニ依嘱セシガ其後今井館長ヨリ同館ハ今ヤ増築準備中ニシテ設備上差支アルヲ以テ第八回会合ヲ本館ニ於テ開催センコトヲ希望セラレ且ツ本館ニ於テハ当春季ニ事務室新築落成記念ノ為メ図書整理事務ニ関スル事項ヲ主トシ併セテ少数ナガラ稀覯図書ノ展覧会ヲ開催スル企画アリシヲ以テ此ノ期ヲ利用シテ本倶楽部ノ会合ヲモ併催セバ多少参考ノ一助トモナランカトノ微意ヨリシテ本館当番幹事トナリ茲ニ春季第八回総会ヲ開キタル次第ナリ然ルニ斯ク多数ノ参会ヲ得殊ニ石川県徳島県等ノ遠隔ナル地方ヨリ参会セラレタルハ本倶楽部ノ為メニ深ク慶賀スル所ナルト同時ニ司会者ニ於テモ亦光栄トスル所ナリ |