平成14年度京都大学附属図書館公開展示会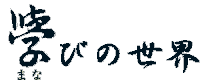 | >>「学びの世界」目次 I: 出版文化のコスモロジー—中国から朝鮮・日本へ— 4: 禅籍と五山版  〔I-4-1〕 〔I-4-1〕  |
|
Ⅰ-4 禅籍と五山版
14世紀以後、元代から明初にかけて、日中間において活発化した文化交流の主要な担い手となったのは、新興の知識人層たる禅僧たちであった。日本の禅僧の間では中国留学熱が起こり、中国からは日本へ高僧があいついで来朝した。彼ら禅僧たちの手により、出版隆盛の時代を迎えた元代中国から日本へ、最新の漢籍刊本が多くもたらされた。日本の禅寺では、これらの中国製木版本を模倣した五山版が盛んに出版された。五山版は禅籍を中心とするが、禅僧が儒仏兼通し詩文や史学にも通ずるという大陸の文化状況を反映して、外典(特に詩文集)も多く刊行され、禅僧が漢詩文に親しむ五山文学が形成されていった。 |
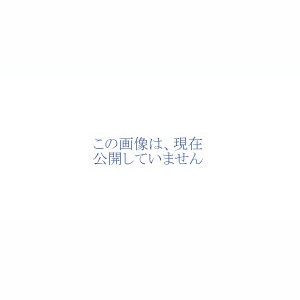 瑞渓周鳳頂相 (図録p.44) |
| 〔I-4-1〕 瑞渓周鳳頂相 総合博物館 文亀2年(1512)恵昌賛 瑞渓周鳳(1393-1473)は三度にわたり相国寺鹿苑院主として禅宗寺院を統轄する僧録に任じられた経歴を持つ、室町時代の代表的な五山僧であり、漢詩文の名手として名高い。その著書として、五山研究に高い史料価値を持つ日記の抜粋『臥雲日件録抜尤』、日本初の外交文書集『善隣国宝記』などがある。 |
電子図書館ホームページ|貴重資料画像
Copyright 2003. Kyoto University Library