旧館報「かりん」
『KALIN』の創刊にともない、旧図書館報『かりん』は2018年をもって終刊しました。2008年12月から2018年12月の11号までご愛読いただき、ありがとうございました。
館報名「かりん」の由来
カリン(Chinese quince)は中国原産のバラ科の落葉高木です。4~5月に淡紅色の可憐な花が咲き、10~11月頃には黄色く熟しただ円形の実が生ります。実は香りがよく、薬効成分「カリンポリフェノール」がのどの炎症に効くため、のど飴でも知られています。
中国の古い詩に「我に投ずるに木李(カリン)を以てす、これに報ゆるに瓊(たま)を以てせん」(彼女は花梨の実をくれた、私はお返しに美しい珠を贈ろう)とあり、カリンは長いよしみをなす意とも、女性の求愛に男性が応える意とも言われます。また、カリン木材は水分含有量の変化が少なく密度が高いため、狂いの出にくい優れた材木と言われます。
図書館報『かりん』は、図書館前の樹木、カリンにちなんでいます。香り高いカリンのように、内容豊かで、世代や分野を問わず幅広く多くの方々に愛されるように、また、利用者の学習や研究成果に結実できるようにという願いをこめて、「かりん」と名づけられました。
「かりん」は京都大学学術情報リポジトリ(KURENAI)で全文公開しています
第11号(2018年12月1日発行)
全文リンクへ

- <巻頭言>定説を疑う寶 馨02
<Prologue>Questioning the OrthodoxyTAKARA Kaoru03 - <声>本の海に漕ぎ出して仲井 慧悟04
<Voices>Rowing Out in the Sea of BooksNAKAI Keigo05 - <声>私と魔物と地下の書庫近藤 真帆06
<Voices>Me, the Demons, and the Underground ArchivesKONDO Maho07 - <声>魂の宿る本と部屋土田 亮08
<Voices>Books and Rooms with a SoulTSUCHIDA Ryo09 - <特集: 吉田南シネマ>みんなの映画中嶋 節子10
<Special Feature: Yoshida-South Cinema>All About Our HouseNAKAJIMA Setsuko11 - <特集: 吉田南シネマ>私の映画体験吉田 万里子12
<Special Feature: Yoshida-South Cinema>My Movie ExperienceYOSHIDA Mariko13 - <特集: 吉田南シネマ>エンドロールから長谷 海平14
<Special Feature: Yoshida-South Cinema>From the Closing CreditsHASE Kaihei15 - <自著を語る>交錯と共生の人類学:オセアニアにおけるマイノリティと主流社会KAZAMA Kazuhiro16
<Author's Book Review>Anthropology of Minorities:Coexistence and Complexity in the Pacific IslandsKATSUMATA Naoya17 - <自著を語る>日本古代宮廷社会の儀礼と天皇吉江 崇18
<Author's Book Review>Rituals and Emperors of Ancient Japanese Imperial Court SocietyYOSHIE Takashi19 - <自著を語る>死が映す近代:19世紀後半イギリスの自治体共同墓地久保 洋一20
<Author's Book Review>Death Reflected in Modern Times:Municipal Cemeteries in the late 19th Century BritainKUBO Yoichi21 - <寄贈図書>吉田南構内各部局教員及び関係者寄贈図書22
Donated booksDonated books from the people concerned with Yoshida-South Campus22 - <特別図書紹介>23
Introduction of Special Collections23 - <図書館の活動>吉田南総合図書館の一年間24
<Activities>Yoshida-South Library Event Calendar24 - <図書館の活動>図書館統計26
<Activities>Statistics of the Library26 - <図書館の活動>貸出回数ランキング27
<Activities>Ranking of books borrowed27
第10号(2017年12月1日発行)
全文リンクへ

- <巻頭言>知的散策のすすめ杉山 雅人02
<Prologue>ake a Stroll of the MindSUGIYAMA Masahito03 - <声>私にとっての図書館鈴木 佑菜04
<Voices>The Library and MeSUZUKI Yuna05 - <声>古典と選書--総人のミカタを振り返って真鍋 公希06
<Voices>Classics and Selected Readings: The Sojin no Mikata Series in ReviewMANABE Koki07 - <声>吉田南総合図書館との10年間のおつきあい長沼 祥太郎08
<Voices>My 10-Year "Friendship" with Yoshida-South Library/NAGANUMA Shotaro09 - <特集: 私の愛読書>万葉秀歌松沢 哲郎10
<Special Feature: My Favorite Books>Man'yo Shuka (Selected Poems from the Man'yoshu)MATSUZAWA Tetsuro11 - <特集: 私の愛読書>人生を変えた一冊山田 剛史12
<Special Feature: My Favorite Books>A Book That Changed My LifeYAMADA Tsuyoshi13 - <特集: 私の愛読書>虔十公園林田中 真介14
<Special Feature: My Favorite Books>The Kenju Park GroveTANAKA Shinsuke15 - <自著を語る>生きるユダヤ教: カタチにならないものの強さ勝又 直也16
<Author's Book Review>Living Judaism: The Power of the IntangibleKATSUMATA Naoya17 - <自著を語る>子育て支援が日本を救う: 政策効果の統計分析柴田 悠18
<Author's Book Review>Child-Rearing Support Can Save Japan: Statistical Analyses on Policy EffectsSHIBATA Haruka19 - <自著を語る>アメリカの大学におけるソ連研究の編制過程藤岡 真樹20
<Author's Book Review>The Process of Organizing Soviet Studies in the United StateFUJIOKA Masaki21 - <寄贈図書>吉田南構内各部局教員及び関係者寄贈図書22
Donated booksDonated books from the people concerned with Yoshida-South Campus22 - <特別図書紹介>23
Introduction of Special Collections23 - <図書館の活動>吉田南総合図書館の一年間24
<Activities>Yoshida-South Library Event Calendar24 - <図書館の活動>図書館統計26
<Activities>Statistics of the Library26 - <図書館の活動>貸出回数ランキング27
<Activities>Ranking of books borrowed27
第9号(2016年12月1日発行)
全文リンクへ

- <巻頭言>私的読書について前川 玲子02
<Prologue>Thoughts on My Own Reading StyleMAEKAWA Reiko02 - <声>休息の場吉田 千裕04
<Voices>Place for RestYOSHIDA Chihiro 04 - <声>「いい本」との出会い方朝田 秀一06
<Voices>How to Meet "Good Books"ASADA Shuichi06 - <声>図書館を巣にして羽尾 一樹08
<Voices>Traveling from the LibraryHAO Kazuki08 - <メディアの多面性>ミディアムとしての映画館木下 千花 10
<Multiplicity of Media>Movie Theaters as MediumKINOSHITA Chika10 - <メディアの多面性>メディア × アートで世界は変わるのか?土佐 尚子12
<Multiplicity of Media>Can the combination of Media × Art change the world?TOSA Naoko12 - <メディアの多面性>分野横断型国際プロジェクトの面白さとコミュニケーションツール加藤 和人 14
<Multiplicity of Media>The Fun in Multidisciplinary International Projects and Communication ToolsKATO Kazuto14 - <自著を語る>ディープ・アクティブラーニング : 大学授業を深化させるために松下 佳代16
<Author's Book Review>Deep Active Learning: Toward Greater Depth in University EducationMATSUSHITA Kayo16 - <自著を語る>レナード・ウルフと国際連盟 : 理想と現実の間で籔田 有紀子18
<Author's Book Review>Leonard Woolf and the League of Nations: Between Ideals and RealityYABUTA Yukiko 18 - <自著を語る>言語への目覚め活動 : 複言語主義に基づく教授法大山 万容20
<Author's Book Review>Awakening to Languages: an educational approach for plurilingual educationOOYAMA Mayo20 - <寄贈図書>吉田南構内各部局教員及び関係者寄贈図書22
Donated booksDonated books from the people concerned with Yoshida-South Campus22 - <特別図書紹介>23
Introduction of Special Collections23 - <図書館の活動>24
Activities24
第8号(2015年12月1日発行)
全文リンクへ

- <巻頭言>ごみの山か宝の山か -アーカイヴズの功罪-新宮 一成02
<Prologue>One Person's Trash is Another Person's Treasure-The Merits and Demerits of Archives-SHINGU Kazushige02 - <声>私と吉田南総合図書館佟 占新04
<Voices>My Relationship with Yoshida-South LibraryTONG Zhanxin04 - <声>あの夏と本田中 仁海06
<Voices>One Summer and a BookTANAKA Hitomi06 - <声>衝撃を育む今村 達哉08
<Voices>Cultivating ShockIMAMURA Tatsuya08 - <私の考える国際化>国際化時代の西洋史研究について合田 昌史10
<Internationalization in My Eyes>Study of Western History in an Era of InternationalizationGODA Masafumi10 - <私の考える国際化>一歩ずつ着実に、堅実に!丸橋 良雄12
<Internationalization in My Eyes>The Course of True Internationalization Never Runs SmoothlyMARUHASHI Yoshio12 - <私の考える国際化>冒険の香りシバニア イーサン14
<Internationalization in My Eyes>The fragrance of adventureSIVANIAH Easan14 - <自著を語る>アメリカ教育福祉社会史序説 : ビジティング・ティーチャーとその時代倉石 一郎16
<Author's Book Review>A Social History of Education : Welfare in the United States - The Era of Visiting Teachers -KURAISHI, Ichiro16 - <自著を語る>総合生存学 : グローバル・リーダーのために藤田 正勝18
<Author's Book Review>Integrated Studies in Human Survivability : Developing Global LeadersFUJITA, Masakatsu18 - <自著を語る>アクティブラーニングと教授学習パラダイムの転換溝上 慎一20
<Author's Book Review>Active Learning and Paradigm Shift From Teaching to LearningMIZOKAMI Shinichi20 - <寄贈図書>吉田南構内各部局教員及び関係者寄贈図書22
Donated booksDonated books from the people concerned with Yoshida-South Campus22 - <特別図書紹介>23
Introduction of Special Collections23 - <図書館の活動>24
Activities24
第7号(2014年12月1日発行)
全文リンクへ

- 図書館の一年間
- <巻頭言>περιπατειν林 信夫01
- <声>書庫との出会い中元 洸太02
- <声>戻ってきました佐伯 直樹03
- <知の世界を逍遥する>教養部があった頃高橋 由典04
- <知の世界を逍遥する>教養教育に想う川井 秀一05
- <知の世界を逍遥する>オープンで自由な学び 映画、大学、図書館、そしてインターネット飯吉 透06
- <知の世界を逍遥する>ノンフィクションで知る技術の進化の面白さ喜多 一07
- <知の世界を逍遥する>国際化、学際化からみた逍遥館への期待北川 進08
- <知の世界を逍遥する>図書館にないものと公文書館の必要性伊從 勉09
- <自著を語る>イタリアン・セオリー岡田 温司10
- <自著を語る>貨幣と欲望佐伯 啓思11
- <自著を語る>都市を冷やすフラクタル日除け ― 面白くなくちゃ科学じゃない ―酒井 敏12
- <寄贈図書>吉田南構内各部局教員及び関係者寄贈図書13
- <図書館愛称によせて>知の世界を逍遥せよ!辻 正博14
- <グレート・ブックス読書会によせて>矛盾・問い・共感小林 哲也15
- <特別寄稿>光合成をやめた不思議な植物の生活に迫る末次 健司16
- <特別図書紹介>18
- <図書館の活動>19
第6号(2013年12月1日発行)
全文リンクへ

- 人環・総人図書館の一年間
- <巻頭言>電脳読書宮本 嘉久01
- <声>猫喫茶としての図書館開 信介02
- <声>やあ、もちろん森口 遥平03
- <新しい一歩>破れかぶれな一歩篠原 資明04
- <新しい一歩>本に背中を押されて新しいステップを刻んだ菅原 和孝05
- <新しい一歩>ためらいと見境ない決断瀬戸口 浩彰06
- <自著を語る>グループ・ダイナミックス入門杉万 俊夫07
- <自著を語る>治承・寿永の内乱と平氏元木 泰雄08
- <自著を語る>政策研究のための統計分析浅野 耕太09
- <寄贈図書>教員及び関係者寄贈図書10
- <特別図書紹介>平成24年度 特別図書11
- <特別図書紹介>英國國家圖書館藏敦煌遺書Chinese Manuscripts from Dunhuang Collected in British Library辻 正博12
- <特別寄稿>『ゆとり京大生の大学論』ができるまで― ある学生から見た大学組織改革安達 千李14
- <図書館のあゆみ>16
- <情報収集のコツ>18
- <図書館の活動>20
第5号(2012年12月1日発行)
全文リンクへ

- 人環・総人図書館の一年間
- <巻頭言>ロンドンの中のスクエア、スクエアの中のイギリス間宮 陽介01
- <声>知的刺激との出会い方米重 大海02
- <声>僕とトロント、ときどき京都。橋井 崚佑03
- <私の進む道を決めた一冊>数学の冒険立木 秀樹04
- <私の進む道を決めた一冊>ドイツ悲劇の根源道籏 泰三05
- <私の進む道を決めた一冊>地球の科学 大陸は移動する石川 尚人06
- <自著を語る>一人称小説とは何か ― 異界の「私」の物語廣野 由美子07
- <自著を語る>スラヴ語入門三谷 惠子08
- <特別図書紹介>平成22ー23年度 特別図書09
- <特別図書紹介>「フランス小説に描かれた日本」西山 教行10
- <特別図書紹介>Documentary Educational Resources: “!Kung series”,“India series”金子 守恵12
- <特別寄稿>フラミンゴの舞台裏澤西 祐典14
- <寄贈図書>16
- <情報収集のコツ>18
- <図書館の活動>20
第4号(2011年12月1日発行)
全文リンクへ

- 人環・総人図書館の一年間
- <巻頭言>図書館東側の小径の風景冨田 恭彦01
- <声>卒業生・学外者にとっての大学図書館百木 漠02
- <声>準総合図書館の魅力島津 夢太03
- <自分の地図を持とう>地図だけではわからないことがいっぱいある大木 充04
- <自分の地図を持とう>こだわりから生まれるオリジナルな《地図》山田 孝子05
- <自分の地図を持とう>吉田南キャンパスの“地図”をつくろう阪上 雅昭06
- <自著を語る>漢字と日本人の暮らし阿辻 哲次07
- <自著を語る>生命は細部に宿りたまう : ミクロハビタットの小宇宙加藤 真08
- <所蔵資料紹介>図書館で映画芸術を探究する加藤 幹郎09
- <研究紹介>パズルを研究する旅東田 大志13
- 寄贈図書15
- 大型コレクション>近世近代イギリス新聞アーカイブ"British Newspapers 1600-1900"16
- <情報収集のコツ>「こうすればいい」が分かる! Jinkan-Soujin Library Tips17
- <図書館の活動>20
第3号(2010年12月1日発行)
全文リンクへ

- 人環・総人図書館の一年間
- <巻頭言>筆記する川島 昭夫01
- <声>古びた書物をひらけば西村 木綿02
- <声>私のお気に入り、人環・総人図書館原田 久人03
- <漢籍目録紹介>いまなぜ『京都大学大学院人間・環境学研究科漢籍目録』なのか松浦 茂04
- <原書を読むチカラ>原典にあたる必要性河﨑 靖05
- <原書を読むチカラ>チカラは最初から具わっている(ただし朝鮮語の場合)小倉 紀蔵06
- <原書を読むチカラ>連想された力中森 誉之07
- <自著を語る>人間形成にとって共同体とは何か―自律を育む他律の条件―岡田 敬司08
- <自著を語る>カエル・サンショウウオ・イモリのオタマジャクシハンドブック松井 正文09
- <所蔵資料紹介>新しい漢籍と古い漢籍―三高蔵書の特色について―道坂 昭廣10-12
- 教員及び関係者寄贈図書13
- <大型コレクション>British Periodicals Collection14
- <情報収集のコツ>論文を効率的に探して手に入れるには15-18
- <図書館の活動>遡及入力事業について19
- <図書館の活動>図書館統計20
- <図書館の活動>貸出回数ランキング21
第2号(2009年12月1日発行)
全文リンクへ

- 人環・総人図書館の一年間
- <巻頭言>ネビュラス堀 智孝01
- <声>机と棚岡本 源太02
- <声>ささやかな議論の場霜田 洋祐03
- <学術情報リポジトリ>『言語科学論集』の紹介山梨 正明04-05
- <勉強法・研究法を伝授>学問の要諦は対話にあり東郷 雄二06
- <勉強法・研究法を伝授>「精聴」の勧め藤田 糸子07
- <勉強法・研究法を伝授>「図書館」へ行こう西井 正弘08
- <勉強法・研究法を伝授>数学、物理は丸暗記宮本 嘉久09-10
- <自著を語る>戦後教育のジェンダー秩序小山 静子11
- <自著を語る>アラブ、祈りとしての文学岡 真理12
- <自著を語る>基礎環境化学 : 環境を化学反応から捉えるためのエッセンス津江 広人13
- <所蔵資料紹介>利用という面での地図の価値小原 丈明14-16
- <環on映画会>環on映画会へのお誘い17
- <環on映画会>私にとって環on映画会とは?ナザロワ エカテリナ (NAZAROVA Ekaterina)18
- <環on映画会>環on映画会ポスター制作秘話宮下 芙美子18
- <寄贈図書>19-21
- <特別図書>22
- <情報収集のコツ>KULINEとMyKULINE23-26
- <図書館の活動>人環・総人図書館の一年間27
- <図書館の活動>図書館・室利用者アンケート調査報告 人環・総人図書館28-31
- <図書館の活動>図書館統計32
- <図書館の活動>貸出回数ランキング33
創刊号(2008年12月15日発行)
全文リンクへ
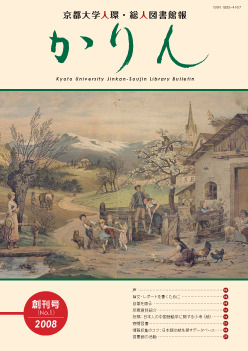
- 人環・総人図書館の一年間
- <巻頭言>図書館の愉楽内田 賢徳01
- <声>図書館の魅力籔田 有紀子02
- <声>居場所佐野 太南03
- <論文・レポートを書くために>私の実践的論文作法奥田 敏広04
- <論文・レポートを書くために>文系世界の経験から水野 眞理05
- <論文・レポートを書くために>化学系の論文を書くには(Q&A)田部 勢津久06-07
- <自著を語る>メタボにならない脳のつくり方森谷 敏夫08
- <自著を語る>イザベラ・バード 極東の旅1・2金坂 清則09
- <自著を語る>火山噴火-予知と減災を考える鎌田 浩毅10
- <所蔵資料紹介>日本重要水産動植物図と田中芳男松田 清11-14
- <投稿>日本人の中国語勉学に関する小考(続) -補語を中心に-劉 志偉15-20
- <寄贈図書>21-23
- <大型コレクション・特別図書>24
- <情報収集のコツ>日本語文献を探すデータベース-CiNii特集-25-28
- <図書館の活動>話せる図書館 環on29
- <図書館の活動>人環・総人図書館の一年間30
- <図書館の活動>貸出回数ランキング31
- <図書館の活動>図書館統計32
- <図書館の活動>京都大学学術情報リポジトリ 紅(KURENAI)33
旧館報『バベルの図書館』(1996-2008)
『かりん』の創刊にともない、旧図書館報『バベルの図書館』は2008年をもって終刊しました。
1996年7月から2008年3月の23号まで長らくご愛読いただき、ありがとうございました。