平成14年度京都大学附属図書館公開展示会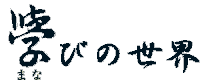 | >>「学びの世界」目次 II: 『幼学指南鈔』とその周辺—日本での受容— 1: 幼学指南鈔  〔II-1-1〕 〔II-1-1〕 
|
 幼学指南鈔 巻七(京都大学蔵本) (図録p.59上) |
| 〔II-1-1〕幼学指南鈔 附属図書館 04-85/ヨ/01貴 編者不詳、 [平安末期]写、2巻(巻7、22) [重要文化財] 『幼学指南鈔』は、平安末期に邦人の手により編纂された類書である。本来は三十巻に目録一巻を添えた全三十一冊であったと推測されるが、現在では目録を含む八巻は失われ、残りは今回写真掲載を許可された陽明文庫のほか、故宮博物院、大東急記念文庫等、諸家の分蔵するところとなっている。 故宮博物院蔵の巻十七の途中に「久安三年二月一日 大江時房」という墨書が見られること、また各冊末に所蔵者であったとおぼしき「覚瑜」の署名があり、覚瑜の活動時期が承元4年(1210)頃と推定されることから、その成立時期は平安末期と比定されている。また陽明文庫蔵の『幼学指南目録』から明らかになる全体の部類が『藝文類聚』によく一致することや、本文内容の対照などから、『幼学指南鈔』も先立つ『秘府略』などの和製類書同様、『藝文類聚』『初学記』『事類賦』といった中国類書からの引用の多いことが指摘されている。京大本は後補の藍色楮紙表紙に模して修復がなされているが、陽明文庫本は、共紙原前表紙の表面に原布表紙と思われるわずかな裂を認めることができる。また両者とも前表紙端に八双を残すなど、装幀の古体を伝える点でも貴重である。 |
電子図書館ホームページ|貴重資料画像
Copyright 2003. Kyoto University Library