平成14年度京都大学附属図書館公開展示会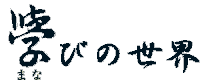 | >>「学びの世界」目次 III: 学びの展開と継承 3: 抄物  〔III-3-1〕 〔III-3-1〕  |
|
Ⅲ-3-1 抄物
抄物は、室町中期から現れる資料で、中国原典に対して、仮名で解説注釈を加えたものである。抄物は、講義のための「手控え」と、講義を聞いて作った「聞書」に大別できる。抄物は講義に関わるものであるため、当時の世相に触れたり、口語的な表現が現れたりして、当時の社会や言葉を知る上でも重要な資料となっている。漢籍の抄物のうち、儒教経典は明経博士家が、紀伝道の管掌した史記、漢書、それに各種の詩集などは五山僧が扱うようになっていた。禅籍の抄物はもちろん禅僧たちの周辺で作られ、神道関係のものは、清原宣賢の実父である吉田兼倶の周辺で作られていた。 |
 印鑑図(1) (図録p.135右) |
| 〔参考〕 寿岳文庫 文学部 寿岳文庫とは、元京都府立大学教授・寿岳章子氏が収集した抄物のコレクションで、平成12年度京都大学文学部に寄贈された。66点の抄本・刊本よりなり、一括して文学部の貴重書となった。寿岳章子氏は、抄物がまだあまり注意されていない時代から抄物に注目し、研究され、抄物の擬態語・擬声語、口語資料としての特徴などを分析された。抄物研究のパイオニアの一人である。 |
電子図書館ホームページ|貴重資料画像
Copyright 2003. Kyoto University Library