[Maintenance]J-STAGE / Journal@rchive (8/29-30)
Sep. 7-9, the 3rdd SPARC Japan Seminar/DRFtech-Kyoto
9月7-9日に、京都大学附属図書館ライブラリーホールで、京都大学学術情報リポジトリ(KURENAI)事業に関連する、2つのイベントを実施します。 お申し込み不要、参加自由です。学外からお越しになる方は、附属図書館入口カウンターに申し出て入館してください。 ■(1)■第3回 SPARC Japan セミナー2009/RIMS 研究集会 「数学におけるデジタルライブラリー構築へ向けて-研究分野間の協調のもとに」 https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2009/20090908.html ○日時 : 平成21年9月8日(火) 13:30-16:00 平成21年9月9日(水) 10:00-15:50 ○場所 : 京都大学附属図書館 ライブラリーホール https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/mainlib/map/3f ○主催 : 京都大学数理解析研究所 ○共催 : 国立情報学研究所 国際学術情報流通基盤整備事業 (SPARC Japan) 京都大学図書館機構 ○概要 : 京都大学数理解析研究所(RIMS)ではRIMS研究集会「数学におけるデジタルライブラリー構築へ向けて」を開催します。2005年から2008年までに開催した研究集会「紀要の電子化と周辺の話題」では主に数学系ジャーナルおよび紀要等の電子化に関する研究成果の発表と諸分野との情報交換とが中心でした。今回は世界的なDigital Mathematics Library(DML)構築の流れを受け、これまでに蓄積した成果および問題意識を諸分野の各ジャーナルおよびデジタ ルリポジトリと共有し、同時に諸分野の成果と問題点との関わりを議論する場とします。数学と直接の関連をもたない研究分野のジャーナルでも数式を含む論文が多数含まれることは珍しくありません。数学においても多様なメディア等への対応、computationの発達に伴うeScience的なデジタルライブラリーの構築には諸分野での経験が活かせると考えます。日本において学術情報コミュニケーションを実際に担うグループは必ずしも大きくなく、数学分野と諸分野との相互交流を深めることで学術コミュニケーション全体を活性化することは必ずそれぞれの分野に還元されるはずですので、この機会にご参集いただければ幸いです。 研究代表者:行木 孝夫(北海道大学大学院理学研究院) ●プログラム ---------- 9月8日(火) ---------- 13:30-14:10 麻生和彦(東京大学数理科学研究科) 「東京日光シンポジウム(1955)講演音声テープのデジタル化とその活用方法」 14:30-15:00 西村暁子(京都大学附属図書館情報管理課) 「図書館の電子ジャーナル化事業:KURENAIの数学文献を中心に」 15:20-16:00 佐藤翔(筑波大学図書館情報メディア研究科) 「機関リポジトリのアクセスログ解析:分野別傾向」 ---------- 9月9日(水) ---------- 10:00-10:50 高久雅生(物質・材料研究機構科学情報室)、 谷藤幹子(物質・材料研究機構科学情報室) "NIMS eSciDoc - a Subject Repository in Materials Science and Its Applications Towards eScience" 11:00-11:50 Malte Dreyer (Director, Max Planck Digital Library, Germany) "eSciDoc, Data Repository in Science --- Trends and Practice in Europe" 13:20-13:50 行木孝夫(北海道大学大学院理学研究院)、黒田拓(北海道大学大学院理学研究院) 「国内数学系ジャーナルの概要とDigital Mathematics Library」 14:00-14:30 横井啓介(東京大学大学院情報理工学系研究科)、相澤彰子(国立情報学研究所) 「デジタルライブラリーにおける類似数式検索」 14:40-15:10 鈴木昌和(九州大学大学院数理学府) TBA (文書処理における数式認識技術) 15:20-15:50 Mira Waller and David Ruddy (Project Euclid) TBA (Overview of Project Euclid) プログラムについて詳しくは、下記の案内をご覧ください。 https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2009/20090908.html ■(2)■DRF技術ワークショップ(技術と研究が出会うところは) 「Workshop of Application of Repository Infrastructure for eScience and eResearch ----研究成果やデータを永久保存していく活動へ向けて」 ○日時: 2009年9月7日(月)13:00-16:30 ○場所:京都大学附属図書館ライブラリーホール https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/mainlib/map/3f ○主催:Digital Repository Federation (DRF), 独立行政法人物質・材料研究機構 ○共催:京都大学図書館機構 ○対象:IR技術者(思想設計・システム開発にかかわってきた人) IR利用者(研究者・研究分野を超えて主役として成果の保存と発信に関心のある人) そのほか一般の方の参加も歓迎します ○企画趣旨: 研究成果やデータを永久保存していく活動は、研究組織の維持や発展のために必要なシステムであると同時に、研究者のセルフアーカイブすなわちprivate libraryとして日常的に利用でき、かつ発信力をもって流通することが可能な仕組みに研究者も関心を持つようになりました。例えば研究室内の研究成果や実験データなどを研究室サーバーに集積して、研究室内で共同利用したり、個人でデータベースを構築してホームページから公開することも普通に行われるようになりました。そのような日常において、安定し、永続的に継承できる知識アーカイブとしての仕組み(インフラストラクチャ)が、昨今の様々なウェブ技術や無料サービス、あるいはオープンソースのソフトウエアで実現できるようになり、それらをデジタルアーカイブ(リポジトリ、データベース)あるいはeScience,eResearchと称して研究環境全体を包括して捉えられる時代にまで進んできました。そのような中で、技術志向に陥ることなく、しかし研究者の体温にあったアーカイブ環境はいかなるもので、それに応える技術やウェブ社会の方向性、といったところをざっくばらんに話す座談の場として本ワークショップを企画しました。研究分野や年代による違い、あるいは組織や国を超えて、科学研究の永続的な保存と発信に向かって、認識を共にする方々の参加をお待ちしています。また飛び入りプレゼンも歓迎します。 物質・材料研究機構 谷藤幹子・高久雅生 ●プログラム <テーマ1 研究環境を理解する> 13:00-14:30 研究者が日常的に使う情報環境と望むこと(資源、データ形式、取り出し、自前DBとの同期など).研究分野を越えたメタデータ/コンテンツ共有の必要性・可能性・問題点 ・行木孝夫(北大、数学分野、研究者視点) 「Network of Digital Repository in mathematics community」 ・轟眞市 (物材機構研究員、材料科学分野、研究者視点) 「セルフアーカイビング事例から読み解く、研究情報環境が備えるべき機能」 ・植田憲一(電通大教授、研究者視点)、米田仁紀(電通大准教授、研究者視点) 「(演題未定)」 <テーマ2 情報環境を共有する> 14:30-15:50 世界で進むデータアーカイブの動き、日本のIRアプリケーション(今やっていること、考えていること)、そのためのリポジトリアプリケーションの可能性・実効性 ・坂東慶太(My Open Archive、システム視点) 「草の根リポジトリ活動から見た、学術流通とリポジトリ」(仮題) ・Malte Dreyer (マックスプランクデジタルライブラリー、インフラ視点) 「New phase of eSciDoc -- Solution for eScience, Comparison of IRsoftwares」 ・高久雅生 (物材機構エンジニア、システム視点) 「NIMS eSciDoc -- a feedback from Japanese aspects」 <テーマ3 横断的にディスカッション> 15:50-17:30 将来の科学情報資源をざっくばらんに議論しましょう。YouTubeなどの画像、FaceBookなどのSNS、蓄積した情報資源の活用技術(辞書化、意味検索、分類、編集からパーソナライズまで) ・杉田茂樹、鈴木雅子(デジタルリポジトリ連合) 「“Beyond Institutional Repositories”及び“Beyond Romary & Armbruster on Institutional Repositories”レビュー」 ・長神風二(東北大脳科学グローバルCOE特任准教授) 「リポジトリからe-Scienceへ:サイエンスコミュニケーターからの提案」(仮題) プログラムについて詳しくは、下記の案内をご覧ください。 [図書館機構]
KURENAI exceeded four million papers / Interview with TERAMOTO, Yoshikuni(Graduate School of Agriculture, Kyoto University)
 となりました。
4万件目を記念して、寺本好邦先生にインタビューをお願いしました。
●寺本好邦先生 - 京都大学大学院農学研究科森林科学専攻生物材料機能学講座 (助教)
http://www.fukugou.kais.kyoto-u.ac.jp/teramotoj.htm
http://www.fukugou.kais.kyoto-u.ac.jp/frame_indexj.htm
Q1: ご専門の分野について教えてください。
となりました。
4万件目を記念して、寺本好邦先生にインタビューをお願いしました。
●寺本好邦先生 - 京都大学大学院農学研究科森林科学専攻生物材料機能学講座 (助教)
http://www.fukugou.kais.kyoto-u.ac.jp/teramotoj.htm
http://www.fukugou.kais.kyoto-u.ac.jp/frame_indexj.htm
Q1: ご専門の分野について教えてください。
A1:木材とその構成成分(セルロース,リグニン等)をはじめ,関連する多糖類など各種生物由来素材を対象に,その分子・材料特性を究めつつ,異種素材との複合化による機能材料化やリファイニングによるエネルギー変換に関する研究を行っています.Q2: 今回の論文はどのような内容でしょうか? また、研究の進展によってどのようなことを明らかにしようとされているのでしょうか?
A2:今回の論文は,木材からのバイオエタノール生産に必要な前処理技術について報告するもので,主に前の所属先の(独)産業技術総合研究所で検討した結果がベースとなっています.原油価格高騰の折にしばしば報道されたガソリンに代わるバイオエタノールは,既にトウモロコシデンプンや砂糖(ショ糖)から生産され上市されています.その一方で,単位面積当たりの蓄積量が大きく食糧用途と競合しない木材に含まれるセルロースをグルコースに変換(糖化)し,それを発酵してエタノールを生産する技術を確立しておくことは,長期的には重要な課題です.セルロースもデンプンもグルコースが繋がった構造をとっていますが,結合様式が異なるため前者は強固な分子が集まった結晶構造をとっています.さらに樹木中のセルロースは,分子集合体レベルではリグニンやヘミセルロースと複合化されており,それらが集まって細胞?繊維?繊維集合体に至る階層構造を有しています.階層構造があることで樹木は巨大生物として生き長らえることができるのですが,逆に言えば樹体支持を目的とした構造をバラバラにして糖化に持ち込むのは一般には困難です.そのため,木材糖化には厳しい処理が必要という先入観があるのですが,この論文ではエネルギー投入量やプロセスの環境対策を考慮した穏やかな処理でも木材の酵素糖化率を高められるということを実験的に示しました.今後はこの処理の効果を構造論的に解明し,酵素糖化率と構造要因の相関を示す何らかの尺度を見出すことが課題です.Q3: 今回KURENAIに登録していただいた論文をどのような方に読んでもらいたいですか?
A3: 私自身はこれまで恵まれていましたが,研究環境によっては電子ジャーナルを気軽に使えないところもあるかと思いますので,そういうところへの情報発信に繋がれば良いと思います.身近なところでは投稿論文の体裁を知りたい学生さんにも向いているかもしれません.Q4: 先生のご専門の分野ではどのような学術雑誌に1年間でだいたいどれくらいの数の論文を投稿されるが一般的ですか?
A4: 私の分野の助教クラスの研究者であれば,自分が密接に関わった論文を1年間に2報以上は発表したいと考えていると思います.個人的には,自ら進めている研究のほかに,現状では修士課程を修了して就職する学生さんが多いので,在学中に学生さんがメインで論文を執筆し国際的なジャーナルに1報は投稿できる状態にしておくというのが理想的だと考えています.それが間に合わなくても,そう遠くない時期に学生さんが著者となった論文を投稿することを目標としています.Q5: 先生が論文を収集・執筆される際によく使われる電子ジャーナルやデータベースは何でしょうか?
A5: 普段はWeb of Science(Thomson Reuters社)を主に使っています.論文執筆の際に,より幅広いデータを統合的に検索できるSciFinder Scholar(CAS)を使うことがあります.Q6: 京大の研究成果をインターネット上に公開するKURENAIの取り組みについてご意見・ご感想をお願いします。
A6: 国際的なジャーナルで成果発表するのが一般的な分野でも,研究者のウェブサイトの業績欄からリポジトリに,著作権のことをあまり気にせず(?)リンクを張れるので,中身の濃い情報発信ができる使いでのあるサービスだと思います. これからどんどん全国の大学等でデータ蓄積が進んでいくことと思いますが,その先には国内の大学等を統合したデータベースに,さらには世界的なデータベースへの統合が進むのでしょうか.どの程度の規模がベストなのかはわかりませんが・・・.*(図書館補足)学術雑誌掲載論文の著作権は学術雑誌出版社側に移譲されていることが一般的ですが、その利用条件の1つとして、所属機関のホームページで原稿を公開することを認める、としている出版社も多くあります。リポジトリ事業では、その点を考慮し、大学の研究成果を大学自身が広報するという立場で論文を主に原稿形式で公開しています。 なお、先生のご指摘のとおり、国内の統合データベースとしてCiNiiやJAIROから、世界的規模ではGoogle/Google ScholarやScopusからも、KURENAIの収録論文を検索することが可能になっています。 寺本先生、お忙しい中、研究活動や研究成果の発表の仕方がよく分かる丁寧なコメントありがとうございました。 KURENAI事業では、寺本先生にご指摘いただいたように、電子ジャーナルを気軽に使えない多くの研究の現場に、国際的ジャーナルに掲載される京都大学の最先端の研究成果を届けられるように、努力していきたいと思います。 また、研究者ご自身の業績リストを補完するものとして、研究活動の広報に使っていただけるような事業にしていきたいと思います。 ◆京大論文アーカイブ【KURENAI(京都大学学術情報リポジトリ)】
 - 現在約4万件以上の京大研究者の論文を提供
[附属図書館電子情報掛]
- 現在約4万件以上の京大研究者の論文を提供
[附属図書館電子情報掛] RIMS Kokyuroku v749-899, 1540-1600 available on KURENAI
 ○京都大学数理解析研究所
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/ja/index.html
◆京都大学発行電子ジャーナル (E-Journals published by Kyoto University on KURENAI)
○京都大学数理解析研究所
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/ja/index.html
◆京都大学発行電子ジャーナル (E-Journals published by Kyoto University on KURENAI)
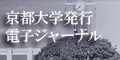 - 現在約80誌以上の京大発行の学術雑誌を提供
◆京大論文アーカイブ【KURENAI(京都大学学術情報リポジトリ)】
- 現在約80誌以上の京大発行の学術雑誌を提供
◆京大論文アーカイブ【KURENAI(京都大学学術情報リポジトリ)】
 - 現在約4万件以上の京大研究者の論文を提供
[附属図書館電子情報掛]
- 現在約4万件以上の京大研究者の論文を提供
[附属図書館電子情報掛]